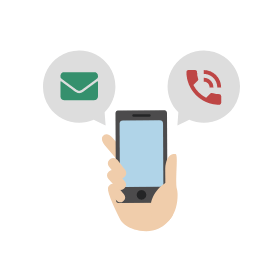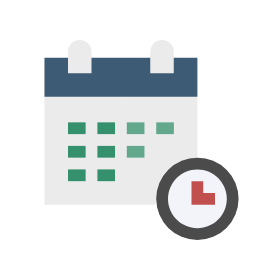【労災・残業代・解雇に注力】法律事務所クレシェンド
東京都品川区小山台1-8-12
【見積もり無料】労災の損害賠償額、残業代を無料で試算。【完全成功報酬制◎】労働問題であれば、全国どこに居ても依頼が可能です!特に労働災害/残業代請求/不当解雇に注力◎ご相談者様の権利を守る為に戦います!【相談料0円】
【メール歓迎】中野 雅也(飯田橋法律事務所)
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン727
【弁護士歴14年】退任代行・退職代行・不当解雇に注力◆取締役を辞任したい/任期途中で解任された◆解雇された/解雇通知を受けた等◆夜間休日面談可◆飯田橋駅すぐ・仕事帰りの面談◎※ハラスメントは対応しておりません
しみず法律事務所
東京都中央区銀座6-12-15いちご銀座612ビル5階A-1
◆初回相談無料◆夜間・休日の相談可◆労働問題解決実績300件以上!豊富な経験を活かし、残業代請求、解雇、労働災害など幅広い問題に対応。信頼関係を大切に、最善の解決ができるよう全力でサポートします◆企業側の相談◎
【残業代の請求なら】弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
【不当解雇・残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8アーバンセンター横浜ウエスト10階
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
埼玉中央法律事務所
埼玉県さいたま市大宮区宮町2-28 あじせんビル4階・6階
【残業代/不当解雇/労災のご相談は相談料0円】労働者側で労働事件を専門的に扱う日本労働弁護団に所属。年間労働相談150件超の経験と実績。労使紛争の調整を行う埼玉労働局あっせん委員(現職)。頂いたお電話には弁護士が出ますので、その場でご相談可能です。
弁護士 阿部・薗田・大杉(伊倉総合法律事務所)
東京都港区虎ノ門4-1-14神谷町プラザビル4階
【残業代請求/不当解雇/雇止め/内定取消事案は着手金0円・成功報酬制】労働問題の実績多数!経験豊富な弁護士があなたに寄り添い、労働者の権利を守るために徹底サポートいたします。【初回相談無料】
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
東京都新宿区西新宿6-6-3 新宿国際ビルディング新館8階
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
NN赤坂溜池法律事務所
東京都港区港区赤坂2-12-12Martial Arts 赤坂溜池山王ビル5階
【証券会社勤務/社会人経験20年以上】◆外資系・役員の方◆ご相談者様の立場を理解しているからこそ、迅速で的確な対応が可能です!《解決実績多数》詳細ページをご確認ください。
【退職問題に注力】下地法律事務所
東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス ※Googleマップ上の住所記載が異なる場合もございますが、こちらが正しい住所になります。
【初回相談30分無料/オンライン対応/最短即日 面談OK◎】不当解雇/退職勧奨/給与未払いなどにも幅広く対応◎退職代行は11万円で代行手続き~退職条件の交渉までお任せ!慰謝料請求や未払い残業代も同時に対応◎経験豊富な弁護士があなたの「強い味方」となります
【解雇/残業代のご相談は初回無料】柏リバティ法律事務所
千葉県柏市末広町5-16エスパス5階G号
【権利を守るための一貫したサポート】上司から突然解雇を告げられた/未払いの残業代を請求したい方はお早めにご相談を◆解決への見通しを明確にしながら、会社との交渉から訴訟まで幅広くサポートいたします【初回相談0円】
【不当に解雇されたら】弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
千葉県船橋市本町7-11-5 KDX船橋ビル6階
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
弁護士 田村 有規奈(法律事務所UNSEEN)
東京都千代田区平河町1-6-4H1O平河町6階
【初回相談30分0円】【オンライン面談対応】労働問題の経験豊富な女性弁護士がご相談者様にとってベストな解決を目指します!不当解雇/残業代請求/ハラスメントなど労働トラブルは1人で悩まずにご相談ください。
かせだ法律事務所
東京都中央区八丁堀4-12-7サニービル5階B号室
【初回相談無料】不当解雇/解雇予告/残業代請求/退職金未払いなど◆示談交渉に強みあり!裁判になる前にスピード解決を目指します◆最初から最後まで1人の弁護士が対応◆諦めてしまう前にご相談ください!
【残業代請求/不当解雇実績多数◎】弁護士法人ゆかり法律事務所
東京都新宿区高田馬場4-4-17山根ビル203
【未払給与・残業代の請求は着手金0円の完全成功報酬!】労働者の権利と生活を守るため迅速対応いたしますので、労働トラブルはお早めに当事務所へご相談を!不当解雇の着手金分割払い可◆【初回面談0円】
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
神奈川県川崎市川崎区砂子二丁目11番29号平松川崎ビル5階
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
【メール相談歓迎】弁護士 中村 新(銀座南法律事務所)
東京都中央区銀座7-17-2アーク銀座ビルディング5階
【弁護士歴20年以上|初回相談0円】解雇・雇い止め・残業代請求など労使トラブルに注力/労働局あっせん委員・上場企業社外役員などの経験を持つ弁護士が一貫対応/証拠集めからサポート≪詳しくは写真をクリック≫
弁護士 金井 啓(小笹勝弘法律事務所)
神奈川県横浜市中区本町2-19弁護士ビル6階
【初回相談無料】【弁護士直通】年間相談件数200件以上/不当解雇・内定取り消し・雇い止め・退職代行など労働問題全般に対応/元派遣社員の弁護士が一貫対応【オンライン面談・全国対応】
弁護士君和田・江夏・川口(東京法律事務所)
東京都千代田区永田町2-14-2山王グランドビル3階
【60年の歴史と実績】【赤坂見附駅/永田町駅からすぐ】1955年設立の老舗事務所です。労働審判によるスピード解決ならお任せください。残業代・不当解雇・労災等、数多くの労働事件を解決しております。
【不当に解雇されたら】弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】
【メール歓迎】キャリアディフェンダー法律事務所
東京都渋谷区広尾1-4-10鴻貴ビル4F
【最速1か月】【オンライン完結】退職パッケージ交渉に注力◆企業法務歴15年の弁護士があなたの資産とキャリアを守ります!【外資系/ベンチャー】【取締役・執行役員・部長・課長】【初回面談0円】【不当解雇】≪ページ下部に、正社員の退職勧奨・不当解雇専門サイトあり!≫
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
千葉県千葉市中央区富士見2-3-1塚本大千葉ビル9階
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
【残業代の請求なら】弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
【不当解雇・残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】