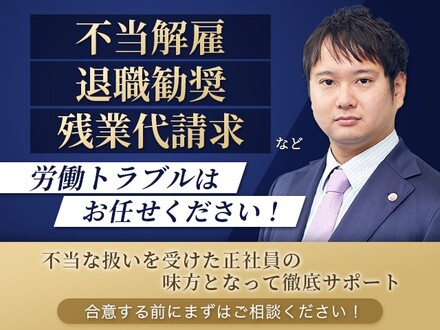【労働者向け】会社に訴えられたら?訴訟の大まかな流れと裁判になったときのポイント


- 「会社に訴えられたあとの対応を知りたい」
- 「自分を訴えた会社と全面的に争いたい」
会社との間で法的トラブルが発生し、 会社に訴えられることもあるでしょう。
しかし、訴訟の経験がない(少ない)方からすれば、訴えられたときに何をすればよいかわからないはずです。
そこで本記事では、会社から訴えられた方に向けて以下の内容について解説します。
- 会社から訴えられる可能性があるケース
- 会社から訴えられてから判決が下されるまでの流れ
- 会社から訴えられた際に労働者がとるべき4つの対応
- 会社から訴えられた方が弁護士に相談・依頼すべき理由
本記事で会社に訴えられたあとにすべきことを理解し、今後の方針や対応などについて検討しましょう。
会社から訴えられる可能性がある3つのケース
労働者が不法行為や犯罪をすれば、会社から訴えられる可能性があります。
ここでは、労働者が会社に訴えられる可能性がある3つのケースについて解説します。
1.故意に会社に損害を与えた場合
労働者が故意に(わざと)会社に対して損害を与えた場合、労働者は損害賠償責任を負うことになります。
たとえば、以下のようなケースでは、会社から不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性があるでしょう。
- マニュアルを守らずに機械を操縦し壊した
- 上司の指示を無視して取引し損害が発生した
- 会社の貸与物をわざと壊したり、なくしたりした など
なお、労働者が故意に会社に損害を与えた場合は、労働者はその損失について全額を賠償する必要があります。
2.過失で会社に損害が生じた場合
労働者の過失(不注意)によって会社に損害が生じた場合も、労働者は損害賠償責任を負う可能性があります。
過失の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 個人情報の管理が不十分で漏洩してしまった
- 社用車を運転中に不注意で交通事故を起こした
- 建設現場の監督を怠り、事故が発生してしまった など
しかし、故意の場合と異なり、過失の場合は会社にも一定の責任があると考えられます。
そのため、労働者の責任の一部が制限されたり、そもそも労働者に責任がないと判断されたりすることもあります。
3.業務上横領などの犯罪をした場合
刑法をはじめとする各種法律に違反した場合、会社に刑事告訴される可能性があります。
仕事に関連して成立する犯罪と具体的な行為については、以下のとおりです。
|
犯罪 |
具体例 |
|
業務上横領罪(刑法第253条) |
|
|
背任罪(刑法第247条) 特別背任罪(会社法第960条) |
|
|
名誉毀損罪(刑法第203条) 信用毀損及び業務妨害罪(刑法第233条) |
|
|
営業秘密侵害罪(不正競争防止法第21条) |
|
このような犯罪をした場合、刑事告訴だけでなく、損害賠償請求や懲戒処分などもされる可能性が高いでしょう。
会社から訴えられてから判決が下されるまでの流れ
会社から訴えられた場合の基本的な流れは、以下のとおりです。
- 裁判所から訴状などが届く
- 裁判所に答弁書を提出する
- 裁判に向けて証拠などを準備する
- 期日を迎えたら法廷で会社と争う
ここでは、会社から訴えられてから判決が下されるまでの大まかな流れについて解説します。
1.裁判所から訴状などが届く
訴訟を提起するにあたり、会社はまず裁判所に訴状を提出します。
そして、訴状を受理した裁判所は、被告である労働者に対して訴状や答弁書などを送付します。
これらの訴状などは特別送達という形式で届き、郵便局の配達員から直接手渡しされることになります。
2.裁判所に答弁書を提出する
裁判所から訴状を受け取ったら、労働者は答弁書を提出する必要があります。
答弁書とは、裁判所に対して自分の言い分を伝えるための書面のことを指します。
通常、答弁書は訴状と一緒に同封されているので、その用紙に会社の主張を認めるのかどうかや反論や和解の希望の有無などを書きます。
そして答弁書が完成したら、正本と副本(コピーしたもの)を1通ずつ用意して裁判所に提出します。
3.裁判に向けて証拠などを準備する
裁判所に答弁書を提出したら、自分にとって有利な証拠を集める必要があります。
その際、訴状の内容をよく確認し、その裁判で必要な証拠を集めることが重要です。
たとえば、不法行為に基づく損害賠償請求事件では、主に以下の内容について争われます。
- 労働者側に故意・過失があったか
- 会社が持つ権利を侵害しているか
- 会社に対して損害が発生しているか
- 行為と損害との間に因果関係があるか
労働者側は、自分の主張や反論が認めてもらえるよう、会社が主張した内容や提出した証拠とは異なる観点から証拠を集めておきましょう。
4.期日を迎えたら法廷で会社と争う
通常、会社が訴訟を提起してから約1ヵ月後に1回目の口頭弁論期日が開かれます。
1回目の口頭弁論期日では、当事者双方の主張内容について確認することが多いです。
その後、1~2ヵ月に1回程度のペースで続行期日が開かれ、主張・立証を重ねていきます。
口頭弁論が終結すると、最終的に裁判官からこの事件に関する判決が言い渡されることになります。
会社から訴えられた際に労働者がとるべき4つの対応
会社から訴えられたら、できる限り冷静になり以下の対応をとるようにしましょう。
- 訴状の内容をよく確認する
- 訴えられたら必ず答弁書を提出する
- 会社と争わない場合は和解の可能性を模索する
- できる限り早く労働問題が得意な弁護士に相談・依頼する
ここでは、会社から訴えられた際に労働者がとるべき4つの対応について説明します。
1.訴状の内容をよく確認する
裁判所から訴状が届いたら、まずは以下のポイントを確認しましょう。
- 会社の主張(請求の趣旨・原因)
- 第1回期日や答弁書の提出期限
- 証拠説明書に書かれている内容 など
会社の主張や答弁書の提出期限などによって、これからとるべき対応は変わります。
訴状を見るのが怖いからと放置せずに、できる限り早く全ての資料を一読しておきましょう。
2.訴えられたら必ず答弁書を提出する
会社に訴えられて、裁判所から訴状が届いたら、必ず裁判所に答弁書を提出しましょう。
答弁書を提出しなかった場合、裁判所に争う意思がないと判断されて会社側の主張が全面的に認められます。
事件の整理や証拠の準備が十分でなくても、最低限、原告の請求について争う旨の回答をしておくことが重要です。
3.会社と争わない場合は和解の可能性を模索する
会社の請求内容を認める場合は、和解をするという選択肢もあります。
訴状が届いた場合でも、会社と和解が成立する可能性は残っています。
訴訟での争いを続けるより負担が少なく、会社から譲歩を引き出せる可能性もあるため、和解を検討するのもひとつの方法でしょう。
4.できる限り早く労働問題が得意な弁護士に相談・依頼する
訴訟は、労働者の方が自分だけでも対応できます。
しかし、訴訟は精神的な負担が大きく、対応を間違えれば敗訴となる可能性もあります。
そのため、できる限り労働問題が得意な弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
法律事務所によっては、無料相談に応じている場合もあり、今後の流れや方針などを知ることができます。
まずは「ベンナビ労働問題」で労働問題が得意な弁護士を探し、自分の法律トラブルについて相談してみましょう。
会社から訴えられた方が弁護士に相談・依頼すべき4つの理由
会社に訴えられた場合、以下の理由から弁護士に相談・依頼すべきでしょう。
- 会社の請求内容などを正確に把握できるから
- 今後の方針などのアドバイスが受けられるから
- 答弁書や証拠説明書などの作成を任せられるから
- 依頼者に代わって裁判の手続きをしてくれるから
ここでは、会社から訴えられた方が弁護士に相談・依頼すべき理由について説明します。
1.会社の請求内容などを正確に把握できるから
訴訟された場合は、会社の請求内容などを正確に把握することが重要です。
しかし、法律や訴訟に慣れていない方の場合、請求内容などを確認するだけでも大きな負担となります。
弁護士に相談をすれば、訴状に書かれている請求内容や事実関係などについて丁寧に説明を受けられます。
また、訴状に書かれている内容が妥当なのか、それとも認められないのかなどの判断もしてもらえるでしょう。
2.今後の方針などのアドバイスが受けられるから
会社に訴えられた場合、被告側の選択肢には以下の2つがあります。
- 請求棄却を目指して争う
- 早期解決を目指して和解をする
弁護士に相談・依頼すれば、請求内容や事実関係などを踏まえてより良い選択肢を提案してもらうことが可能です。
また、会社と争う場合はどのような主張をすべきか、何を証拠として提出すべきかなどのアドバイスももらえます。
3.答弁書や証拠説明書などの作成を任せられるから
会社に訴えられた場合、裁判所に対して答弁書や証拠説明書などを提出する必要があります。
これらは、裁判でも重要な資料として扱われ、勝訴するためには欠かせないものとなっています。
弁護士に依頼した場合、こうした重要な書面の作成や裁判所とのやり取りなどを任せることが可能です。
書類作成を任せれば手間や負担を軽減できますし、より効果的に被告側の主張ができるようにもなるでしょう。
4.依頼者に代わって裁判の手続きをしてくれるから
最高裁判所の「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第10回)」によると、民事訴訟の平均期日回数は4.1回となっています。
裁判は平日の日中におこなわれるため、本人が対応する場合は数回程度会社を休んだり、家事を家族などに任せたりする必要があるでしょう。
しかし、弁護士に依頼をすれば、依頼者の代わりに裁判所に出頭してくれます。
その結果、会社や家事を休む必要はなくなりますし、裁判自体もスムーズに進めることができるでしょう。
会社から訴えられたことに関するよくある質問
最後に、会社から訴えられたことに関するよくある質問に回答します。
Q.言い分がなくても訴訟には応じるべきか?
会社側の主張が正しく労働者側に言い分がなくても、訴訟には応じるほうが望ましいでしょう。
請求が認められることは否定できなくとも、請求金額が適切であるとは限らず、裁判所が和解を勧めてくれるケースもあります。
Q.答弁書の期限に間に合わない場合はどうすべきか?
原則として、答弁書は指定された期限までに提出するのが望ましいです。
遅くとも、第1回期日の前日までに提出しなければなりません。
「間に合わないから」と放置するのではなく、期限に遅れてでも答弁書を提出するようにしましょう。
Q.第1回期日の都合が悪い場合はどうすればよいか?
第1回期日に限り、答弁書を出しておけば被告(労働者)は欠席することができます。
その際、答弁書に第1回期日に出席できない旨の記載をしておくか、裁判所に欠席する旨の電話をしましょう。
なお、答弁書を提出せずに期日を欠席すると、争う意思がないと判断されるので注意してください。
さいごに|会社から訴えられたらできる限り早く弁護士に相談を!
会社から訴えられた場合、訴訟の提起から約1ヵ月後には第1回期日を迎えることになります。
その間、被告となった労働者の方は、訴状を確認したり、答弁書などを作成したりする必要があります。
少ない時間の中で訴訟の準備をすることは大きな負担ですし、準備が不十分になる可能性も考えられます。
そのため、なるべくなら労働問題が得意な弁護士に相談し、訴訟の対応を依頼するほうが望ましいでしょう。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

【不当解雇・残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る
【労災/不当解雇の解決実績◎多数!】会社の非協力による労災申請の拒否や、納得できない理由での一方的な解雇・退職強要など、深刻な労働トラブルも当事務所にご相談ください!4人の特色ある弁護士が、実績に裏付けられた対応力でサポートします◆【平日夜間のご相談可○】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
 この記事の監修
この記事の監修

ルーセント法律事務所

その他に関する新着コラム
-
会社役員を辞めるのは原則自由です。ただし、タイミングによっては損害賠償を請求されることがあるため、しっかり見極めなければなりません。本記事では、会社役員の辞め方...
-
本記事では、法律トラブルを依頼中の弁護士に不信感を抱く6つのケースについて紹介します。それらの原因と対処法についても詳しく解説し、ほかの弁護士に変えたいと思った...
-
本記事では、会社との労働問題を通常訴訟で解決したいと考えている方に向けて、労働問題で会社を訴える際の手順、会社を訴えるメリット、会社との訴訟を弁護士に依頼すべき...
-
長時間労働やハラスメントなどの労働問題に直面しているにも関わらず、どこに相談すればいいか分からず悩んでいませんか。本記事では豊中市で労働相談が可能な4つの窓口と...
-
長時間労働やハラスメントなどの労働問題に直面しているにも関わらず、どこに相談すればいいか分からず悩んでいませんか。本記事では練馬区で労働相談が可能な5つの窓口と...
-
長時間労働やハラスメントなどの労働問題に直面しているにも関わらず、どこに相談すればいいか分からず悩んでいませんか。本記事では松戸市で労働相談が可能な4つの窓口と...
-
長時間労働やハラスメントなどの労働問題に直面しているにも関わらず、どこに相談すればいいか分からず悩んでいませんか。本記事では世田谷区で労働相談が可能な5つの窓口...
-
長時間労働やハラスメントなどの労働問題に直面しているにも関わらず、どこに相談すればいいか分からず悩んでいませんか。本記事では豊田市で労働相談が可能な4つの窓口と...
-
長時間労働やハラスメントなどの労働問題に直面しているにも関わらず、どこに相談すればいいか分からず悩んでいませんか。本記事では西宮市で労働相談が可能な4つの窓口と...
-
長時間労働やハラスメントなどの労働問題に直面しているにも関わらず、どこに相談すればいいか分からず悩んでいませんか。本記事では神戸市で労働相談が可能な4つの窓口と...
その他に関する人気コラム
-
この記事では、労働基準監督署でパワハラの相談をして解決できることや、パワハラ問題の解決フローについて紹介します。
-
うつ病と診断されたら無理をせず、休職するのも大切です。本記事では、うつ病で休職する際の手続き方法や相談先、休職期間の過ごし方や傷病手当金の申請方法などを紹介しま...
-
有給休暇の取得理由は、法律上必要ありません。有給の休暇取得は、労働者に与えられた権利ですし、休暇中の過ごし方は労働者の自由です。しかし、実際は会社で上司から取得...
-
企業が労働基準法に違反した行為をすると罰則が与えられます。以下で労働基準法違反となるのはどういったケースなのか、その場合の罰則はどのくらいになるのかご説明してい...
-
本記事では「源泉徴収票を紛失してしまった」「複数枚必要になった」など、さまざまな理由で再発行が必要な場合に知っておくべき知識と対処法を解説します。
-
試用期間中に「この会社合わないかも…。」と思って退職を考える人もいるでしょう。試用期間中の退職は正社員同様、退職日の申し出や退職届などが決まっています。この記事...
-
マイナンバー制度は利用する機会が少ないため、通知カード・マイナンバーカードを紛失した方もいるのではないでしょうか。通知カード・マイナンバーカードを紛失した場合、...
-
労働組合の作り方について、実は難しいことはありません。煩わしい手続きを取ることなく結成することができるのです。そんな労働組合の作り方について、記事にてご紹介して...
-
マイナンバーカードは郵便またはインターネットから作ることができます。まだ作成していない場合はこれからの利用拡大に備えて作っておきましょう。この記事では、マイナン...
-
解雇予告(かいこよこく)とは会社側が労働者を解雇しようとする場合に、少なくとも30日前に通知なければならない『解雇の予告』です。今回は、解雇予告とはどういったも...
その他の関連コラム
-
労働組合の作り方について、実は難しいことはありません。煩わしい手続きを取ることなく結成することができるのです。そんな労働組合の作り方について、記事にてご紹介して...
-
うつ病と診断されたら無理をせず、休職するのも大切です。本記事では、うつ病で休職する際の手続き方法や相談先、休職期間の過ごし方や傷病手当金の申請方法などを紹介しま...
-
長時間労働やハラスメントなどの労働問題に直面しているにも関わらず、どこに相談すればいいか分からず悩んでいませんか。本記事では千葉市で労働相談が可能な4つの窓口と...
-
自爆営業は、労働法に違反している恐れがあり、民事上も損害賠償の対象になる可能性があります。この記事では、自爆営業の違法性や断り方、対処法などについてご紹介します...
-
法律トラブルの解決は、能力・経験・得意分野や人柄などの特徴を見極めた上で、信頼できるに弁護士に依頼しましょう。ポータルサイトを利用して、複数の弁護士を比較して選...
-
中途採用者についてのリファレンスチェックを行う際には、個人情報保護法による規制に注意する必要があります。この記事では、リファレンスチェックを適法に行うに当たって...
-
労働条件通知書がないのは法律違反です。労働条件通知書がないとさまざまなトラブルにつながるおそれがあるため、従業員は適切に対処する必要があります。本記事では、労働...
-
会社との労働問題を労働基準監督署に通報しても、すぐに動いてもらえるとは限りません。できるだけ速やかに対応してもらうためには、通報前の準備や通報の仕方などがポイン...
-
労働基準法が定める休憩時間のルールを解説します。職場における休憩の取り扱いに疑問がある場合、本記事を参考として頂ければと思います。
-
長時間労働やハラスメントなどの労働問題をどこに相談すればいいか分からず悩んでいませんか。本記事では大田区で労働相談が可能な5つの窓口と専門家を解説しています。本...
-
退職先から離職票が届かない場合、労働基準監督署に相談することで解決する可能性があります。ただし、労働基準監督署が動くケースは限られており、状況次第では弁護士に依...
-
本記事では、残業代請求の弁護士費用相場をはじめ、弁護士費用を抑えるコツ、弁護士に依頼した際の流れなどについて解説していきます。