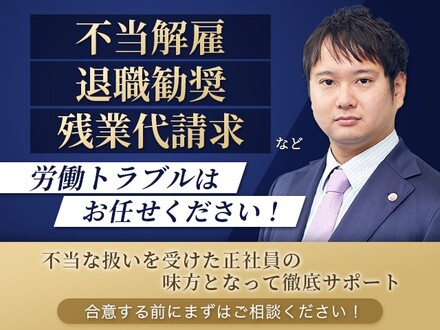勤務先によっては「アルバイトやパート従業員に有給休暇を付与しない」と主張する勤務先もあるでしょう。
ただし、一定の条件を満たせば、パートの方でも有給休暇を取得できます。
有給休暇の制度は、労働基準法に定められているため、雇用形態に関係なく、条件を満たせば誰でも有給を取得できるのです。
本記事では、パート従業員の方が有給休暇を取得できる条件をはじめ、取得できる日数や手当の計算方法を解説します。
職場に有給を付与しないと主張された場合の対処法や、有給休暇を取得してから退職する流れについても紹介するため、パート先から有給休暇をもらえずに悩んでいる方やこれからパート先の退職を検討している方はぜひ参考にしてください。
アルバイト・パートが有給休暇をもらえないのは違法?
結論から伝えると、アルバイトやパート従業員でも、有給休暇を取得できます。
有給休暇は、原則として労働基準法において定められた全ての労働者に与えられる権利です。
そのため、正社員だけでなく、契約社員やアルバイト、パートなどの雇用形態で働く方にも、一定の条件を満たせば付与されます。
ここでは、アルバイトやパート従業員に有給休暇を付与しないことが違法である法的根拠をはじめ、付与される有給日数の計算方法、さらに有給で発生する給与の計算方法を解説します。
有給休暇の発生条件
有給休暇の正式名称は「年次有給休暇」といい、休暇を取得した日の分の給料(賃金)が支払われる制度であり、「年休」や「有休」もしくは「有給」といわれるのが一般的です。
つまり、有給休暇は、給料が発生するものの、労働を休める日を意味します。
一定の条件に該当すれば、毎年一定の日数の休暇が与えられます。
有給休暇の発生条件は、次の2つです。
- 6ヵ月以上継続して勤務している
- 全労働日の8割以上出勤している
1つ目の条件は、入社してから半年以上継続して勤務していることです。
つまり、6ヵ月以上勤務していれば、週1日のみ出勤するパートやアルバイト従業員でも、有給休暇を取得できることを意味しています。
一方で、雇用契約を締結した日から半年未満の場合は、有給休暇の発生条件に該当しません。
そのため、短期のアルバイトや期間限定のパートのような働き方では、有給をもらえない可能性があります。
2つ目の条件は、全労働日の8割以上を出勤していることです。
全労働日の定義は、以下のとおりです。
- 全労働日=労働義務の日(アルバイト先・パート先の就業規則で定められた労働日)-所定の休業日(土日祝日など)の日数
勤務し始めてから半年以上が経過していても、欠勤が多く、全労働日の8割以上出勤できていない場合は、有給休暇の発生条件の対象外です。
勤務を開始してから、どの程度欠勤したかをカウントし、有給を取得できるかを確認してみましょう。
もらえる有給の日数はどう計算する?
正社員をはじめ、契約社員やアルバイト、パートなどの雇用形態に関係なく、有給休暇は勤務条件(週の所定労働日数・時間)によって付与日数が労働基準法で定められています。
大きく分けて、週30時間以上もしくは週5日以上の勤務か、週30時間未満かつ週4日以下の勤務かによって付与される有給日数の基準が変わるのが特徴です。
労働時間が週30時間以上もしくは週5日以上勤務の場合は、フルタイム勤務と同様の日数、週30時間未満週4日以下勤務の場合は比例付与という方式のもと、以下のとおり有給日数が決定されます。
| 所定労働日数 | 【年間】所定労働日数 | 雇用から半年後 | 雇用から1年半後 | 雇用から2年半後 | 雇用から3年半後 | 雇用から4年半後 | 雇用から5年半後 | 雇用から6年半後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週5日以上、もしくは週30時間以上 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
| 週4日かつ週30時間未満 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日かつ週30時間未満 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日かつ週30時間未満 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日かつ週30時間未満 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
アルバイトやパートで入社した6ヵ月後の有給日数は、週1日勤務で1日、週3日勤務で5日、週4日勤務で7日となり、週の所定労働日数と勤続期間に応じて付与されます。
自身の有給を何日分取得できるかわからない場合は、勤務先の上司や人事担当者に確認しましょう。
有給で発生する給料はいくら?
有給休暇の取得時に発生する賃金は、通常の勤務でもらえる額と同等の通常賃金が支払われるのが原則です。
ただし、有給休暇を取得して支払われる賃金の計算方法には、次の3つがあります。
- 通常の賃金から算出するケース
- 過去3ヵ月の勤務実績から算出するケース
- 標準報酬月額から算出するケース
1週間や1ヵ月の労働日数、労働時間があらかじめ決まっている通常の賃金から算出するケースでは、「有給を取得する日の勤務時間×時間分」で支払われる金額を算出可能です。
たとえば、月曜日は4時間労働、水曜日は6時間労働のように固定されている場合は、月曜日は4時間分、水曜日は6時間分の時給が支払われます。
【例】
時給1,000円で4時間勤務した場合
時給1,000円×4時間=4,000円
月のシフトに変動がある場合、アルバイトやパート先での過去3ヵ月の賃金の総額から算出するケースもあります。
ボーナスや臨時手当を差し引いた過去3ヵ月の賃金総額を、労災により遅刻・早退した日を除いた3ヵ月の勤務日数で割ることで、有給取得時の賃金を算出します。
【例】
時給1,200円で5時間、週3日勤務した場合
- 3ヵ月の賃金総額が21万6,000円(1ヵ月を4週間とする)
- 合計勤務日数が36日
21万6,000円÷36日=6,000円
最後は、社会保険料を決める基準となる標準報酬月額から算出する方法です。
まず、従業員が得た月額給与を50の等級に分けられた標準報酬月額をもとに区分し、有給休暇取得時の賃金にあたる標準報酬日額を算出します。
計算式「標準報酬日額=標準報酬月額÷30」にあてはめ、支払われる金額が決まります。
2019年の法改正
2019年4月からは、労働基準法の改正により、条件を満たした従業員に対して年に5日の年次休暇を取得させるよう義務付けられました。
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。
この法改正によって有給休暇の取得が義務付けられているのは、年次有給休暇が10日以上付与される労働者に限られています。
そのため、アルバイトやパートの場合は、対象が一部の方のみとなるでしょう。
有給休暇の取得義務の対象となるのは、次のとおりです。
- 週5日以上勤務(勤続年数6ヵ月以上)
- 週30時間以上勤務(勤続年数6ヵ月以上)
- 週4日以上勤務(勤続年数3年6ヵ月以上)
- 週3日以上勤務(勤続年数5年6ヵ月以上)
対象となるアルバイトやパート従業員の方は、年に5日以上の有給休暇の取得が法律によって義務付けられているため、積極的に取得していきましょう。
有給の権利を行使しないとどうなる?
新たに付与された有給休暇を1年以内に消化しきれなかった場合に、残日数を翌年に持ち越すことは可能です。
ただし、有給休暇には有効期限が定められており、期限を過ぎると使用できなくなります。
有給休暇の有効期限は、付与された日から2年間です。
また、持ち越せる日数は、20日が上限とされているため、持ち越し後に保有できる日数は最大40日までと覚えておきましょう。
持ち越した有給休暇は、古い年度のものから消滅していきます。
アルバイトやパートとして働く方のなかには、半年や1年ごとに契約を更新するケースもあるでしょう。
ただし、この場合も2年の期限内であれば契約更新時に有給休暇の日数も持ち越されます。
退職時に有給休暇が残っている場合は、消化しないとただなくなってしまうだけになるため注意が必要です。
退職日のタイミングに合わせて有給休暇を使い切りましょう。
たとえ、まとまった日数分の有給休暇が残っていても、躊躇することなく使い切ってしまって問題ありません。
ただし、有給休暇を消化して退職する場合は、退職日や最終出勤日に合わせて業務の引き継ぎをしっかりと済ませておきましょう。
「パートに有給はない」と言われたらどうする?
「アルバイトやパート従業員には有給休暇を付与しない」と上司から伝えられるケースもあるでしょう。
ここでは、職場からパートに対して有給休暇を付与しないと主張された場合の対処法を解説します。
同僚と協力して、上司と交渉する
1つ目は、会社に対して有給休暇の取得を交渉する方法です。
本来であれば有給休暇の取得対象であるにもかかわらず、会社側の知識不足のために有給休暇を取得できていないケースも少なくありません。
まずは、直属の上司に相談してみましょう。
それでも解決が見込めない場合は、直属の上司よりも上役の人や本社の人事部などに問い合わせてください。
一人で掛け合う勇気がない場合は、同僚たちと協力しながら交渉するのもおすすめです。
交渉する際は、有給休暇の取得が法律で認められた権利であるとはっきりと主張しましょう。
労働基準監督署に相談する
会社との交渉に自信がない方や会社との交渉に不安を感じている方は、労働基準監督署のような外部機関に相談することも検討してみましょう。
労働基準監督署とは、労働基準法や労働契約法などの法律に基づき、労働条件や安全衛生の指導、労災保険の給付などをする機関です。
職場の安全や労働者の健康を守るための重要な役割をもちます。
労働基準監督署内には、総合労働相談コーナーという窓口が設置されており、誰でも気軽に職場でのトラブルについて相談できます。
アルバイトやパートなどの従業員の相談にも対応しているため、一人で悩みを抱え込まず、気になっていることや解決方法などを問い合わせてみましょう。
退職し、書面で有給取得を申請する
交渉しても、有給休暇の取得を認めてくれない場合は、思い切って転職を検討してみましょう。
退職する際は、退職時に付与されている有給休暇を全て消化してから転職してください。
退職時に有給休暇を取得するためには、まずは直属の上司に退職したい旨を伝えます。
その際に、引き継ぎを踏まえたうえで、最終出勤日を相談して決めましょう。
最終出勤日が決まったら、有給休暇の消化を加味して退職日を決定し、申請書を使って有給休暇の取得申請をします。
職場に申請用紙がない場合は、インターネット上にある無料の書式テンプレートを活用しながら、申請書を作成してみましょう。
有給を申請して退職するまでの流れ
アルバイトやパート勤務の方も、有給休暇付与の対象である場合は、退職時にまとめて消化できます。
円満退職を希望する方で退職前にスムーズに有給休暇を消化したい場合は、いくつか押さえるべきポイントがあります。
ここでは、有給休暇を申請、取得してから退職するまでの流れを詳しく解説しましょう。
有給を取れる日数を計算する
有給休暇は、労働日数や時間数によって付与される日数が異なります。
そのため、退職時に有給休暇を取得する場合は、有給休暇がどの程度残っているかを確認しなければなりません。
有給休暇は、入社して6ヵ月後に、労働基準法に定められた日数分が付与され、その後1年ごとに日数が追加されていきます。
ただし、法律で定められた日数はあくまでも最低限の基準であり、勤務先によっては、基準の日数以上を付与されるケースもあるため、有給休暇についての規定をあらかじめ確認しましょう。
正確な有給休暇の残日数を知りたい場合は、給与明細や勤怠管理システムなどで確認するか、勤務先の人事部や総務部に問い合わせてください。
退職日を決定し、退職の意思を伝える
有給休暇の残日数を把握できたら、退職日を決めていきます。
有給休暇の残日数が多ければ多いほど、なるべく早めに会社に相談して、退職日までのスケジュールを組むよう心がけてください。
退職日を決める際は、後任への引き継ぎ期間と新しい勤務先が決まっている場合は入社予定日を考慮することが大切です。
退職時の有給休暇の消化は、労働者に与えられた権利ではあるものの、会社の都合を一切加味せずに退職日を決定してしまうと、退職時や退職後にトラブルに発展する恐れもあるため注意が必要です。
業務内容によって引き継ぎにかかる時間は大きく変動します。
退職日を決める際は上司に相談しながら日程を組むことが大切です。
退職予定日の1ヵ月以上前のタイミングで相談しておくと、有給を消化して退職できる可能性が高まるだけでなく、落ち着いた状態で退職手続きを進められます。
退職の意思を伝える際、退職届の提出は義務付けられていないため、口頭で伝えるだけで問題ありません。
ただし、社内規定などによって職場から提出が求められるケースもあります。
円満退職するためにも、職場のルールにしたがって準備しましょう。
可能な限り引き継ぎをおこなう
退職日が決まったら、可能な限り引き継ぎをおこないます。
退職時の引き継ぎについて定める法律はないため、法律上は引き継ぎをする義務はありません。
ただし、たとえ義務でなくても、後任がスムーズに業務にあたるためには、必要最低限の引き継ぎをおこなうべきでしょう。
さらに、就業規則において退職時の業務引き継ぎが義務付けられているケースもあるため、事前に確認してください。
引き継ぎをするためには、自身がどの業務を担当しているかを整理する必要があります。
担当業務をリスト化して、業務ごとに仕事のやり方を共有してください。
可能であれば、簡単なマニュアルを作成しておくと、スムーズに引き継ぎができるでしょう。
証拠の残る書面で、有給の消化を申請する
有給休暇の取得を口頭で申請してしまうと、勤務先から「申請なんてされていない」と主張される恐れがあります。
退職時に有給休暇の取得を申請したにもかかわらず、欠勤扱いにされて賃金が支払われないなどの事態を防ぐためにも、証拠として残る書面での申請がおすすめです。
書面で申請する際は、原本をコピーして保管しておきましょう。
そのほかには、メールでの申請もおすすめです。
退職時に勤務先とトラブルに発展しないためにも、有給休暇を申請した証拠を残すように意識してください。
離職票などの書類を受け取る
退職の申し出が受理されたら、退職に向けた手続きを進めていきましょう。
退職時には会社から受け取る書類がいくつか存在します。
退職時に受け取る書類は、以下のとおりです。
- 源泉徴収票
- 離職票
- 雇用保険被保険者証(雇用保険に加入している場合)
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
離職票や雇用保険被保険者証は、再就職先が決まっている場合や失業保険を受給する際に提出が必要な書類です。
上記の書類は、退職日以降に郵送されるケースが多く、退職日から2週間を目安に送られてきます。
どのような書類を、いつのタイミングで受け取れるかあらかじめ確認しておきましょう。
書類がもらえない場合は?
退職時に受け取るはずの書類がもらえない場合は、次のようなケースが考えられます。
- 職場の担当者が作成し忘れている
- 管轄のハローワークでの手続きが滞っている
- 職場の嫌がらせによって書類が発行されていない
受け取るはずの書類が作成されない、郵送されない場合に備えて、担当部署や担当者名の連絡先を聞いておきましょう。
単純に担当者が作成し忘れていた場合は、依頼すれば問題なく書類を受け取れるでしょう。
また、管轄のハローワークに問い合わせて、書類発行の進捗状況を確認することも大切です。
会社に問い合わせても書類が作成されない場合は、嫌がらせの可能性もあります。
その場合は、ハローワークに相談のうえ、対策を検討しましょう。
有給に関する交渉が難しいと感じるなら
「職場の上司が怖くて有給休暇を取得できない」「人手不足を理由に有給休暇を取らせてくれない」と悩んでいる方は、退職も視野に入れてください。
退職の意思を伝えるのも不安な場合は、退職代行サービスの利用を検討しましょう。
退職代行とは、依頼者の代わりとなって退職の意思を伝えるサービスです。
労働組合や弁護士が運営する退職代行サービスを活用すれば、有給休暇の取得や退職日の調整など、退職時のさまざまな交渉ごとにも対応してくれます。
多くの退職代行業者は、無料相談に対応しているため、有給休暇が取得できずに困っている方は、気軽に相談してみましょう。
よくあるQ&A
アルバイトやパートの方の有給休暇について、よく寄せられる質問を紹介します。
有給がもらえない正当な理由はありますか?
有給休暇の取得は、労働者の権利であり、条件を満たす全ての人に与えられるものです。
そのため、会社側はいかなる事情があっても、有給休暇の取得を拒否できません。
ただし、会社側は、事業の正常な運営を妨げる場合に、有給休暇の取得時季を変更できる時季変更権をもっています。
ただし、時季変更権は、あくまで取得時季を変更するものであって、有給休暇の取得を拒否できるものではないため、申請自体を拒否することは違法行為とみなされるでしょう。
パートで有給を使い切って欠勤したらどうなる?
有給休暇を使い切った状態で欠勤した場合、欠勤した日の給料はもちろん支給されません。
また、無断欠勤や私的な理由の欠勤が目立つ場合は、賞与や昇給への影響も考えられるでしょう。
勤務態度の改善の見込みがないと判断された場合は、解雇の対象にもなるため注意が必要です。
パートの有給は持ち越せますか?
アルバイトやパート従業員の方も、ほかの雇用形態の従業員と同様に、有給休暇を持ち越せます。
有給休暇の有効期限は、付与されてから2年間です。
その期間中に雇用契約の更新があっても、有効期限が残っている有給休暇はそのまま持ち越せます。
さいごに|有給は労働者の権利
有給休暇の取得は、労働基準法によって定められた労働者の権利です。
アルバイトやパートの方でも条件を満たせば有給休暇を取得できます。
本記事で紹介した有給休暇の日数や取得する条件を正しく理解しておけば、勤務先と交渉する際も落ち着いて対処できるでしょう。
有給休暇を取得できないと悩んでいる場合は、労働基準監督署のような公的機関に相談してください。
有給休暇を取得できないようなブラック企業から退職したい場合は、思い切って退職代行サービスの利用も検討してみましょう。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

【不当解雇・残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

退職代行に関する新着コラム
-
本記事では、堤法律事務所の中谷 真一郎先生監修のもと、なぜ「退職代行モームリ」が問題となったのか、その法的な核心部分を深掘りしつつ、今、私たちが本当に安心して利...
-
熊本県内で退職代行サービスを検討しているものの、選ぶポイントやどんなサービスがあるかわからず戸惑ってしまう方もいるでしょう。この記事では熊本県でおすすめの退職代...
-
退職にあたり、なるべく多くの給付金をもらいたいと考える方も多いでしょう。怪我や病気が理由で退職する場合、条件を満たせば傷病手当金と失業保険の両方を受給できます。...
-
退職代行を長崎県で利用する場合、長崎の地域に密着しているかを見極めるのも大切です。都心を中心に対応しているサービスは、地方でのサポートが難しい場合が見られます。...
-
徳島県で使える退職代行サービスは、全国対応型と地域密着型の両方が存在します。2つの種類によって、サポートの方法や体制が異なるので、どちらを利用すべきかの見極めが...
-
現在、福井県で退職代行サービスを探している方は、全国に対応しているサービスに加えて地域密着型のサービスにも目を向けてみましょう。本記事で、おすすめの退職代行サー...
-
退職代行を群馬県内で探す際、さまざまなサービスが存在しています。本記事では、群馬県でおすすめの退職代行サービスを、全国対応型と地域密着型に分けてそれぞれ厳選して...
-
神奈川で利用できる退職代行サービスはたくさんあります。近年ではサービスの増加に伴い、どれを使えばよいかわからないという方もいるでしょう。本記事では、神奈川県に焦...
-
愛媛県で退職代行サービスの利用を考えていませんか?本記事では、愛媛県でおすすめの退職代行サービス4選・退職代行サービスを選ぶ際にチェックしたい3つのポイントを解...
-
香川県で退職代行サービスの利用を考えていませんか?本記事では、香川県でおすすめの退職代行サービス4選・退職代行サービスを選ぶ際の3つのポイントをまとめました。記...
退職代行に関する人気コラム
-
退職後の給付金には多くの種類が存在します。現在、仕事を辞めて次が決まるまでのつなぎとして、手当を受給しようと考えている方は少なからずいるでしょう。ただ、給付金を...
-
うつ病にかかり退職を考えている方は、退職の流れや生活費などが気になると思います。この記事では、うつ病で退職する場合の流れや保険、支援制度についてご紹介します。
-
退職代行サービスに興味があるものの、具体的に何をしてもらえるのか理解できておらず、利用を踏みとどまっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、退職代行サー...
-
退職代行を入れて引き継ぎもなく退職したことで、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえません。今回は、退職代行を使って退職しようとお考えの方に、退職時の...
-
失業保険の給付金を受け取りながらのバイトは可能か、退職者のなかで気になる方は多いでしょう。アルバイトは収入が発生するので、手当の受給にはなにかしらの影響が出てく...
-
うつ病で退職した人も失業保険を受け取れます。この記事では、うつ病で退職した人が300日の失業保険を受給する条件や受け取るまでの流れを解説します。受給金額や失業保...
-
失業保険の不正受給は税務署やハローワークにバレる可能性が高いです。この記事では、失業保険を不正受給するとバレる理由やバレるケースを詳しく解説します。失業保険の利...
-
退職代行を利用しても退職に失敗してしまうという事例があるようです。今回は、退職代行が失敗する5つのパターンと、失敗のリスクを極力抑えるための効果的な3つの方法を...
-
この記事では、失業手当をもらいながら4時間ピッタリのバイトをした場合にどうなるのかを解説します。バイトをしながら失業手当を受け取る条件も解説するので、失業手当を...
-
この記事では求職活動をするふりだけでも失業保険が受けられるのかについて解説します。求職実績の簡単な作り方や、実績に含まれない求職活動も紹介しています。不正受給を...
退職代行の関連コラム
-
この記事では秋田での退職代行サービスの選び方やメリットを詳しく解説します。あわせて信頼できるサービスの選定方法を提供します。
-
現在、仕事を辞めたくなり、退職代行に注目している方は少なからず存在します。しかし、職種や業界によっては利用できないだろうと考える方もいるでしょう。本記事では教員...
-
青森在住で今の仕事を辞めたい方で思っている方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、青森で特におすすめの退職代行2選をご紹介します。選び方のコツや利用の...
-
退職代行はアルバイトやパートでも利用でき、どのような雇用形態であってもスピーディな退職が望めます。本記事では、アルバイトやパートが退職代行を利用するメリット・デ...
-
退職代行Jobsの評判が気になっていませんか?本記事では、退職代行Jobsを実際に利用した方の良い評判・悪い評判や、利用に向いている方の特徴をまとめました。さら...
-
退職ジャパンの利用を検討している方で疑問や不安を抱いている方も多いでしょう。この記事では、退職ジャパンの評判や特徴、怪しいと言われる理由を詳しく解説します。失業...
-
バイトを辞めたいけど電話で伝えるのが怖くて悩んでいる方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、電話するのが怖い理由や上手く伝えるコツを解説します。早く辞...
-
発達障害には多くの種類が存在し、人によって見られる症状は異なります。現在、発達障害の症状を自覚しており、仕事にも影響が出ていることで悩んでいる方は少なくありませ...
-
本記事では、即日退職して明日から行かない方法について詳しく解説します。今話題の退職代行サービスの概要や信頼できる退職代行会社の選び方も紹介します。
-
「一年未満で会社を辞めたけど失業保険ってもらえるの?」結論、一年未満で退職した場合でも状況によっては失業保険を受けられます。この記事では、失業保険の適用条件や受...
-
新卒で入社したもののすでに退職を検討している方も多いのではないでしょうか。この記事では、新卒で退職を言いづらい理由や対処法を詳しく解説します。おすすめの退職理由...
-
毎日辛いのに退職を切り出せず悩んでいませんか。鳥取で使える退職代行サービスと法律事務所を厳選して紹介しています。利用が増加している背景やメリットとデメリットも解...
可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
【弁護士監修】退職代行とは?今使っても大丈夫?【2025年10月最新版】
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
退職代行で引き継ぎ放棄しトラブルに?リスク回避が可能な方法と注意点