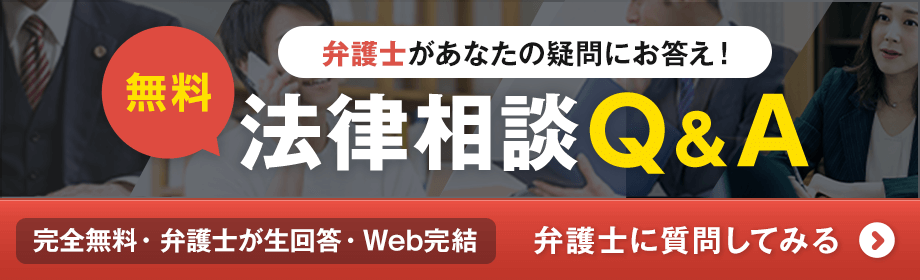本コンテンツには、紹介している商品(商材)の広告(リンク)を含みます。
ただし、当サイト内のランキングや商品(商材)の評価は、当社の調査やユーザーの口コミ収集等を考慮して作成しており、提携企業の商品(商材)を根拠なくPRするものではありません。
「失業保険を一度もらうと、この先受け取れないのではないか」
「再就職が決まったが次に失業保険を受け取れるのはいつなのか」
失業保険の受給者の中には、このような疑問を持つ方も多いと思います。
失業保険は、一度受給しても条件を満たすことで再び受給することが可能です。
2回目以降の受給資格を知っておけば、再就職先で退職してしまった場合でも安心して求職活動が行えるでしょう。
この記事では、失業保険を一度受給することで受ける影響や受給資格について、詳しく解説します。
また、受給する上での注意点も紹介するので、失業保険を利用して新しい環境へチャレンジしようと考えている方は、この記事を参考に失業保険の手続きを進めましょう。
あわせて読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
会社辞めたらお金もらえるって知ってる?

『失業保険サポート』では、退職後にもらえる給付金を受け取るサポートをしてもらえます。
実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。
| 平均月収 |
月間でもらえる金額 |
| 月収30万円 |
約20万円 |
| 月収40万円 |
約26万円 |
| 月収50万円 |
約33万円 |
| 月収60万円 |
約40万円 |
| 月収70万円 |
約46万円 |
| 月収80万円 |
約53万円 |
| 月収90万円 |
約60万円 |
| 月収100万円 |
約66万円 |
会社を辞めて給付金を申請するだけでこんなにもお金がもらえます。
ですが、「ほんとに仕事辞めたらこんなにお金もらえるの?」「さすがに退職してからお金もらえるわけなくない?」と疑問に思いますよね。
そんなあなたに向けて『失業保険サポート』では給付金について詳しく分かる無料Web個別相談を実施しています。
「会社を辞めたいけどお金が...」とお困りのあなた!
この機会に無料で給付金について知れる個別相談を一度試してみませんか。
公式サイト:https://roudou-pro.com/links/syakaihoken_sokyu/
失業保険を一度もらうとどうなるのか
失業保険は、退職した後に安心して求職活動を行えるように設けられている支援制度ですが、人によっては失業保険を2回以上を利用することも考えられます。
ここでは、一度失業保険を受け取ることでどのような影響を受けるのかについて解説します。
- 雇用保険の被保険者期間がリセットされる
- もう一度受給資格を満たせば再び受給できる
- 次にもらえるのは半年後か1年後以降
雇用保険の被保険者期間がリセットされる
失業保険を一度受給することで、雇用保険の被保険者期間がリセットされます。
失業保険を受けるためには被保険者期間の条件を満たす必要がありますが、一度失業保険を受け取ると一定期間働いてからでないと、再び受給することができなくなるのです。
たとえば、被保険者期間の条件を満たしている人が退職して失業保険を受け取った場合、その時点で雇用保険の被保険者期間はリセットされます。
そのため、その後に再就職先を1ヶ月で辞めてしまうと、被保険者期間が条件に満たないため失業保険を受け取ることができないのです。
被保険者期間の長さに関係なく、一度失業保険を受け取ると被保険者期間がリセットされることを覚えておきましょう。
もう一度受給資格を満たせば再び受給できる
一度失業保険を受け取り被保険者期間がリセットされても、改めて受給資格を満たせば再び失業保険を受け取ることができます。
これは自己都合・会社都合のどちらにも共通して回数に制限はありません。
失業保険を受けるための被保険者期間は次のとおりです。
| 受給資格 |
雇用保険の加入期間 |
| 一般の離職者 |
離職前2年間の被保険者期間が12ヵ月以上 |
特定受給資格者
特定理由離職者 |
離職前1年間の被保険者期間が6ヵ月以上 |
たとえば、一度失業保険を受け取った後でも、一般の離職者が受給できる「離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」の条件を満たせば、退職後にもう一度失業保険を受給できます。
「失業保険を一度受け取ると二度と受給できない」と思っている方もいますが、失業保険の受給条件さえクリアすれば再び受給できるので、2度目の退職を考えている方は頭に入れておくと良いでしょう。
次にもらえるのは半年後か1年後以降
再就職した後に再び失業保険を受け取れるのは、半年後か1年後以降となります。
これは、一度失業保険を受け取ると被保険者期間がリセットされることに加え、失業保険には先述した「失業保険を受けるための被保険者期間」が設定されているためです。
再就職してから半年で受給できるのは、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」の場合です。
特定受給資格者とは、会社の倒産や解雇によって事前に転職の準備ができないまま離職してしまった人のことで、特定理由離職者とは自己都合による退職であるものの自分の意志に反する正当な理由がある人を指します。
つまり、自分の意志ではない理由で退職を余儀なくされたケースでは、再就職から半年で再び失業保険を受け取れるのです。
一方、再就職から1年が経過しないと失業保険が受け取れないのは「一般の離職者」です。
一般の離職者とは、キャリアアップや今の仕事が合わないなどの自己都合による理由で退職した人のことを指します。
そのため「再就職して雇用保険に加入したから短期間で辞めても失業保険がもらえるだろう」と考えている方は要注意です。
再就職先がブラック企業だった、人間関係が合わなかった、などの理由ですぐに退職することになっても、失業保険が受給できない可能性があることを理解しておきましょう。
失業保険の受給資格とは
失業保険の受給資格は、大きく次の3つが挙げられます。
- 働く意思と能力がある
- 雇用保険に一定期間以上加入している
- 求職活動による実績がある
ここで紹介する受給資格を理解して、再び失業保険を受給する際に役立てましょう。
働く意思と能力がある
失業保険の受給資格1つ目は、働く意志と能力を備えている状態であることです。
失業保険は、就職する意思があり、かつすぐに働ける状態でないと受給することができません。
そのため、退職後に学業や家事に専念したい方や、仕事をせずに休養を取りたい方などは対象外となります。
ただし、病気や妊娠、ケガなどが原因で働けない状態の場合は、延長申請を行うことで後から失業保険を受けることが可能です。
病気やケガで退職を余儀なくされた方は、治療状況に応じて延長申請を検討すると良いでしょう。
雇用保険に一定期間以上加入している
冒頭で伝えたとおり、雇用保険の被保険者期間が一定期間に達していなければ、失業保険を受けることができません。
一般の離職者の場合は「離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」で、特定受給資格者・特定理由離職者の場合は「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」が必要です。
また、受給資格別の主な退職理由は次の表を参考にしてください。
一般の離職者
(自己都合) |
- より待遇の良い職場を求めている
- 独立する
- 結婚や育児のため
- 職場の人間関係が悪い
- 会社による懲戒処分で解雇になった
|
特定理由離職者
(自己都合) |
- 心身の不調で働けなくなった
- 家族の介護や看病で退職しなければならない
- 通勤手段である公共交通機関の廃止で通勤できなくなった
- 労働契約期間の満了後に更新を希望したが更新されなかった
|
特定受給資格者
(会社都合) |
- 会社が倒産した
- 会社による賃金の不当な未払いが続いた
- 希望退職制度に応募して辞めた
- リストラ・解雇を命じられた
|
自分がどのケースに当てはまっているのかを見極めた上で、失業保険の手続きを進めてください。
求職活動による実績がある
3つ目の条件は、失業認定日までに一定の求職活動実績を作ることです。
求職活動実績とは、再就職に向けて行っている求職活動のことです。
失業保険を受給するためには、4週間毎の失業認定日までに2回の求職活動実績を作らなければいけません。
主な求職活動実績には、以下が挙げられます。
- ハローワークで就職相談を行う
- ハローワークや転職サイトで求人に応募する
- 転職フェアに参加する
- オンラインセミナーに参加する
- 国家資格の試験を受ける
ただし、転職サイトや派遣会社に登録しただけでは求職活動実績になりません。
求職活動を無駄にしないためにも「これは求職活動実績になるのか?」と疑問に感じた場合は、かならずハローワークに相談するようにしましょう。
退職理由別の失業保険の給付期間
ここからは、「一般の離職者」と「特定理由離職者・特定受給資格者」それぞれの失業保険給付期間を紹介します。
一般の離職者
一般の離職者の給付期間は、年齢にかかわらず雇用保険の被保険者期間によって変動します。
雇用保険の被保険者期間別の給付期間は次の表のとおりです。
| 雇用保険の被保険者期間 |
1年未満 |
1年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
| 給付日数 |
0日 |
90日 |
120日 |
150日 |
一般の離職者が失業保険を受給するまでには「待機期間」に加え「給付制限期間」が設けられます。
待機期間とは、失業保険の受給が決まった日から、失業状態が7日間経過するまで失業保険が給付されない期間のことです。
また、給付制限期間とは一定期間失業保険が受給できない期間のことで、退職回数によって2ヶ月から3ヶ月の期間が設定されています。
給付制限期間は通常2ヶ月ですが、過去5年間で2回以上自己都合による退職をしていると、3回目の離職では3ヶ月の給付制限期間となるのです。
このように、一般の離職者には「待機期間」と「給付制限期間」が設定されているため、退職して初めての支給を受けるまでに3ヶ月〜4ヶ月がかかることを理解しておきましょう。
特定理由離職者・特定受給資格者
特定理由離職者と特定受給資格者の給付期間は、雇用保険の被保険者期間と退職時の年齢によって異なります。
| 雇用保険の被保険者期間 |
1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
| 30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
ー |
30歳以上
35歳未満 |
120日 |
180日 |
210日 |
240日 |
35歳以上
45歳未満 |
150日 |
240日 |
270日 |
45歳以上
60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
60歳以上
65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
特定理由離職者と特定受給資格者の場合は、雇用保険の被保険者期間が1年未満でも受給できることが特徴です。
被保険者期間が1年を経過すれば、年齢が高くなるにつれて給付期間が長くなります。
特定理由離職者と特定受給資格者には給付制限期間はありませんが、7日間の待機期間が設定されています。
そのため、待機期間が満了した後の約1ヶ月後が、初回の支給日になると考えておいてください。
給付金額の計算方法
失業保険の受給金額は、以下の3ステップで算出されます。
- 賃金日額=離職前6ヶ月の賃金合計÷180
- 基本手当日額=賃金日額✕給付率
- 基本手当総額=基本手当日額✕給付日数
ステップ2で用いられる「給付率」は、退職時の年齢や賃金日額ごとに定められています。
令和6年8月現在の給付率・賃金日額・基本手当日額は以下の表を参考にしてください。

引用:厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」
また、ステップ2で算出される「基本手当日額」とは、実際に受け取る1日あたりの給付額です。
基本手当日額に給付日数を掛けることで、給付金額の総額が算出される流れになります。
シミュレーションとして、以下の条件で給付金額を算出してみましょう。
|
【前提条件】
- 受給資格:一般の離職者
- 年齢:34歳
- 退職前6ヶ月間の賃金合計:270万円
- 雇用保険の被保険者期間:12年
270万円÷180=1万5,000円(基本手当日額)
1万5,000円(基本手当日額)✕50%(給付率)=7,500円(基本手当日額)
7,500円(基本手当日額)✕120日(給付期間)=90万円(給付金額)
|
以上の計算式から、このケースでは総額90万円の失業保険が受給できるとわかりました。
「自分の給付金額が知りたい」と考えている方は、この計算式に当てはめて計算してみてください。
失業保険を受給する上での3つの注意点
失業保険を受給する上で注意するポイントには、主に以下の3つが挙げられます。
- 受給期間中のアルバイトやパートには制限がある
- 失業保険には2年間の時効期限がある
- 不正受給には罰則が課せられる
ここで紹介するポイントに気を付けて受給手続きを進めてください。
受給期間中のアルバイトやパートには制限がある
1つ目の注意点は、失業保険の受給中にアルバイトやパートの制限がかかることです。
この制限を守らなければ、失業保険が見送り、または停止されることがあります。
失業保険中のアルバイト・パートの主な制限は以下のとおりです。
- 週20時間未満に抑える
- 31日未満の雇用契約にする
- 受給中のバイトをハローワークに申告する
- 7日間の待機期間はバイトをしない
- 賃金日額の80%以下に収入を抑える
アルバイト・パートを「週20時間未満」「31日未満の雇用契約」に抑える理由は、雇用保険の加入条件を満たさないようにするためです。
失業保険は「雇用保険の加入条件を満たすと受給できない」と定められており、雇用保険の加入条件である「週20時間以上の労働」と「31日以上の雇用契約」をしてはいけません。
また、アルバイトやパートの収入が賃金日額の80%を超えると、受け取れる失業保険が減額されます。
失業保険の減額分を算出する計算式は以下のとおりです。
| 減額分={(1日のアルバイト収入ー控除額)+基本手当日額}ー(賃金日額×80%) |
「控除額」とは国が定める金額で、2024年8月以降の控除額は1,354円です。
控除額は毎年見直しが行われるので、計算する際はかならず確認するようにしてください。
経済的な事情で失業保険中にアルバイトやパートを行う場合は、働いた分が無駄にならないよう制限に気をつけましょう。
失業保険には2年間の時効期限がある
失業保険には時効期限が設けられているため、手続きを先延ばしにしてしまうと受け取れなくなるおそれがあります。
ただし、すべての失業保険に2年間の時効期限があるというわけではありません。
以下は、2年間の時効期限内に遡って申請できる失業保険の一覧です。
| 2年間の時効期間がある失業保険一覧 |
- 就業手当
- 再就職手当
- 移転費
- 広域求職活動費
- 短期訓練受講費
- 求職活動関係役務利用費
- 一般教育訓練に係る教育訓練給付金
- 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金
- 教育訓練支援給付金
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 高年齢再就職給付金
- 出産時育児休業給付金
- 育児休業給付金
- 介護休業給付金
- 常用就職支度手当
|
注意点は、失業保険の要である「失業手当」には、2年の時効期間が設けられていないことです。
1年間の申請期限が過ぎると受給資格が失なわれ、一切受け取れなくなります。
失業手当がないと失業保険の受給額が大幅に減ってしまうため、退職から1年以内に手続きすることを忘れないようにしましょう。
また、妊娠や病気、ケガなどの特別な理由ですぐに手続きができない場合は、受給期間の延長を申し込むことができます。
延長を申し込むことにより、求職活動ができる時期から失業保険が受け取れるので、すぐに働けない場合はかならずハローワークへ相談しましょう。
不正受給には罰則が課せられる
失業保険の不正受給を行うと罰則が課せられる点にも注意が必要です。
よくある不正受給の例として「実際に行っていない求職活動を失業認定申告書に記載する」「アルバイトやパートをしている事実をハローワークに報告しない」などが挙げられます。
不正受給の具体的な罰則は次のとおりです。
- 不正受給発覚以降の受給が停止される
- 不正に受給した失業保険を返還する
- 不正に受給した失業保険の2倍の金額を納付する
- 特に悪質な場合は詐欺罪として刑事告発される
不正受給は、故意でなくても処分対象になります。
不正処分になるケースを十分に理解し、不正受給にあたらないよう適切に手続きを行わなければいけません。
また、不正受給が発覚し納付命令を無視した場合、所有している貴金属や車、不動産などを差し押さえられるおそれがあります。
もし不正受給が発覚して処分命令を命じられた場合は、すぐに対応することを心がけましょう。
まとめ
この記事では、失業保険を一度もらうことでどのような影響を受けるのかを解説しました。
失業保険を一度受け取ると雇用保険の被保険者期間がリセットされるため、再び受給するためには改めて一定の被保険者期間を満たす必要があります。
そのため、次に失業保険を受け取れるのは、最短でも半年後か1年後です。
また、失業保険を受け取るにあたり、アルバイトやパートに制限がかかる点や時効期限があることに気をつけなければなりません。
人によっては、一度だけでなく何度も退職して失業保険を受給する方もいるでしょう。
この記事を参考に、2回目以降でも失業保険を受け取れる条件を理解し、安心して求職活動を行う環境を手に入れてください。
会社辞めたらお金もらえるって知ってる?

『失業保険サポート』では、退職後にもらえる給付金を受け取るサポートをしてもらえます。
実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。
| 平均月収 |
月間でもらえる金額 |
| 月収30万円 |
約20万円 |
| 月収40万円 |
約26万円 |
| 月収50万円 |
約33万円 |
| 月収60万円 |
約40万円 |
| 月収70万円 |
約46万円 |
| 月収80万円 |
約53万円 |
| 月収90万円 |
約60万円 |
| 月収100万円 |
約66万円 |
会社を辞めて給付金を申請するだけでこんなにもお金がもらえます。
ですが、「ほんとに仕事辞めたらこんなにお金もらえるの?」「さすがに退職してからお金もらえるわけなくない?」と疑問に思いますよね。
そんなあなたに向けて『失業保険サポート』では給付金について詳しく分かる無料Web個別相談を実施しています。
「会社を辞めたいけどお金が...」とお困りのあなた!
この機会に無料で給付金について知れる個別相談を一度試してみませんか。
公式サイト:https://roudou-pro.com/links/syakaihoken_sokyu/