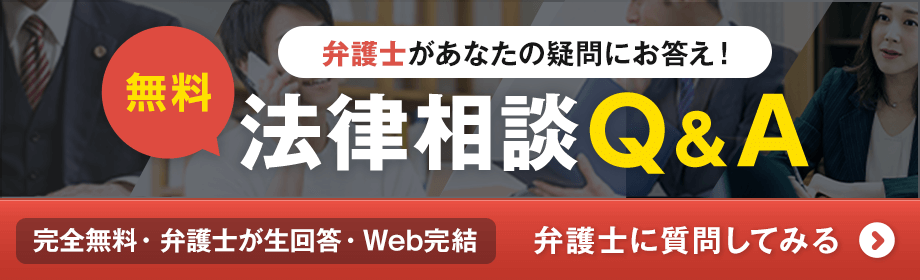労働審判は自分でできる?自力で手続きする際の流れや有利に進めるポイントを解説

労働審判とは、不当解雇などがあった場合に、労働問題の専門家である労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名が、裁判所で調停や審判をすることで、企業と労働者のトラブル解決を目指す手段です。
会社と話し合いで解決できない場合、労働審判での解決を目指すケースが多く、その際は弁護士へ依頼するのが一般的です。
しかし「弁護士へ依頼すると報酬を払わなければいけない」「頼れる弁護士の探し方がわからない」などの点から、「自分で労働審判をしたい」と考える方もいます。
労働審判は自分ですることも可能ですが、弁護士へ依頼した場合より不利な結果になりやすく、また多くの時間が必要になる傾向があるため、手続きやルールを熟知しておくことが大切です。
本記事では労働審判を自分でする方法や手続きの流れ、労働審判を進める際のポイントなどを解説していきます。
労働審判は自分ひとりでできる?10%程度の人は弁護士なしで対応している
労働審判は自分ひとりでできます。
実際に労働審判をする方のうちの10%程度は、弁護士なしで対応しています。
参考までに「弁護士白書 2023年版「労働審判事件の代理人選任状況(地裁)」に掲載されている、2022年の労働審判事件における代理人の選任状況を、以下にまとめました。
【2022年の地方裁判所における労働審判事件の代理人選任状況】
|
区分 |
件数(割合) |
|
相手方のみ弁護士代理人あり |
243件(7.4%) |
|
双方に弁護士代理人なし |
82件(2.5%) |
|
申立人のみ弁護士代理人あり |
298件(9.2%) |
|
双方に弁護士代理人あり |
2,650件(81%) |
「相手方のみ弁護士代理人あり」と「双方に弁護士代理人なし」の合計で9.9%ですから、労働審判において、労働者側である申立側が代理人をつけていないケースは約1割程度といえます。
労働審判は裁判所でのやり取りであるため、「代理人なしでは不可能」と考える方もいますが、10%程度の方は弁護士なしで対応している点をおさえておきましょう。
自分で労働審判をおこなう際に知っておくべき3つの基礎知識
自分で労働審判をする際の基礎知識として、以下の3点を把握しておきましょう。
【自分で労働審判をする際の基礎知識】
- 申し立て先
- 申し立て書類
- 申し立て費用
あらかじめ上記3点を調べておくと、よりスムーズに労働審判の手続きを進められます。そこで次の項目からは、上記3つの「自分で労働審判をする際の基礎知識」を、順に解説していきます。
申し立て先|相手方の住所地を管轄する地方裁判所など
労働審判の管轄について、労働審判法第2条には、以下のように記載されています。
労働審判法2条1項
労働審判手続に係る事件(以下「労働審判事件」という。)は、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する地方裁判所、個別労働関係民事紛争が生じた労働者と事業主との間の労働関係に基づいて当該労働者が現に就業し若しくは最後に就業した当該事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所の管轄とする。
引用元:労働審判法|e-Gov法令検索
この条文に基づいて、労働審判が実施される場所をまとめると、次のようになります。
【労働審判の申し立て先となる裁判所】
- 相手方の住所、居所、営業所または事務所の所在地を管轄する地方裁判所
- 労働者が現に就業し、または最後に就業した事業主の事業所の所在地を所轄する地方裁判所
- 当事者が合意で定める地方裁判所(合意は書面で作成)
- 労働審判の申し立て先は、会社がある場所や就業場所を管轄する地方裁判所、もしくは合意によって決めた地方裁判所のいずれかです。
- なお労働審判は簡易裁判所への申し立てができず、原則として地方裁判所の本庁や一部の支部のみで可能です。
申し立て書類|労働審判手続申立書や証拠書類など
労働審判を申し立てる際の主な書類や費用は、以下のとおりです。
【労働審判を申し立てる際の主な必要書類】
- 労働審判手続申立書
- 予想される争点についての証拠書類
- 証拠説明書
- 資格証明書(申立人または相手方が法人の場合、代表者事項証明書・全部事項証明書などが必要)
- 申立手数料(労働審判を求める事項の価額によって変化)
- 普通郵便切手(郵送する書類の重さに50gを足した重さに対応する普通郵便切手)
争点によって異なりますが、労働審判の証拠書類は不当解雇の場合、就業規則(賃金規定など含む)・雇用契約書などが該当します。
賃金未払いの場合、給与明細なども用意しておくとよいでしょう。
証拠説明書は、証拠書類の名称・作成者・証拠書類の趣旨を説明する書類です。
裁判所のホームページには労働審判手続申立書と証拠説明書の作成例が掲載されているため、記載例を参考に作成するとよいでしょう。
このほか、相手方が法人の場合、法務局で取得できる代表者事項証明書・全部事項証明書などが必要です。
申し立て費用|収入印紙や郵便切手など数千円程度
労働審判を申し立てる際には、収入印紙が必要となり、以下のとおり訴額によって印紙代が異なります。
|
訴額 |
印紙代 |
|
10万円まで |
500円 |
|
20万円~750万円 |
1,000円~20,000円 (請求額が10万円増えるごとに印紙代が500円ずつ加算) |
|
800万円~1,000万円 |
21,000円~25,000円 (請求額が50万円増えるごとに印紙代が1,000円ずつ加算) |
|
1,100万円~1億円 |
2,6200円~133,000円 (請求額が100万円増えるごとに印紙代が1,200円ずつ加算) |
上記の印紙代のほかにも、裁判所から相手方への郵便代も発生します。
労働審判の際に必要となる郵便代は、裁判所によって異なりますが、数百円~数千円程度が発生するとおさえておくとよいでしょう。
そのほかにも、交通費などをあわせると、労働審判の費用は35,000円〜40,000円程度になると考えられます。
自分で労働審判をする際には、どれくらいの費用が必要になるかをあらかじめ確認しておきましょう。
自分で労働審判をおこなう際の大まかな流れ|5ステップ
自分で労働審判をする際の流れは、以下のとおりです。
【自分で労働審判をする際の流れ】
- 裁判所に労働審判の申し立てをする
- 裁判所から相手方の答弁書が送られてくる
- 審判期日になったら裁判所で話し合いをする
- 調停が成立した場合は調停調書が作成される
- 調停が不成立の場合は裁判所から審判が出される
次の項目から、上記の各ステップの内容や注意点などを解説していきます。
1.裁判所に労働審判の申し立てをする
自分で労働審判をする場合、まずは管轄の地方裁判所へ労働審判の申し立てをします。
申し立て先は基本的に地方裁判所の本庁ですが、以下の支部への申し立ても認められています。
【労働審判の申し立てが認められている支部】
- 東京地裁立川支部
- 静岡地裁浜松支部
- 長野地裁松本支部
- 広島地裁福山支部
- 福岡地裁小倉支部
労働審判の申し立てをする際は、所轄の裁判所へ労働審判手続申立書・証拠書類・証拠説明書などを提出します。提出方法は基本的に郵送・持参の2種類です。
2.裁判所から相手方の答弁書が送られてくる
労働審判の申し立てが受理されると、原則として申し立てから40日以内に第1回目の期日が指定され、当事者が呼び出されます。
相手方の企業には、期日呼出状や申立書の写しなどが送られます。
なお、答弁書には、以下の内容を記載して提出します。
- 申立ての趣旨に対する答弁
- 申立書記載の内容に対する認否
- 答弁の裏付けとなる具体的な事実
- 予想される争点・装填に関する重要な事実
- 争点ごとの証拠
- 従前に交渉があった場合はその内容など
相手方から提出された答弁書の内容は、申立人にも送付されるため、相手方の具体的な主張などを確認し、期日までに対策を講じるなどの準備をしましょう。
3.審判期日になったら裁判所で話し合いをする
審判の期日になったら、申し立てた先の地方裁判所で実施される審理に参加します。
労働審判は労働審判官(裁判官)1名、労働審判員(労働実務の有識者)が2名の合計3名で労働審判委員会を構成したうえで、審理されます。
労働審判の期日は、原則3回までとされており、各期日では、以下の内容を話し合います。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.調停が成立した場合は調停調書が作成される
第1回期日から第3回期日までの間の労働審判で和解が成立した場合、調停調書が作成されます。
調停調書とは、調停で決まった内容を記載した書類のことで、確定判決と同じ効力をもつとされています。
そのため、調停調書が作成されたあと、当事者は同じ争点を再度争えなくなり、義務が果たされない場合は強制執行されることがあります。
5.調停が不成立の場合は裁判所から審判が出される
和解が成立しない場合は、第1回期日から第3回期日までの事情を考慮して、労働審判委員会が審判を下します。
審判から2週間以内に異議申し立てがされない場合、審判が確定し、手続きが終わります。
なお、第3回期日が終了しても、和解できる可能性が高いと判断された場合は、第4回期日の審判が開かれることがあります。
審判に納得がいかない場合は異議の申し立てをする
下された審判の内容に納得できない場合、労働審判の口頭告知を受けた日、または審判書の送達を受けた日から2週間以内に異議申し立てをすることで、審判の内容を失効させ、訴訟で争うことができます。
なお、弁護士白書 2023年版「労働審判事件の新受・既済件数(地裁)」では、労働審判のうち70%〜80%で話し合いを意味する「調停」が成立しており、10%〜20%程度は、労働審判委員会が下す「審判」で手続きが終了したとされています。
このような点から、労働審判から訴訟に発展するケースは少ないといえるでしょう。
労働審判で自分にとって有利な結果を得るための3つのポイント
労働審判で有利な結果を得るためのポイントは、以下の3つです。
【労働審判で有利な結果を得るためのポイント】
- 説得力のある労働審判手続申立書を作成する
- 第1回期日に向けて主張や証拠を整理しておく
- 依頼しなくてもいいので弁護士に相談しておく
次の項目から、上記3つのポイントを解説していきます。
1.説得力のある労働審判手続申立書を作成する
短期間での解決を目指す労働審判においては、説得力のある労働審判手続申立書を提出することが重要です。
審判の結果は、どれだけ説得力のある申立書を作成でき、どれだけ有力な証拠を揃えられるのかに左右されます。
説得力のある労働審判手続申立書を作成するコツは、以下のとおりです。
【説得力のある労働審判手続申立書を作成するコツ】
- 争点と関係性の低い内容や不満などの感情論は極力掲載しない
- 申立人有利の結果となった、似た判例を記載する
- 自分に不利な事実は受け入れて労働審判委員会の心証を良くするための内容を書く
- 証拠のうち特に見てほしい部分を申立書に記載する
- 事例は「誰が」「いつ」「どこで」「誰に対して」「どのようなことをしたのか」などを具体的に書く
- 項目に題名をつける・一文を短くするなどの読みやすさを意識する
上記6点を意識して労働審判手続申立書を作ると、できる限り説得力のある、わかりやすい内容にできるため、労働審判で有利になる可能性を高められます。
また、誤字脱字をなくすと読みやすくなるため、労働審判手続申立書を作ったあとに見直すことも重要です。
大げさな表現や感情的な表現を濫用するとかえって書面の説得力が失われることになりますのでご注意ください。
2.第1回期日に向けて主張や証拠を整理しておく
労働審判で有利になるため、第1回期日に向けて、主張したい内容や確認してほしい証拠を整理しておくことをおすすめします。
原則として3回までの審理で解決を目指す労働審判は、限られた期間内に迅速かつ適正に解決することを目的としています。
そのため、書類提出時に十分な証拠と訴えをわかりやすく記載し、第1回期日で簡潔かつ的確に主張することが重要です。
自分で労働審判をする場合、「緊張して主張すべきことを伝えられなかった…」と後悔しないよう、内容を整理してメモなどにまとめておきましょう。
3.依頼しなくてもいいので弁護士に相談しておく
労働審判は自分で手続きできますが、ある程度の見通しを立てるためにも、弁護士に相談してみることをおすすめします。
無料相談可能な弁護士なら、費用をかけずに専門家の意見やアドバイスをもらえます。
労働審判は、訴訟と比べて少ない時間での解決を目指すため、十分な準備・対策をすることが重要です。
さらに、各期日には口頭で主張するため、あらかじめ相手の答弁書をしっかりと理解して、証拠とともに論理的に述べなければ不利な結果になりかねません。
このような点から、労働審判でよい結果を出したい場合は、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
労働事件を得意とする弁護士に相談すれば、専門知識・豊富な経験をもとに、現状や今後についてアドバイスをしてくれるでしょう。
また、弁護士に相談することで、労働審判に適さない事案と早い段階で気づくことができれば、余計な手間暇をかけないで済む点もメリットです。
相談だけでも受け付けてくれる弁護士は少なくないため、自分で労働審判をしようと考えている場合でも、まずは弁護士の意見を聞いてみることをおすすめします。
労働審判を弁護士なしでおこなう際の3つの注意点
弁護士なしで労働審判をする場合、以下の3点に注意しましょう。
【弁護士なしで労働審判をする際の注意点】
- 労働審判の対象とならない事件がある
- 3回の期日を迎える前に終了することがある
- 必ずしも労働者にとって有利な結果になるとは限らない
あなたが直面している問題が労働審判では解決できず、訴訟に移行しなければならないケースの場合、労働審判の手続きをすると、時間や労力を無駄にしてしまう可能性があります。
また、自分で手続きすることによって、不利な結果となる恐れもあるため、上記3つの注意点を把握しておくことをおすすめします。
そこで次の項目から、労働審判を弁護士なしで実施する際の3つの注意点を順に見ていきましょう。
1.労働審判の対象とならない事件がある
労働審判の対象になるのは「個別労働関係民事紛争」だけです。
具体的には、労働審判の対象になる個別労働関係民事紛争は、以下の事件が該当します。
【労働審判の対象になる事件の例】
- 解雇や懲戒処分の効力を争う事件
- 賃金請求事件
- 退職金請求事件
- 解雇予告手当請求事件
- 時間外手当請求事件
- 労災等の損害賠償請求事件
不当な解雇・懲戒のほか、賃金などの不払いは労働審判の対象になりますが、公務員の雇用や労働組合が当事者の場合、対象外となるため注意しましょう。
2.3回の期日を迎える前に終了することがある
労働審判は原則3回という短期間での解決を目指す手続きであるため、状況によっては労働審判委員会が「労働審判に適していない」と判断し、3回の期日を待たずに訴訟に移行することがあります。
具体例としては、トラブルの内容が複雑な場合や、双方の主張が大きく食い違っており、妥協点を見つけられないと判断される場合などが挙げられます。
この点を把握しておかないと、「手間暇をかけて労働審判を進めたのに、結局訴訟になり、弁護士へ依頼することになった…」という状況になりかねません。
そのため、自分で手続きをしようと考えている場合であっても、最初に「労働審判に適した案件かどうか」を弁護士に相談することをおすすめします。
3.必ずしも労働者にとって有利な結果になるとは限らない
労働審判を申し立てても、もちろん必ず勝てるとは限りません。
例えば会社側に弁護士がついている場合、自分で労働審判をすると、法的知識の少なさから不利な内容を多く述べてしまい、負けることも考えられます。
弁護士費用を節約するために自分で労働審判を行い、判断ミスや戦略のミスで負けてしまっては本末転倒かと思います。
そのため、労働審判でよい結果を出したい場合は、専門家に相談しながら計画的に進めていくのがよいでしょう。
労働審判を自分でおこなう場合のよくある質問
労働審判を自分でする際のよくある質問は、以下の3つです。
- Q.労働審判を弁護士に依頼せずに自分でおこなうメリットは?
- Q.労働審判を弁護士に依頼せずに自分でおこなうデメリットは?
- Q.労働審判の手続きをできる限り安く弁護士に依頼するにはどうしたらよいか?
上記3つのよくある質問について、次の項目から順に解説していきます。
Q.労働審判を弁護士に依頼せずに自分でおこなうメリットは?
労働審判を自分でするメリットは、費用をおさえやすいところです。
労働審判にかかる弁護士費用は着手金が30万円前後、成功報酬は請求額の約15%~20%前後が相場ですが、自分で手続きをする場合、これらの費用を節約できます。
以下のようなケースであれば、弁護士に依頼するより、自分で手続きをするほうがメリットを感じやすいでしょう。
【自分で労働審判をしてメリットを感じやすい状況】
- 請求できる額が低い
- 会社の違法性が明らかでトラブルが複雑でない
- 請求できる金額が形式的に決められている
Q.労働審判を弁護士に依頼せずに自分でおこなうデメリットは?
労働審判を自分ですることには、以下のデメリットがあります。
【労働審判を自分でする際のデメリット】
- 自分で書類や証拠の準備をしなければならない
- 書類作成時・口頭での説明時に簡潔さ・的確さを求められる
労働審判は短期間での解決を目指すため、第三者が見て納得できる、説得力の高い書類や証拠を用意することが重要です。
また審理は口頭のため、論理的な説明能力も求められます。
事件が単純でない場合、自分で労働審判を進めることは難しいため、まずは弁護士の意見を聞いてみることをおすすめします。
Q.労働審判の手続きをできる限り安く弁護士に依頼するにはどうしたらよいか?
弁護士費用を節約する方法は、主に以下の2つです。
【弁護士費用を節約する方法】
- 弁護士費用保険を使う
- 法テラスの民事法律扶助業務を使用する
- 成功報酬制で弁護士に依頼する
法テラスでは、一定の資力要件(給与額、資産額が一定額を上回らない)を満たす方のため、民事法律扶助業務にて、無料の法律相談や弁護士費用の立替などをしているため、労働審判の費用をおさえたい場合は利用を検討するとよいでしょう。
基本的には以下の条件を満たせば法テラスの民事法律扶助業務の立替制度を利用できます。
【法テラスの弁護士費用立替制度が利用できる条件】
- 資力が一定以下であること
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと
- 民事法律扶助の趣旨に適する方
また、弁護士費用保険とは保険会社や共済協同組合が販売する保険で、弁護士に法律相談や交渉などの依頼をした際の費用が保険金(100万円〜300万円程度)として支払われます。
クレジットカードに付帯していることもあるため、弁護士費用保険を利用できる方は、労働審判の弁護士費用に使えるかどうか確認してみましょう。
労働審判についても、着手金不要の成功報酬制で受任している弁護士もいます。
成功報酬制で依頼すれば、成果があった場合は報酬が発生することにはなりますので、必ずしも弁護士費用が節約できるわけではありませんが、成果があるまでは費用は発生せず、また、敗けた場合は弁護士費用は生じませんので、費用倒れを防ぐことができます。
費用倒れが怖いので弁護士に依頼するのを躊躇する、という方は、成功報酬制で弁護士に依頼してみるのもよいかもしれません。
さいごに|労働審判の無料相談をするなら「ベンナビ労働問題」がおすすめ
労働審判は自分で手続きでき、実際に1割程度が弁護士に代理人を依頼していません。
ただし、労働審判は原則3回の期日という限られたスケジュールで審理をするため、申立書や証拠の内容が重要です。
さらに審理では口頭で主張しなければならないため、入念な準備と明確で説得力のある説明をすることも大切です。
会社側に明らかな違法性が認められるような複雑ではないトラブルなら、自分で労働審判の手続きをできる場合もありますが、複雑な場合には弁護士でないと対応できないケースもあります。
事件内容によっては労働審判に適していないと判断され、3回の期日を待たず、訴訟へ移行することもあるため、労働審判の手続きをする際は、まず弁護士に相談することをおすすめします。
「ベンナビ労働問題」であれば、無料で労働審判の相談ができる弁護士を探しやすいため、不当解雇や賃金未払いなど、会社とのトラブルに直面している場合は、ぜひご活用ください。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

【不当解雇・残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
 この記事の監修
この記事の監修

弁護士法人勝浦総合法律事務所【東京オフィス】

労働審判に関する新着コラム
-
労働審判は自分ですることも可能ですが、多くの時間が必要になる傾向があるため、手続きやルールを熟知しておくことが大切です。本記事では労働審判を自分でする方法や手続...
-
就業規則とは、給与規定や退職規定などの労働条件が記載されている書類です。従業員を10人以上雇用している会社であれば、原則として作成した後に労働者に周知し、労働基...
-
パワハラを受けた方にとっては理不尽で許し難いものであり、パワハラをした相手に何か報復したいと考える方もいるでしょう。そこで今回は、パワハラの訴え方と訴える前に考...
-
企業が労働基準法に違反した行為をすると罰則が与えられます。以下で労働基準法違反となるのはどういったケースなのか、その場合の罰則はどのくらいになるのかご説明してい...
-
労働問題を迅速に解決してくれる労働審判。個人でも申し立てられる労働審判ですが、もちろん弁護士を付けておけば有利に進めることができます。それでは、労働審判にかかる...
-
労働審判を利用する際に弁護士に相談するメリット、弁護士に依頼する際の選び方のポイント、労働審判が得意な弁護士の選び方、いつ弁護士に相談するかを解説していきます。
-
労働審判の流れを解説。残業代の未払いや不当解雇等、労働問題が起きた場合には労働審判を利用することで、お金や手間をかけずに解決できる場合があります。上手く活用する...
-
代替休暇制度(だいたいきゅうかせいど)とは、月60時間を超える部分の時間外労働について、50%以上の割増賃金の支払いの代わりに有給休暇を与える制度です。今回は「...
-
試用期間中に「この会社合わないかも…。」と思って退職を考える人もいるでしょう。試用期間中の退職は正社員同様、退職日の申し出や退職届などが決まっています。この記事...
-
総合労働相談コーナーは労働条件の不当な変更や解雇、雇い止め、ハラスメントなどの相談窓口です。総合労働相談コーナーでは労働者からの相談に対し解決方法の提案や紹介を...
労働審判に関する人気コラム
-
パワハラを受けた方にとっては理不尽で許し難いものであり、パワハラをした相手に何か報復したいと考える方もいるでしょう。そこで今回は、パワハラの訴え方と訴える前に考...
-
企業が労働基準法に違反した行為をすると罰則が与えられます。以下で労働基準法違反となるのはどういったケースなのか、その場合の罰則はどのくらいになるのかご説明してい...
-
労働者にとってセーフティネットとして利用できる雇用保険、条件を満たしていれば誰でも加入できますが、もし未加入だったときどうすればいいのでしょう。
-
サービス残業とは、企業が残業代を支払わずに従業員に残業をさせることです。そもそもサービス残業は支払うべき賃金を正当な理由なく支払わない行為であるため、違法であり...
-
試用期間中に「この会社合わないかも…。」と思って退職を考える人もいるでしょう。試用期間中の退職は正社員同様、退職日の申し出や退職届などが決まっています。この記事...
-
労災保険(労働災害補償保険)は事業主、役員、特殊な業種の方以外は原則「強制加入」の保険です。労災保険手続きを行わず未加入の場合は、会社側が保険料や給付金の追加徴...
-
みなし残業で働いている方の中には、みなし残業の多さに疑問を持った方もいるともいます。労働基準法で定められている残業の上限は45時間。45時間を超えたみなし残業は...
-
みなし残業には、残業が少ない月も残業代がもらえるというメリットがある一方、と慢性的な長時間労働や未払い残業の原因になるというデメリットもあります。労働制度をきち...
-
就業規則とは、給与規定や退職規定などの労働条件が記載されている書類です。従業員を10人以上雇用している会社であれば、原則として作成した後に労働者に周知し、労働基...
-
労働問題を迅速に解決してくれる労働審判。個人でも申し立てられる労働審判ですが、もちろん弁護士を付けておけば有利に進めることができます。それでは、労働審判にかかる...
労働審判の関連コラム
-
基本給が低いことによって、労働者側にデメリットはあるのでしょうか。こちらの記事では基本給の概括や、基本給が低いことで受ける影響を、法律の専門家である弁護士監修の...
-
みなし残業などの固定残業代制度は、違法な長時間労働や未払い賃金などに注意が必要です。この記事では「固定残業を支払っているのだから、労働者を残業させてもとよい」と...
-
パワハラを受けた方にとっては理不尽で許し難いものであり、パワハラをした相手に何か報復したいと考える方もいるでしょう。そこで今回は、パワハラの訴え方と訴える前に考...
-
雇い止めは労働法の法改正により、話題になっています。雇い止め自体は、労働契約として合法的なものなのですが、雇い止めを行った経緯が不当なものである場合無効を主張で...
-
文書提出命令とは何か、どのような効果があり、どんな文書の提出を命令してもらえるのかを解説!労働問題では残業代請求や不当解雇などの証拠を取れる可能性が高い「文書提...
-
労働審判の流れを解説。残業代の未払いや不当解雇等、労働問題が起きた場合には労働審判を利用することで、お金や手間をかけずに解決できる場合があります。上手く活用する...
-
法定労働時間は労働基準法定められている『1日8時間、週40時間』以下の労働時間のことです。法定労働時間は労働賃金や残業代などの計算において基本となるものです。こ...
-
テレワーク、在宅勤務時の負傷等について労災認定を受けるための要件を詳しく解説!在宅勤務で労災が認められる場合、認められない場合の具体例について、法律の専門的な観...
-
弁護士依頼前の様々な疑問・不満を抱えている方も多いでしょう。今回は、それら労働問題の弁護士選び方に関する内容をお伝えしていきます。
-
労働者にとってセーフティネットとして利用できる雇用保険、条件を満たしていれば誰でも加入できますが、もし未加入だったときどうすればいいのでしょう。
-
労災保険(労働災害補償保険)は事業主、役員、特殊な業種の方以外は原則「強制加入」の保険です。労災保険手続きを行わず未加入の場合は、会社側が保険料や給付金の追加徴...
-
過労死の裁判は、労働基準監督署での労災認定、会社への損害賠償、刑事的責任など、それぞれ争うことになります。この記事では、過去の判例から、過労死の認定基準、裁判の...
労働審判とは、2006年4月に導入された、地方裁判所で職業裁判官(労働審判官)1人と使用者側有識者、労働者側有識者(労働審判員)各1名ずつの合計3人で構成された労働審判委員会の下で、使用者と労働者の間の紛争を適正かつ迅速に解決するための審判制度です。労働審判の目的は、給与の不払いや解雇などといった事業主と個々の労働者の間で発生した労働紛争を、迅速・適正かつ効果的に解決することです。
労働審判の流れを解説|労働審判を活用する際の手続きと解決フロー
労働問題であれば、権利・利益の大小関わらず労働審判を申し立てることができます。実際の手続では特に賃金関係と解雇関係の事件が主を占めています。
例えば、残業代・給与・退職金や賞与の未払いといった賃金に関する問題や、不当解雇・雇い止め・退職勧奨といった雇用に関する問題が多いです。
原則として、公務員の労働審判はできません。
公務員は、国家公務員法や地方公務員法に基づいて登用されており、民間の労働者とは立場が異なります。そのため、公務員と国・地方自治体との紛争は民事に関する紛争に該当しないものとして、労働審判の対象にはなりません。
弁護士費用は弁護士事務所によって金額が違うため、決定的に「いくら」という決まりはありません。
一般的に20~40万円+成功報酬(請求金額の15%~20%前後)の合計60~100万円程あたりが相場になっていますが、報酬基準は事務所単位で設定されており、報酬額も事案に応じて変動します。
弁護士に相談、依頼時に労働審判の申し立てにかかる費用がどれくらいかかるかをしっかり確認しましょう。
申立から終結まで平均75日(約2ヶ月半)ほどとなっております。原則3回以内で審理を終結しなければならないと法律で定められており、実際にも97%以上が3回以内、7割は2回以内で終結しています。
通常訴訟では一審手続は2年以内のできるだけ短い期間内に終えることが努力目標とされているにすぎず、回数も8~10回程度と多く、いかに労働審判に迅速性があることがわかります。
また、労働審判から通常訴訟に移行した場合でも、労働審判で,基本的に双方の主張立証は出尽くしているため、最初から通常訴訟を起こした場合よりも解決までの時間は短くて済みます。