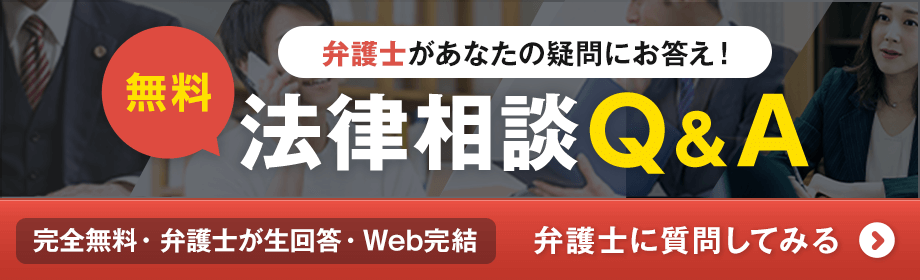就業規則(しゅうぎょうきそく)とは、働く上での労働賃金や労働時間、労働条件などについて事業場ごとに定めたものです。なお、労働者を常時10人以上雇用している会社の場合は、就業規則の作成と届出が原則として義務付けられています。(労働基準法第89条)
ただし、就業規則の効力自体は労働基準監督署への届出の有無とは関係ありません。事業所内で周知されてさえいれば就業規則は効力を有します。
なお、就業規則で定めればどのようなルールも効力を発揮できるわけではありません。合理性に欠く内容は無効になる場合もあります。
この記事では、就業規則を定める上でのルールと、労働条件の変更をする場合の対応についてご紹介します。
就業規則のルールと絶対的記載事項

就業規則を作成し、効力をもたせる場合は、事業所での周知が必要です。労働基準監督署に届出がなくとも周知されていれば、就業規則は有効です。
この項目では就業規則を定める上でのルールや記載事項についてご紹介します。
就業規則を定める際のルール
就業規則は、常時10人以上の労働者を雇用している会社であれば必ず作成し、管轄の労働基準監督署に届出なければなりません。
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
引用元:労働基準法
また、作成した就業規則に効力を持たせるには、労働者への周知が必要です。事前に労働者代表に意見を聞いた上で就業規則を作成し、労働者がいつでも内容を知ることができる状態にすることで『労働者への周知』ができていると判断します。
就業規則を作成する際の記載事項
就業規則を作成する際は、どのようなことを規定するのか細かく法律で定められています。そのなかで、必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)と会社の任意で記載する事項(相対的記載事項)を以下にまとめました。
|
絶対的記載事項 |
相対的記載事項 |
|
|
退職金やボーナス(賞与)などは、相対的記載事項です。そのため、会社で制度や規定がなくても違法ではありません。また、ハラスメント規定に関しては、記載事項として定められていませんが、会社側は規定しておくべきでしょう。
なお、これら事項が記載されていなくても就業規則に効力をもたせることができます。
おすすめ記事:正社員なのにボーナスが全くない…法律はどう定めている?|シェアしたくなる法律相談所
就業規則の法的効力

就業規則は、労働基準法に準じて労働条件を定めることができます。
労働規定で効力の優先順位は以下の通りです。ただし、労働基準法はあくまでも最低ラインとなるので労働者にとって有利なものが優先されるケースもあります。
|
※労働協約とは…労働組合と会社との間での取り決め
労働者が確認しておくべき就業規則とは

就業規則は会社で働く上で、重要なものですから入社した際には必ず目を通しておきたいものです。
ただ、就業規則などの会社の書面はかしこまった言葉で書かれていることが多いのですべてに目を通すのは根気がいります。そこで、この項目では必ず確認しておくべき項目を4つにしぼってご紹介します。
給与(賃金)規定
会社の給与規定には、残業などの時間外労働の割増賃金などの重要項目が書かれています。
もしも、残業代や給料などの未払い賃金トラブルを抱えている場合は、就業規則は重要な証拠にもなるのでコピーを手元に残しておきましょう。
|
おすすめ記事 |
休暇規定
休暇規定には有給休暇や慶弔休暇などについての項目が書かれています。有給休暇は、現行の法律では入社6ヶ月後に付与されます。
休暇規定を確認する際は、会社が繁忙期などを理由に労働者の休暇取得時期を調整する『時季変更権』の行使条件等を見ておくとよいかもしれません。
おすすめ記事:年次有給休暇とは|5分でわかる基本概要まとめ
退職規定
退職規定には退職を申し出る際の手続きなどについて記載してあります。
なお、退職金は法律上の権利ではなく会社が任意で設定する制度です。そのため、就業規則で退職金の定めがないことは違法ではありませんし、定めがなければ退職金の支払いを求めることはできません。
おすすめ記事:未払い退職金を請求するための手順と退職金が払われる条件
ハラスメント
ハラスメントは記載事項として指定されているものではありませんが、労働基準法や男女雇用機会均等法などに関わるため、基本的には就業規則でハラスメント防止に関する規定が置かれています。
- 職場上の立場を利用した嫌がらせ(パワーハラスメント)
- 性的な言動(セクシュアルハラスメント)
- 妊娠・出産を理由とした言動(マタニティハラスメント)
このようなハラスメントを受けている場合は、就業規則に基づき社内のコンプライアンス窓口に相談しましょう。
|
おすすめ記事 |
就業規則を変更するときのルールと対処法

就業規則は、法改正や時代にあわせて更新(変更)することもあります。
特に、2018年はさまざまな労働法の改正があります。
この項目では、就業規則を変更するときのルールと対処法についてご紹介します。
変更にはルールがある
就業規則の変更によって労働者が不利益を被る場合、労働契約法で定められた不利益変更のルールにのっとってこれを適用する必要があります。
なお、変更後のルールを適用する場合にはやはり就業規則の周知が必要です。
また、変更後の就業規則についても労働者代表などからの意見聴取や労働基準監督署への届出といった手続きが必要です。
不利益な労働条件の変更は弁護士に相談
就業規則の『不利益変更』によって労働条件や待遇が低下している場合、変更自体の効力を争うことができます。もっとも、この場合不利益変更の合理性について細かく専門的な議論が必要となりますので、弁護士に相談するのが得策でしょう。
まとめ
就業規則は働くなかで、重要な事項が記載されていますが、普段は軽視してしまいがちですよね。
ここ数年はさまざまな労働法が改正されるので、就業規則の変更があるかもしれません。自身がどのような条件で働いているのかなど、この機会に一度見直してみましょう。
この記事で、就業規則に関する疑問が解消されれば幸いです。
|
出典元一覧 |
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

【不当解雇・残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る
【正社員の方限定】退職勧奨や残業代未払い、不当解雇、退職代行から労働組合関係まですべての正社員の方の権利をお守りいたします/当日相談・メール、LINEでの相談受付◎/分割払いや後払いにも対応可能
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡


労務問題に関する新着コラム
-
長時間労働やハラスメントなどに苦しんでいる場合は、安全配慮義務違反として会社の責任を問うことも検討する必要があります。本記事では、安全配慮義務違反に該当するケー...
-
会社に有給休暇を申請したところ、「当日の休暇申請は欠勤だ」といわれてしまい、理不尽に感じている方もいるはずです。本記事では、有給休暇の取得条件や欠勤との違い、休...
-
取締役は原則いつでも辞任・退職できます。ただし、業務の途中や引継ぎなしで退職しようとすると、損害賠償を請求されることも少なくありません。本記事では、取締役の辞任...
-
実際に起こったコンプライアンス違反の事例をご紹介し、会社経営をする上で、どのような部分に気を付け、対処しておくべきかをご説明します。こちらの記事でご紹介した、コ...
-
内部告発は社内の不正を正すためにおこなうものです。しかし、内部告発をおこなったことによって不遇な扱いを受けてしまうケースも少なくありません。今回は内部告発のやり...
-
譴責は、懲戒処分の一つとして、会社の就業規則に定められるケースが多いでしょう。譴責処分を受けると、処分対象者の昇給・昇格に不利益な効果が生じることがあります。 ...
-
退職代行サービスを使われた企業はどう対処すればいいのか?弁護士運営ではない退職代行サービスは非弁行為?退職代行サービスを利用された後の流れや退職代行サービスを利...
-
就業規則とは、給与規定や退職規定などの労働条件が記載されている書類です。従業員を10人以上雇用している会社であれば、原則として作成した後に労働者に周知し、労働基...
-
団体交渉を申し込まれた場合に拒否をしてはならない理由や、拒否が認められる可能性がある正当な理由、また拒否する以外に団体交渉において会社が取ってはならない行為をご...
-
使用者が労働組合からの団体交渉の申入れを正当な理由なく拒否したり、組合活動を理由に労働者を解雇したりすると「不当労働行為」として違法となります。不当労働行為のパ...
労務問題に関する人気コラム
-
有給休暇とは、労働者が権利として取得できる休日のことです。有給休暇の取得は権利であり、これを会社が一方的に制限することは原則として違法です。この記事では、有給休...
-
残業代は原則、いかなる場合でも1分単位で支給する必要があります。しかし、会社によっては従業員へ正規の残業代を支払っていない違法なケースも存在します。この記事では...
-
在職証明書とは、職種や業務内容、給与など現在の職について証明する書類です。転職の際や保育園の入園申請時などに求められる場合がありますが、発行を求められる理由や記...
-
所定労働時間について知りたいという方は、同時に残業時間・残業代を正確に把握したいという思いがありますよね。本記事ではその基礎となる労働時間に関する内容をご紹介し...
-
就業規則とは、給与規定や退職規定などの労働条件が記載されている書類です。従業員を10人以上雇用している会社であれば、原則として作成した後に労働者に周知し、労働基...
-
同一労働同一賃金は2021年4月より全企業に適応された、正社員と非正規社員・派遣社員の間の待遇差を改善するためのルールです。本記事では、同一労働同一賃金の考え方...
-
管理監督者とは労働条件などが経営者と一体的な立場の者をいいます。この記事では管理監督者の定義や扱いについてわかりやすく解説!また、管理監督者に関する問題の対処法...
-
ホワイトカラーエグゼンプションとは、『高度プロフェッショナル制度』ともいわれており、支払う労働賃金を労働時間ではなく、仕事の成果で評価する法案です。この記事では...
-
高度プロフェッショナル制度は、簡単に『量』ではなく『質』で給料を支払うという制度です。残業代ゼロ法案などと揶揄されていますが、働き方改革の関連法案でもある高度プ...
-
内部告発は社内の不正を正すためにおこなうものです。しかし、内部告発をおこなったことによって不遇な扱いを受けてしまうケースも少なくありません。今回は内部告発のやり...
労務問題の関連コラム
-
社内で犯罪行為などが発生することを防ぐためには、内部通報制度を設けることが有効です。その際、社内窓口を設置するだけでなく、弁護士に社外窓口を依頼すると、より効果...
-
内部告発は社内の不正を正すためにおこなうものです。しかし、内部告発をおこなったことによって不遇な扱いを受けてしまうケースも少なくありません。今回は内部告発のやり...
-
うつ病になった社員の復帰が難しい場合の対処法やトラブルを防ぐためにできる退職までの話の進め方、うつ病で解雇して裁判になった過去の例などをご説明します。うつ病の社...
-
監査役を解任する方法や解任時の注意点について解説。監査役はたとえ任期途中であっても株主総会の特別決議によって解任することができます。実際に解任する際の流れや、解...
-
団体交渉は誤った対応した際の不利益が大きいため、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。この記事では、団体交渉で弁護士に依頼するメリットや注意点、費用、団体交渉...
-
近年、コンプライアンスの重要性の高まりが盛んに指摘されています。コンプライアンスは、企業が社会の中で経済活動を続けていくうえで、無視できない重要な問題です。この...
-
離職票とは退職した会社から受け取る書類のひとつで、失業給付の申請にあたり必要となるものです。どんな内容の書類なのか、いつ手元に届くのかなど、離職票を希望する際に...
-
同一労働同一賃金は2021年4月より全企業に適応された、正社員と非正規社員・派遣社員の間の待遇差を改善するためのルールです。本記事では、同一労働同一賃金の考え方...
-
従業員の勤務態度を評価する際、どの様なポイントで判断して評価すべきか、『行動』『姿勢』をメインとした評価と、『実績』『能力』『勤務態度』の全てを評価するもの人事...
-
就業規則とは、給与規定や退職規定などの労働条件が記載されている書類です。従業員を10人以上雇用している会社であれば、原則として作成した後に労働者に周知し、労働基...
-
在宅勤務をする場合に支給される在宅勤務手当について解説。利用用途や支給方法について実例を挙げて紹介。在宅勤務の管理方法や企業・労働者それぞれの目線からのメリット...
-
問題社員の辞めさせ方が知りたい会社は案外多いのではないでしょうか。この記事では、問題社員を辞めさせる際に考慮すべきポイントや注意点、不当解雇とならずに解雇するた...