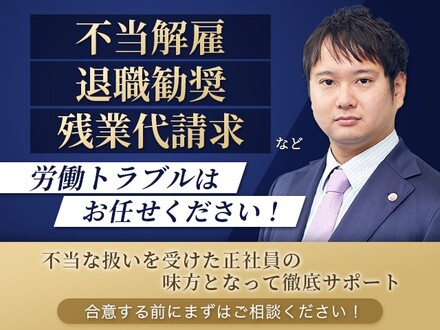本コンテンツには、紹介している商品(商材)の広告(リンク)を含みます。
ただし、当サイト内のランキングや商品(商材)の評価は、当社の調査やユーザーの口コミ収集等を考慮して作成しており、提携企業の商品(商材)を根拠なくPRするものではありません。
「退職した後は何からやればいいの?」
「退職後の手続きを順番で教えて!」
退職を検討している方、すでに退職済の方でこのような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
退職後は健康保険の切り替えや国民年金への加入など、さまざまな手続きが必要です。
そこでこの記事では、退職したらやることを順番に解説します。
この記事を読めば、退職後の手続きの流れ、税金の支払い方法などがすべてわかります。退職後にやることがわからない方は、ぜひこの記事を参考に手続きを進めてみましょう。
あわせて読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
会社辞めたらお金もらえるって知ってる?

『失業保険サポート』では、退職後にもらえる給付金を受け取るサポートをしてもらえます。
実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。
| 平均月収 |
月間でもらえる金額 |
| 月収30万円 |
約20万円 |
| 月収40万円 |
約26万円 |
| 月収50万円 |
約33万円 |
| 月収60万円 |
約40万円 |
| 月収70万円 |
約46万円 |
| 月収80万円 |
約53万円 |
| 月収90万円 |
約60万円 |
| 月収100万円 |
約66万円 |
会社を辞めて給付金を申請するだけでこんなにもお金がもらえます。
ですが、「ほんとに仕事辞めたらこんなにお金もらえるの?」「さすがに退職してからお金もらえるわけなくない?」と疑問に思いますよね。
そんなあなたに向けて『失業保険サポート』では給付金について詳しく分かる無料Web個別相談を実施しています。
「会社を辞めたいけどお金が...」とお困りのあなた!
この機会に無料で給付金について知れる個別相談を一度試してみませんか。
公式サイト:https://roudou-pro.com/links/syakaihoken_sokyu/
今の仕事をやめたいけど、
次の一歩が不安なあなたへ |
|
多くの人が、退職前に次の職場を決めることで、経済的にも精神的にも安心して新しいスタートを切っています。
次こそは・・・
・人間関係が良好な職場で働きたい
・頑張りを政党に評価してくれる職場で働きたい
・残業や休日出社のないホワイトな職場で働きたい
今のような仕事の悩みを二度と抱えたくない!
このような思いの方は、転職エージェントに無料相談して、あなたにピッタリの求人を提案してもらうのがおすすめです。
有益なアドバイスがもらえるだけではなく、履歴書作成から面接対策まで転職活動を完全無料でサポート。ストレスフリーな環境からの再スタートを目指せます。
|
【リスト】退職したらやることの順番
退職したらやることの順番を一覧でご紹介します。各手続きの順番を整理しておきましょう。
| 手続きの順番 |
申請期限 |
申請先/支払い方法 |
| 1:健康保険への切り替え |
退職後14日以内 |
居住地域の役所 |
| 2:国民年金への加入手続き |
退職後14日以内 |
居住地域の役所 |
| 3:失業保険の手続き |
退職後一か月以内 |
居住地域のハローワーク |
| 4:住民税や所得税の納付 |
ー |
納付書払い |
退職後は、これらの手続きが必要であり、手続き方法や申請先などが異なります。
一つの窓口でまとめて申請できないため、余裕を持って進めましょう。
退職に関連する必要書類
退職後の手続きに必要となる書類をご紹介します。手続きする前に書類が揃っているかどうか確認しておきましょう。
退職時に会社から受け取る書類
退職時に会社から受け取る書類は以下のとおりです。
| 名称 |
内容 |
| 離職票 |
失業保険を申請する際に必要な書類。
退職後に会社から受け取る。郵送されることが多い。 |
| 雇用保険被保険者証 |
雇用保険に加入していたことを証明する書類。
次の就職先に提出する。 |
| 源泉徴収票 |
その年の収入額や納税額を確認するための書類。
確定申告や新しい職場での年末調整に必要。 |
| 健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書 |
退職後の社会保険手続きや国民健康保険の加入手続きに必要な書類。 |
これらの書類は、退職時に受け取るだけでなく再就職時にも必要となるため、紛失しないように保管しておきましょう。
再就職時に必要となる書類
再就職時に会社から受け取る書類は、前述した「会社から受け取る書類」のほかに以下の書類が必要です。
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
- 年金手帳
- マイナンバー確認書類(通知カード可)
- 住民票
- 前職の給与明細
これらは自分で用意する必要があります。住民票は管轄の役所に行かないと受け取れないため、早めに行動しましょう。
STEP1:健康保険への切り替え
退職したらまずは健康保険へ切り替えましょう。切り替え期日や申請方法を解説します。
- 手続き期限は14日以内
- 手続きが遅れても加入は可能
- 必要書類の準備
- 複数の保険から選択
- 退職後すぐに再就職する場合は切り替え不要
手続き期限は14日以内
健康保険の切り替え手続きは、退職後14日以内におこないましょう。
この期限を過ぎた場合、加入手続きが遅れた期間の保険料をさかのぼって支払う必要があり、予想外の出費となる可能性が高いです。
また、未加入期間中に病院の診察を受けた場合、保険が適用されずに医療費が全額自己負担になることもあるので注意が必要です。
手続きは市区町村の役所でおこなうため、退職後は速やかに準備しましょう。
手続きが遅れても加入は可能
「健康保険の切り替え手続きの期限は退職後14日以内」とお伝えしましたが、遅れても加入は可能です。
退職後すぐに手続きができなかった場合でも、加入日を退職日や社会保険喪失日まで遡って認められるケースがあるためです。
ただし、手続きが遅れると保険料の支払いを一括で求められる場合があるため、できるだけ早く市区町村役場で申請をおこないましょう。
必要書類の準備
健康保険へ切り替えるためにも、必要書類を準備しておきましょう。
本人確認書類や離職票などが必要であり、書類によっては市区町村の役所でないと受け取れない場合があります。
すべての書類を揃えるのに数日かかる可能性もあるため、できるだけ余裕を持って準備しましょう。
加入する保険を選択
健康保険への切り替え時は、複数の保険から選択できます。
一般的な健康保険が国民健康保険であり、会社員などが退職した際に個人が加入できる保険です。
任意継続とは、前職の健康保険を最長2年間、自己負担で継続する方法です。国民健康保険は社会保険よりも高額になるケースが多いため、前職まで加入していた保険を一時的に継続したい人に向いています。
家族の被扶養者とは、夫婦どちらかの保険に扶養として加入する方法です。被扶養者となれば保険料の支払いが免除されます。
ただし、被扶養者になるには、いくつかの条件を満たさなければなりません。詳しくは、「全国健康保険協会」の公式サイトをご覧ください。
退職後すぐに再就職する場合は切り替え不要
健康保険の切り替えについて、退職後すぐに再就職する場合は切り替え不要です。
退職すると健康保険の資格がなくなりますが、再就職までに期間が空かない場合は新しい職場の健康保険に加入します。そのため、国民健康保険へ切り替える必要はありません。
ただし、期間が空いてしまい、その間に病気や怪我をした場合は治療費が全額自己負担になるので気を付けましょう。
STEP2:国民年金への加入手続き
次に国民年金への加入手続きをおこないましょう。健康保険と同様に手続きや必要書類を解説します。
- 手続きのタイミングと期限
- 必要書類の準備
- 市区町村役所の年金窓口で手続き
- 退職後すぐに再就職する場合は加入不要
手続きのタイミングと期限
国民年金への加入は、健康保険と同様に原則退職から14日以内です。
手続きが遅れると保険料の納付が遅延し、年金受給額に影響が出る可能性があるため、早めの対応が重要です。
なお、経済的な理由で保険料の支払いが難しい場合、支払いを一時的に猶予する制度もあるので一度役所の窓口で相談してみましょう。
必要書類の準備
国民年金へ加入するために必要書類を準備しておきましょう。
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 退職証明書または離職票
- 本人確認書類
退職証明書や離職票は前の会社から受け取る書類のため、保管されているかどうか確認しておきましょう。
もし手元にない場合は前の会社へ問い合わせる必要があります。
これらの書類を揃えたら市区町村の役所で手続きできます。
市区町村役所の年金窓口で手続き
書類を準備できたら市区町村役所の年金窓口で手続きします。
手続きが完了したら後日「国民年金加入のお知らせ」や保険料の納付書が日本年金機構から送られてくるので、納付期限までに支払いましょう。
なお、納付書払い以外にも銀行引き落としでの支払いも可能です。状況に合わせて支払い方法を選択しましょう。
退職後すぐに再就職する場合は加入不要
国民年金の加入手順を解説しましたが、退職後すぐに再就職する場合は国民年金への加入は不要です。すぐに再就職する場合は次の職場で厚生年金に加入するからです。
厚生年金とは、企業に雇用されている労働者が加入する公的年金で、会社が手続きをおこないます。そのため、退職から新しい職場に入るまでの期間が1日でも空いていなければ、わざわざ国民年金に加入する必要はありません。
ただし、退職後に少しでも空白期間がある場合や自営業を始める場合は、国民年金への加入手続きが必要です。
STEP3:失業保険の手続き
健康保険と国民年金の加入手続きが完了したら、失業保険の手続きをおこないます。申請方法や申請場所などが異なるので確認しておきましょう。
- 離職票の受け取り
- ハローワークで申請
- 失業保険受給説明会への参加
- 失業認定日に求職活動の報告
- 失業保険の受給
離職票の受け取り
まずは失業保険を申請するために、前の会社から離職票を受け取りましょう。
離職票は、退職時期や退職理由などが記載されている書類で、基本的に退職後に自宅に送られてきます。
離職票がないと失業保険の申請ができないため、必ず用意しましょう。もし、手元にない場合は前の会社へ問い合わせる必要があります。
ハローワークで申請
離職票を準備できたらハローワークで失業保険の申請をします。
窓口で失業保険申請の旨を伝えれば担当者が手続きの方法や流れを教えてくれます。
なお、申請の際は離職票以外にも、「本人確認書類」「雇用保険被保険者証」などの書類も必要です。事前に準備しておきましょう。
失業保険受給説明会への参加
申請が完了したら、失業保険受給説明会へ参加します。
この説明会では、失業保険の仕組みや受給条件などが詳しく説明されます。
また、不正受給などのルールも説明されるため、正しく受給するためにもしっかりと聞いておきましょう。
失業認定日に求職活動の報告
失業保険受給説明会に参加した後は、失業認定を受けます。
失業認定とは、失業保険を受け取るためにハローワークで定期的に「就職活動をおこなっている」ことを確認してもらう手続きです。
失業認定を受けるためには、ハローワーク指定の「失業認定日」に求職活動の報告をしなければなりません。
例えば、応募履歴や面接履歴、応募先の企業名などを報告します。これらの報告をもとに「本当に働く意志があるのか」を判断します。
失業認定を受けられれば失業保険を受給できるため、これまでおこなった求職活動を具体的に報告しましょう。
なお、嘘の報告をして失業保険を受給した場合は不正受給となり、重いペナルティが課される恐れがあります。
失業保険の受給
失業認定を受けたら失業保険を受給できます。
ただし、すぐに受給できるわけではなく、7日間の待機期間や1~2ヵ月の給付制限期間を経て受給できます。
受給までの具体的な期間については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
関連記事:失業保険を受け取る流れをわかりやすく解説!計算方法や期間についても紹介
失業保険でお困りの方は『失業保険サポート』を利用しよう
失業保険の申請手順について解説しましたが、「一人で申請できるかな」「申請するのが面倒」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
そんな方におすすめなのが「失業保険サポート」です。

失業保険サポートとは、失業保険の申請や仕組みについて、専門のコンシェルジュへ相談できるサービスです。
「失業保険の申請を手伝ってほしい!」「給付金を多くもらうコツを教えて!」などの要望にも応えてくれます。
実際、これまで3,000件以上の相談を解決してきているため、実績や信頼性も抜群です。失業保険のスペシャリストが親切丁寧にアドバイスしてくれるので、失業保険の受給が初めての方でも安心して相談できます。
失業保険の受給に疑問や不安を抱いている方はぜひこの機会に相談してみましょう。
公式サイト:https://shitsugyouhoken-support.com/
STEP4:住民税や所得税の納付
失業保険の申請が完了したら、住民税や所得税の納付をしましょう。それぞれの税の意味や支払い方法を解説します。
- 住民税・所得税の納付に関するポイント
- 退職時期による納付方法の違い
- 納付方法の選択
- すぐに再就職する場合
- 退職時の年末調整
- 確定申告が必要なケース
住民税・所得税の納付に関するポイント
まずは、住民税と所得税の納付に関するポイントを解説します。
それぞれどのような税金で、なぜ支払う必要があるのか理解しましょう。
住民税
住民税は、前年の所得に基づいて自治体が計算し、翌年の6月から翌年5月までの1年間を通じて支払う税金です。
支払い方法は、給与天引き(特別徴収)、自分で納付書を使って支払う(普通徴収)などがあります。
会社員時代は給与天引きされていましたが、退職すると自分で支払わなければならないため、納付書払いになるのが一般的です。
所得税
所得税は、その年の収入に対してかかる税金です。
住民税と同様に、会社員時代であれば給与天引きされていましたが、退職すると自分で支払わなければなりません。
また、所得税は確定申告によって総支払額が決まるため、自分で確定申告する必要があります。
具体的には、退職した年の翌年の2月16日~3月15日までに申告しなければならないため、必要書類や手続きの方法を確認しておきましょう。
確定申告の方法は、国税庁「確定申告特集」で紹介されているので参考にしてみてください。
退職時期による納付方法の違い
住民税と所得税は退職時期により納付方法が異なります。
1月〜5月に退職した場合、未払いの住民税は通常一括で支払います。会社が一括精算し、残りの分を給料から差し引いて納付します。
6月〜12月に退職した場合、その年の住民税は分割払いが可能です。次の勤務先で引き継ぐか個人で支払います。
一方で所得税は、退職時に年末調整がおこなわれない場合に限り確定申告が必要になる場合があります。このように、退職時期によってそれぞれの税金の納付方法が異なります。
納付方法の選択
住民税と所得税は、それぞれ以下の納付方法から選択できます。
一括納付は、残りの税額を一括で支払う方法です。一度に多くのお金が必要になりますが、毎月支払う手間が省けるのがメリットです。
対して分割納付は、納付書を使って毎月分割して納付する方法です。急にお金を準備できない方に向いている方法であり、毎月定期的に支払います。
特別徴収は、再就職先が決まっている場合に、次の会社で給与天引きしてもらう方法です。すぐに再就職できる人に限り利用できる方法です。
このように、税金の支払い方にはいくつかの方法があるため、自分の経済状況を考慮したうえで選びましょう。
すぐに再就職する場合
退職後すぐに再就職する場合、住民税や所得税の納付方法やタイミングに注意しましょう。
退職時に未納分があれば、会社が最終給与から天引きして一括で精算するケースがありますが、再就職先での給与と合算される場合があり、混乱しやすいからです。
住民税に関して、すぐに再就職する場合は住民税の納付が新しい会社に引き継がれるか確認しましょう。退職した月までの分は前の会社が負担し、残りの分は新しい会社が給与から天引きされることが一般的です。
所得税に関しては確定申告の有無について気を付けましょう。
例えば、再就職先にて年末調整がおこなわれる場合、退職前後の所得に基づいて過不足分が調整されるので問題ありません。
しかし、年末調整がおこなわれない場合は、翌年に自分で確定申告しなければならないケースがあります。
退職時の年末調整
退職時に年末調整ができるかどうかは退職のタイミング次第です。具体的には、年内の勤務状況によって年末調整の対応が変わります。
6月〜12月に退職した場合、 残りの住民税は自分で納付書を使って分割払いする必要があります。また、退職時に会社から年末調整を受けられない場合は、翌年3月15日までに個別で確定申告をしなければなりません。
年内に再就職する場合は、新しい勤務先で年末調整を受けます。この際、前の会社から受け取る源泉徴収票が必要ですので忘れずに受け取りましょう。
年末調整をおこなった場合の注意点
退職後に年末調整をした場合は、住民税や所得税の納付に注意が必要です。
退職時に年末調整を済ませたとしても、その年の給与や退職金によって税額が変わる場合があります。
特に、年末調整をした後に収入が増えたり減ったりした場合は、住民税や所得税の追加納付や還付が発生するケースもあります。この場合は確定申告する必要があるため、年末調整前後の収入の増減には気を付けましょう。
確定申告が必要なケース
退職後、以下のケースに該当する場合は確定申告が必要です。
- 退職後に収入があった場合
- 年の途中で退職した場合
- 医療費控除や住宅ローン控除を受けたい場合
退職後にアルバイトや副業などで収入を得た場合は、それらの収入に応じて所得税が決まるので確定申告が必要です。
また、年の途中で退職した場合も、その年の給与所得が年末調整されていないため、自分で確定申告して納税や還付を受けなければなりません。
ほかにも、医療費や住宅ローン控除を受ける際にも確定申告が求められます。
このように、収入に関わらず確定申告が必要になるケースがあるため、退職する前に確認しておきましょう。
詳しくは、国税庁「確定申告が必要な方」を参考にしてみてください。
退職したらやることの順番に関するよくある質問
退職したらやることの順番に関するよくある質問をご紹介します。
退職後の手続きに関する疑問や不安を参考にしてみましょう。
- 退職後はハローワークと市役所のどちらに行くべきですか?
- 手続きが退職後14日過ぎたらどうなる?
- すぐに再就職する場合でも手続きは必要ですか?
退職後はハローワークと市役所のどちらに行くべきですか?
退職後は、まず居住地域の役所へ行き、次にハローワークへ行くのがおすすめです。
退職した後は健康保険や年金の手続きをおこなう必要があります。
そのため、最初に市役所で「国民健康保険」や「国民年金」への切り替え手続きを済ませましょう。
手続きを済ませないと保険証が使えないため、医療費が全額自己負担になる恐れがあります。
次に、ハローワークで失業保険の申請をおこないます。失業保険の申請には「雇用保険被保険者証」や本人確認書類などが必要です。
実際に失業保険を受給できるのは申請から1~2ヵ月前後かかるため、できるだけ早めに行動しましょう。
手続きが退職後14日過ぎたらどうなる?
退職後14日以内に手続きをしないと、不利益を受ける可能性があります。
退職後の国民年金や国民健康保険などの切り替えは、退職後14日以内におこなわなければなりません。
しかし、期間内に切り替えないと未加入期間が発生し、医療費が全額自己負担になってしまう場合があります。
また、年金手続きが遅れると支払いのタイミングが遅れ、将来の年金額に影響が出る可能性もあります。
さらに、失業保険の申請が遅れると受け取れる金額や期間に影響することもあるため、退職したらまず必要な手続きを整理し、早めに行動することが大切です。
すぐに再就職する場合でも手続きは必要ですか?
再就職が決まっていても退職後の手続きは必要です。
特に、国民健康保険や国民年金への切り替えは必ずおこないましょう。これらは前の会社で「社会保険」「厚生年金」として加入していても退職と同時に失効するため、次の職場に入るまでの間に切り替える必要があります。
切り替えない場合、万が一病院にかかったときに全額自己負担となったり、年金が未納扱いになったりします。
このような理由から、すぐに再就職する場合でも手続きをしておきましょう。
まとめ
退職したらやることについて詳しく解説しました。
退職後は、健康保険の切り替えや国民年金への加入手続きが必要であり、退職後14日以内におこなうのが一般的です。
もし遅れてしまうと、医療費が全額自己負担になったり将来受け取れる年金額に影響したりするかもしれません。
また、退職後すぐに働かない場合は失業保険の申請も必要であり、書類の準備や申請手順の理解など、やることが数多くあります。
さらに、住民税や所得税の支払いも怠ってはならないため、自分の状況に合わせて支払う必要があります。
退職後は非常にやることが多いため「退職したけどこれからどうすればいいんだろう?」とお困りの方も多いでしょう。そんな方はぜひ、この記事を参考に手続きを進めてみましょう。
会社辞めたらお金もらえるって知ってる?

『失業保険サポート』では、退職後にもらえる給付金を受け取るサポートをしてもらえます。
実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。
| 平均月収 |
月間でもらえる金額 |
| 月収30万円 |
約20万円 |
| 月収40万円 |
約26万円 |
| 月収50万円 |
約33万円 |
| 月収60万円 |
約40万円 |
| 月収70万円 |
約46万円 |
| 月収80万円 |
約53万円 |
| 月収90万円 |
約60万円 |
| 月収100万円 |
約66万円 |
会社を辞めて給付金を申請するだけでこんなにもお金がもらえます。
ですが、「ほんとに仕事辞めたらこんなにお金もらえるの?」「さすがに退職してからお金もらえるわけなくない?」と疑問に思いますよね。
そんなあなたに向けて『失業保険サポート』では給付金について詳しく分かる無料Web個別相談を実施しています。
「会社を辞めたいけどお金が...」とお困りのあなた!
この機会に無料で給付金について知れる個別相談を一度試してみませんか。
公式サイト:https://roudou-pro.com/links/syakaihoken_sokyu/
今の仕事をやめたいけど、
次の一歩が不安なあなたへ |
|
多くの人が、退職前に次の職場を決めることで、経済的にも精神的にも安心して新しいスタートを切っています。
次こそは・・・
・人間関係が良好な職場で働きたい
・頑張りを政党に評価してくれる職場で働きたい
・残業や休日出社のないホワイトな職場で働きたい
今のような仕事の悩みを二度と抱えたくない!
このような思いの方は、転職エージェントに無料相談して、あなたにピッタリの求人を提案してもらうのがおすすめです。
有益なアドバイスがもらえるだけではなく、履歴書作成から面接対策まで転職活動を完全無料でサポート。ストレスフリーな環境からの再スタートを目指せます。
|