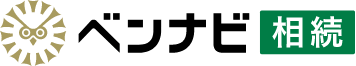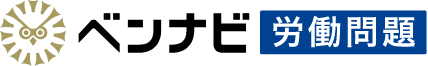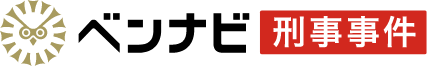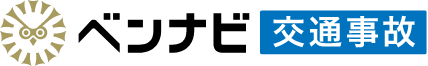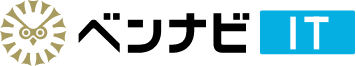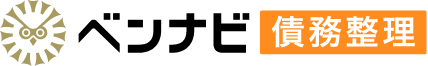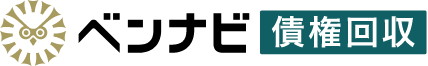会社とのトラブル・男女トラブル・相続問題・借金問題など、身の回りでトラブルが起きた場合に弁護士への無料法律相談を検討する方は多いでしょう。
しかし、日ごろ法律と触れ合う機会が少なく、「弁護士とどのように接すればよいのか?」「どこの弁護士に法律相談すればよいのか?」などと思っている方も多いでしょう。
弁護士によって得意分野や人柄などは大きく異なり、自分にとって納得のいく形で問題解決するためにも弁護士選びは大切です。
本記事では、弁護士に無料相談できる窓口や、相談方法ごとの特徴や相談前に準備すべきことなどを解説します。
今すぐ弁護士に無料相談したいあなたへ
「今すぐ弁護士に無料相談したいけど、弁護士の探し方がわからない…」と悩んでいませんか。
今すぐ相談できる弁護士をお探しなら「ベンナビ」がおすすめです。
ベンナビでは、以下のような条件に当てはまる弁護士を多数掲載しています。
- 初回無料相談可能な弁護士
- 電話相談・オンライン相談可能な弁護士
- 休日の相談可能な弁護士
- 各分野の法律問題を得意とする弁護士
法律問題を解決するためには、問題が大きくなる前に早めに相談をすることが大切です。
ベンナビでは、相談内容別にそれぞれの分野を得意とする弁護士を地域別で検索できます。
お近くの弁護士にお気軽に相談してください。
弁護士に電話で無料法律相談ができるおすすめの窓口
弁護士に電話で無料法律相談できる窓口としては、主に以下の4つがあります。
- ベンナビ
- 法テラス
- 市役所や区役所などの無料法律相談
- 弁護士会の法律相談センター
ここでは、それぞれの窓口について解説します。
ベンナビ|分野ごとに専門性の高い弁護士を選べるポータルサイト
「夜間や土日祝日でないと相談できない」「自分で弁護士を選びたい」という方は、インターネットで弁護士を探しましょう。
ベンナビとは、当社が運営する弁護士ポータルサイトで、以下のように分野ごとにサイトがあります。
ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)|残業代請求・不当解雇などの相談

「残業代が支払われない」「突然解雇されてしまった」など、労働にまつわる問題に関しては、労働問題を得意とする弁護士へ相談しましょう。
弁護士であれば、残業代請求・不当解雇の撤回・慰謝料請求などの対応を依頼できます。
ベンナビ労働問題では、パワハラ・セクハラ・不当解雇・未払い給与の請求など、労働問題を得意とする弁護士を掲載しています。
無料相談はもちろん、電話・メール・LINEなど、さまざまな方法で相談でき、まずは利用してみましょう。
【公式サイト】https://roudou-pro.com/
休日/夜間対応可能の弁護士・事務所も多数掲載!
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)|離婚・男女問題の相談

「配偶者が別れてくれない」「浮気されたので慰謝料を請求したい」など、離婚に関する悩みを抱えている方は、離婚問題を得意とする弁護士へ相談しましょう。
弁護士に相談・依頼することで、適切な形で離婚を成立させたり、慰謝料・養育費・財産分与などのトラブルも法律知識を用いて取り決めたりすることができます。
ベンナビ離婚では、離婚問題が得意な弁護士を掲載しているので利用してみましょう。
【公式サイト】https://ricon-pro.com/
ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)|示談交渉・損害賠償の相談

交通事故は突然起きてしまいます。
「保険会社から提示された示談金に不満がある」「加害者とどのようにやり取りすればよいのか?」など、交通事故にまつわる悩みは交通事故を得意とする弁護士に相談しましょう。
交通事故の損害賠償金については、弁護士が介入することで大幅に増額することもあります。
一人で悩まずに、まずは弁護士に相談しましょう。
【公式サイト】https://jico-pro.com/
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)|遺産分割・遺留分などの相談

家族同士であっても、お金が絡むと大きなトラブルに発展することもあります。
「もっと遺産を多くもらいたい」「ほかの相続人と遺産の取り分で揉めている」など、相続に関する悩みは相続を得意とする弁護士に相談しましょう。
弁護士が間に入ることで冷静かつ論理的に話し合いが進み、法律に則った適切な相続が望めます。
【公式サイト】https://souzoku-pro.info/
ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)|逮捕された加害者向けの相談

身内が逮捕されてしまった」「逮捕されたあとはどうなるのか?」など、刑事事件を起こして身内や自身が逮捕された場合は、刑事事件を得意とする弁護士に相談しましょう。
弁護士が刑事弁護をおこなうことによって、早期釈放や不起訴処分の獲得などが望めます。
【公式サイト】https://keiji-pro.com/
ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)|過払い金・任意整理などの相談

「借金が多すぎてどうしようもない」「過去の過払い金を請求したい」という方は、債務整理を得意とする弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば、自己破産や個人再生などの裁判所を通した手続きも一任でき、迅速かつ大幅に借金を減額できる可能性があります。
また、過払い金を請求する場合も、弁護士は代理人として交渉してくれて心強い味方になります。
【公式サイト】https://saimuseiri-pro.com/
ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)|売掛金・給料未払いなどの相談

「貸したお金が返ってこない」「詐欺でだまし取られたお金を返してほしい」「離婚時に取り決めた養育費や慰謝料が支払われない」などの債権回収について悩んでいる場合は、債権回収を得意とする弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談・依頼することで、相手にプレッシャーをかけられるだけでなく、法的手段で請求することもできます。
まずは弁護士に相談して、早期解決を目指しましょう。
【公式サイト】https://saiken-pro.com/
ベンナビIT(旧:IT弁護士ナビ)|ネット誹謗中傷・リベンジポルノなどの相談

「ネット上の誹謗中傷で悩んでいる」「SNSで住所や名前を勝手に公開された」「名誉毀損になるのかどうか判断してほしい」という方は、インターネットトラブルが得意な弁護士に相談しましょう。
インターネット問題は、弁護士によって得意・不得意が分かれる分野であり、インターネット問題に詳しくない弁護士では適切な対応を取れない可能性があります。
ベンナビITでは、インターネットトラブルが得意な弁護士を掲載しています。
弁護士であれば、投稿の削除・投稿者の特定・損害賠償請求などの対応を一任でき、まずは相談してみましょう。
【公式サイト】https://itbengo-pro.com/
企業法務弁護士ナビ|労務問題・M&Aなどの相談

労務トラブル・事業再生・債権回収・契約書作成・クレーム対応などの悩みや疑問がある場合は、企業法務が得意な弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談・依頼すれば、リーガルチェックを受けることでトラブルを未然に防ぐことができたり、法改正や会社規模を意識して就業規則を改正できたりするなど、状況に応じた的確なアドバイスやサポートが望めます。
電話相談可能・当日相談可能などの事務所も多くあり、まずは相談してみましょう。
【公式サイト】https://houmu-pro.com/
市役所や区役所の無料法律相談|軽い相談をしたい方に
身近な法律相談窓口のひとつとして、市役所や区役所などで定期的におこなわれる無料法律相談があります。
完全予約制で相談時間は30分程度であり、主に日常生活で起きる問題について相談できます。
法律に関する基本的なことを聞きたい方や、手続き上の疑問を解消したい方などにはおすすめの窓口です。
ただし、相談した弁護士にそのまま問題解決を依頼することはできないため、緊急性の高い問題を抱えている方などには不向きです。
相談日時
水曜日・木曜日(祝日等除く) 午後1時から午後3時30分まで [1]午後1時~ [2]午後1時30分~ [3]午後2時~ [4]午後2時30分~ [5]午後3時~ *お一人30分以内の相談になります。
引用元:新宿区|無料法律相談・交通事故相談
無料法律相談の受付時間などは地域によって異なるため、詳しくは各役所のホームページを確認しましょう。
弁護士会の法律相談センター|15分の無料相談・弁護士を紹介してほしい方に
各都道府県に設置されている弁護士会が運営する「法律相談センター」でも、弁護士と相談できます。
東京都に住んでいる方であれば、15分程度の電話無料相談が利用でき、電話番号や受付時間などの詳細は「弁護士会 電話無料相談」を確認してください。
そのほかの地域ではそれぞれ対応状況が異なり、各弁護士会の情報は「全国の弁護士会の法律相談センター」で確認できます。
電話やインターネットなどで法律相談を予約したい方は「ひまわり相談ネット」を利用しましょう。
なお、相談料は無料のところもありますが、なかには30分5,000円程度の相談料が発生するところもあるため注意してください。
法律相談センターでは、弁護士の紹介を受けられるほか、相談した弁護士に問題解決を依頼することもできます。
法テラス|そのほかの悩みごと全般
法テラスでは、民事法律扶助制度の一環として、弁護士との無料法律相談を実施しています。
ただし、弁護士との無料法律相談を利用するには、収入や資産などについて一定の条件を満たす必要があり、詳しくは「民事法律扶助業務」を確認しましょう。
なお、法テラスでは、弁護士との無料法律相談のほかに、弁護士費用の一時立て替えなども実施しています。
弁護士費用を立て替えてもらう場合も一定の条件を満たす必要がありますが、費用面が不安な方は条件を満たしているかどうか確認してみましょう。
【注意!】弁護士以外が法律相談を受けることは違法
SNSなどでは、弁護士かどうかわからない人が法律相談を受け付けているケースもありますが、弁護士以外の人が報酬目的で法律相談を受けることは法律で禁止されています。
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
引用元:弁護士法第72条
素性のよくわからない人に相談してしまうと、高額な相談料を請求されたり、誤った知識を教え込まれたりするリスクがあります。
もし相談相手に不信感を抱いた場合は、日本弁護士連合会のホームページで弁護士名を検索しましょう。
弁護士になると必ず日本弁護士連合会に登録されるため、もし検索しても名前が出てこない場合は弁護士資格を持っていない可能性があります。
弁護士法第72条に違反した場合は「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されます。
弁護士との無料法律相談を利用するメリット
弁護士との無料法律相談を利用した場合、以下のようなメリットがあります。
法的に的確なアドバイスをもらえる
ちょっとした質問やトラブルであれば、Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトで解決することもあります。
しかし、深刻なトラブルの相談や明確な解決方法を求めている法律相談の場合、そのようなサイトでの素性の知れない人の回答を鵜呑みにするのは危険です。
単にインターネットから拾ってきた情報ということもあれば、そもそも出まかせを言っている可能性もあります。
特に法律問題では、ケースによって解決方法や適切な対処法が異なることもあります。
弁護士であれば、法的視点から具体的かつ明確なアドバイスが望めます。
弁護士が必要となればそのまま依頼できる
トラブルの状況によっては、弁護士に依頼しないと問題解決が難しい場合もあります。
たとえば、慰謝料問題に発展しそうな場合や、当事者同士で感情的になって話が進まない場合などは、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼するかどうか迷っている場合も、まずは相談してみましょう。
とりあえず相談して現在の状況を伝えておくことで、のちのち問題解決を依頼する場合、弁護士がスムーズに状況把握して動くことができます。
弁護士との無料法律相談の方法と特徴
ここでは、代表的な無料相談の方法について解説します。
対面での無料相談
相談者が弁護士事務所に行って、弁護士に直接相談するという方法です。
対面形式で相談する場合、メリットとデメリットは以下のとおりです。
メリット1:弁護士の人柄がよくわかる
弁護士と直接やり取りするため、どのような人柄かよくわかるというのが大きなメリットです。
特に、弁護士に依頼することを検討している方は、信頼できる弁護士かどうか判断するためにも対面形式での相談がおすすめです。
メリット2:その場で新たな質問ができる
直接弁護士と会話するため、アドバイスを受けていて新たな疑問が出てきたら、その場で聞くこともできます。
デメリット1:スケジュール調整の必要がある
弁護士と面談する場合、お互いのスケジュールを調整しなくてはなりません。
仕事や家事などで忙しい場合、なかなか都合が合わないこともあります。
デメリット2:移動の手間がかかる
弁護士事務所に行かなければならず、移動の手間がかかるというのもデメリットです。
デメリット3:時間制限がある
通常、相談時間は30分~1時間程度と限られています。
相談時間を無駄にしないためにも、あらかじめ相談内容を簡潔にまとめておきましょう。
電話での無料相談
現在では、電話で無料相談できる弁護士事務所も多くあります。
電話で相談する場合、メリットとデメリットは以下のとおりです。
メリット①:手軽に相談できる
直接弁護士事務所に行かなければならない面談と比べると、電話相談は手軽な相談方法です。
弁護士の表情や雰囲気などは判断しにくいものの、問題解決のための有益なアドバイスが望めます。
メリット②:その場で新たな質問ができる
面談と同様に、相談途中で新たな疑問が出てきたら、その場で聞くことができます。
メリット③:弁護士の人柄がある程度わかる
面談ほどではありませんが、電話相談でも弁護士の人柄をある程度知ることができます。
弁護士に問題解決してもらう場合は弁護士との相性の良さなども重要になるため、人柄を知ることは大切です。
デメリット①:時間制限がある
面談と同様に、電話相談でも制限時間があります。
決められた時間内で状況を伝えて聞きたいことを聞けるように、あらかじめ相談内容をまとめておきましょう。
デメリット②:自分で記録に残す必要がある
せっかく弁護士から有益なアドバイスをもらっても、相談後に内容を忘れてしまっては水の泡になります。
電話相談する際はメモを取ることをおすすめします。
メールでの無料相談
電話相談よりも手軽な相談方法としてメールがあります。
メールで相談する場合、メリットとデメリットは以下のとおりです。
メリット①:手軽に相談できる
スマートフォンやパソコン一つで簡単に相談できることは大きなメリットです。
メリット②:時間を気にせず相談できる
メール相談の場合、多くの法律事務所では24時間相談を受け付けています。
電話相談や面談のように、時間を気にしなくてよいというのも大きなメリットです。
ちょっとした空き時間を使って相談でき、日々忙しい方には特におすすめの相談方法です。
メリット③:弁護士とのやり取りを形に残せる
面談や電話相談では弁護士とのやり取りが形に残りませんが、メール相談であれば残ります。
法律相談では聞き慣れない難しい言葉が出てくることがありますが、弁護士からのメールを見返して自分で調べることもできます。
デメリット①:その場で解決しないこともある
メール相談では相談状況を正確に把握するのが難しく、結局弁護士から「電話相談か面談でお願いします」と言われることもあります。
特に相談状況が複雑な場合は、メールでは相談内容をうまくまとめられずに何を相談したいのか伝わらない可能性もあります。
複雑な法律問題について相談したい場合は、電話や対面での相談を検討しましょう。
デメリット②:何度もやり取りできない
いくら手軽でも、友達とLINEをするように何度もやり取りすることはできません。
相談状況や相談内容などは簡潔にまとめて、アドバイスを受けるようにしましょう。
デメリット③:回答をもらうまでに時間がかかる
電話相談などに比べると、メール相談では回答をもらうまでに時間がかかります。
メール相談の場合、翌日や翌々日に返信が来ることもあります。
したがって、交通事故や刑事事件などの緊急性の高い場合は、ほかの相談方法を選択しましょう。
インターネットでの無料相談
インターネット上には、Q&A形式などで弁護士が質問に回答してくれるサイトなどもあります。
インターネットを利用して相談する場合、メリットとデメリットは以下のとおりです。
メリット①:手軽に相談できる
メール相談と同様に、スマートフォンやパソコンがあれば手軽に相談できるというのは大きなメリットです。
メリット②:ちょっとした質問に適している
なかには「こんなこと弁護士に質問しても大丈夫だろうか」と思っている方もいるでしょう。
そのような場合にも、インターネットであれば気軽に相談できておすすめです。
「自分では大したことないトラブルだと思っていたが、実は慰謝料を請求できる状況だった」という可能性もあります。
デメリット①:具体的な問題解決には向かない
Q&A形式で弁護士に回答してもらえるサイトの場合、ほかの利用者も質問内容を見ることができてしまい、あまり細かい状況を説明できずに的確なアドバイスがもらえないということもあります。
デメリット②:回答をもらうまでに時間がかかる
メール相談と同様に回答をもらうまでに時間がかかり、いつまで経っても回答してもらえない場合もあります。
弁護士との無料法律相談の前に準備しておきたいこと
ここでは、弁護士との法律相談を有効活用するための準備について解説します。
現状をまとめておく
無料法律相談では時間制限があり、何回も利用できるものではありません。
相談前には、以下の内容をメモに書き出して現状を整理しておきましょう。
- 誰が抱えている問題で、トラブルの相手は誰か
- どのような問題か
- 今はどのような状況か
- 最終的にどのような形での解決を望むのか
- 証拠になりそうなものはあるか
どうしてほしいのかをある程度決めておく
無料法律相談の利用目的や、自分がどのような結果を望むのかを明確にしておくことも大切です。
トラブルの内容によっては、アドバイスをもらえば自力で解決できるケースもありますが、弁護士のサポートが必要なケースもあります。
また、問題の解決方法も一つではありません。
たとえば、一口に残業代請求といっても、会社と話し合う・労働基準監督署へ報告する・訴訟を起こすなどの解決方法があります。
弁護士に相談する際は、以下のような自分の希望も伝えましょう。
- なるべく早く問題解決したい
- できるだけ多くの賠償金を受け取りたい
- トラブルの相手がどうしても許せない など
証拠を集めておくと有利
相談内容に関する証拠があれば、より具体的なアドバイスをもらえる可能性が高まります。
たとえば、残業代請求について相談する場合はタイムカードが証拠として有効で、証拠をもとに「いくら獲得できそうか」などのアドバイスが望めます。
事前知識を身に付けておく
法律相談では難しい専門用語が出てくることもあります。
緊急性の高い問題でなければ、事前に専門用語などを調べてから相談するのもよいでしょう。
事前に調べておけば、弁護士が言っていることをスムーズに理解できて、十分なコミュニケーションを取ることができます。
さいごに|弁護士への無料法律相談ならベンナビがおすすめ
法律問題に巻き込まれた際は、相談したい内容の分野に注力している弁護士に相談しましょう。
ベンナビであれば相談内容や地域ごとに弁護士を一括検索でき、「電話相談可能」「初回相談無料」などの事務所も多く掲載しています。
法律相談を利用したからといって契約を迫られることはないため、弁護士に依頼するかどうか迷っている方も、まずは相談してみることをおすすめします。