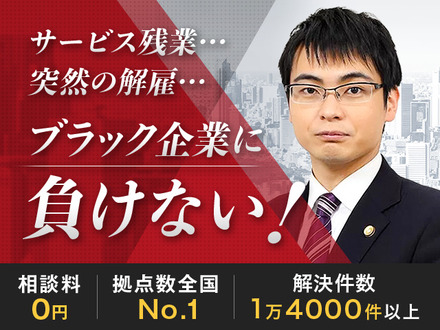安全配慮義務違反とは?主なケースや会社を訴える場合に必要な知識、判例も解説


- 「長時間残業が常態化しているが、安全配慮義務違反に該当しないのか」
- 「会社を安全配慮義務違反で訴えるのはどうすればいいのか」
長時間勤務を強いられたり、セクハラやパワハラを受けたりと、安全で健康に働けない状況にあるのであれば、安全配慮義務違反として会社の責任を問える可能性があります。
しかし、法的な知識がないなかで、労働者が今後とるべき行動を適切に判断することは簡単ではありません。
そこで本記事では、安全配慮義務違反に該当する主なケースや、会社を訴える場合に必要な知識を解説します。
実際の判例も交えてわかりやすくまとめているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。
安全配慮義務違反とは? | 労働者が安全で健康に働けるよう配慮すべき義務の違反
安全配慮義務違反とは、会社が労働者の安全と健康を守るための義務に違反している状態のことです。
労働契約法や労働安全衛生法では、労働者が安心して働けるよう、環境整備や健康への配慮に取り組むことを会社側の義務として定めています。
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
例えば、長時間労働を放置して労働者に健康被害が生じたり、安全面への配慮に欠けた結果事故が発生したりしたケースなどでは、安全配慮義務違反となる可能性が高いと考えられます。
安全配慮義務の対象となる労働者の範囲
安全配慮義務の対象となる労働者の範囲は、以下のとおりです。
| 対象 | 備考 |
|---|---|
| 雇用関係にある労働者 | 雇用形態や勤務形態を問わず、雇用契約を結ぶ全ての労働者が対象になる |
| 派遣労働者 | 派遣先事業者・派遣元事業者ともに安全配慮義務を負う |
| 下請先が雇用する労働者 | 元請業者と下請労働者との間に特別な社会的接触が関係ある場合に限る (下請労働者が元請業者から指揮監督を受けていた場合や、元請業者が管理する設備を使用していた場合など) |
過去の判例からしても、安全配慮義務の対象者となる労働者の範囲は広く捉えられているのが実情です。
とはいえ、実態に即した判断が必要になるので、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
安全配慮義務に違反した場合の罰則は?
安全配慮義務に違反した場合は、労働安全衛生法違反により罰則が科されます。
例えば、危険防止義務を怠った場合は「6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金」、雇入れ時に安全衛生教育を実施しなかった場合は「50万円以下の罰金」です。
また、会社が安全配慮義務を怠った結果、労働者に損害が生じた場合は、民事上の損害賠償責任も負わなければなりません。
安全配慮義務が問われる主なケース
次に、会社側の安全配慮義務が問われる主なケースを解説します。
パワハラ・セクハラ・カスハラなどのハラスメント
パワハラ・セクハラ・カスハラなどのハラスメントは、安全配慮義務違反として会社の責任を問われやすい問題です。
実際、ハラスメント行為により、労働者が精神的・身体的な負担を感じ、健康被害を引き起こすケースは少なくありません。
その際、会社が適切な対応を怠った場合は安全配慮義務違反となる可能性があります。
長時間労働・過重労働
長時間労働・過重労働も、安全配慮義務違反として会社の責任が問われやすいケースのひとつです。
会社には、長時間労働・過重労働による健康被害から労働者を守る義務があります。
そのため、会社が勤務管理や健康管理を怠り、深刻な疾患や突然死などを引き起こした場合は、会社側に責任が生じることになるでしょう。
なお、長時間労働や過重労働が常態化しているような状況であれば、労働基準法による上限規制に違反している可能性も考えられます。
労災事故
会社が安全配慮義務を問われるケースのひとつとして、労災事故が挙げられます。
労災事故とは、業務中や通勤中に労働者が負傷・疾病・死亡する事故のことです。
労災事故の原因が会社側の安全対策不足や危険防止措置の不備にあった場合などは、安全配慮義務違反として会社が責任を追及される可能性があります。
もちろん、全ての労災事故が安全配慮義務と結びつくわけではないので、個別の判断が必要になる点には注意してください。
メンタルヘルス不調(うつ病、適応障害など)
メンタルヘルス不調も、安全配慮義務が問われやすい問題のひとつです。
メンタルヘルス不調は、長時間労働や職場の人間関係などが原因になっているケースが多くみられます。
そして、会社が労働者への健康被害を予見しながら適切な対応を怠っていたのであれば、安全配慮義務違反とされる可能性が高いでしょう。
なお、会社側は労働者のメンタルヘルスに配慮する義務を常時負っているので、労働者側から事前に申告していなかったとしても、会社の責任を問うことが可能です。
安全配慮義務違反といえるかの判断基準となる3つのポイント
次に、安全配慮義務違反といえるかの判断基準となる以下3つのポイントを解説します。
- 予見可能性
- 結果回避可能性
- 因果関係
自身が置かれている状況と照らし合わせながら、読み進めてみてください。
予見可能性| 労働者の安全に問題があることを予測できたか
安全配慮義務違反が成立するかどうかの判断基準として「予見可能性」が挙げられます。
予見可能性とは、会社が労働者の安全に問題があることを予測できた可能性のことです。
会社は労働者の安全確保に配慮する義務を課せられており、危害発生を予測できた場合には対策を講じる必要があります。
そのなかで、適切な対応をとらず、労働者に健康被害などが生じた場合は、安全配慮義務違反になる可能性が出てくるわけです。
例えば、長時間労働による過労死が発生したケースにおいて、月100時間以上の残業が続く状況があったのであれば、予見可能性が認められて会社側に責任が生じることになるでしょう。
なお、予見可能性があっても、回避措置を尽くしていた場合などは会社の責任が軽減されることもあります。
結果回避可能性 | 労働者に及ぶ危険を回避するための対策・対応をしていたか
安全配慮義務違反が成立するかどうかを判断する際には、「結果回避可能性」の有無も重要なポイントのひとつです。
結果回避可能性とは、会社が労働者に及ぶ危険を回避するための対策・対応を講じていたかどうかを指します。
そして、「結果回避可能性」は「予見可能性」とのセットでとらえるケースが一般的です。
つまり、危険発生が予見される状況で、危険を回避することが可能だったにも関わらず、措置を講じなかった場合に安全配慮義務違反が認められることになるのです。
なお、結果回避可能性の判断にあたっては、実施可能な範囲で最大限の対策をおこなっていたかどうかが重要であり、当時の技術水準や経済合理性も考慮するべきとされています。
たとえ危険を予見できたとしても、安全設備を導入するまでに合理的な期間を要した場合や、予算の都合で対応できなかった場合などは、義務違反が否定される可能性があるでしょう。
因果関係 | 安全配慮義務違反と労働者のけがや病気の間に因果関係があるか
「因果関係」も、安全配慮義務違反が成立するかどうかの重要な判断基準です。
例えば、プライベートでの過度な飲酒が原因で作業中にけがを負った場合、その責任は労働者自身が負うべきであり、会社が安全配慮義務違反に問われる可能性は低いと考えられます。
しかし、因果関係の立証は難しく、会社と労働者の間で争いになるケースも少なくありません。
少しでも判断に迷う場合は、労働問題が得意な弁護士に相談してみることをおすすめします。
安全配慮義務違反で会社を訴えたい!会社に損害賠償を請求できる条件とは?
ここでは、会社に損害賠償を請求できる条件を解説します。
大きく2つのパターンに分けられるので、それぞれ詳しくみていきましょう。
会社が安全配慮義務に違反していた場合
会社が安全配慮義務に違反していた場合は、損害賠償の請求が可能です。
労働契約上、会社には労働者が安全に働ける環境を整備する義務があるので、労働者に危険が及ぶ状況を放置して労働災害を招いた場合は債務不履行にあたります。
そのため、労働者は「債務不履行に基づく損害賠償請求」をおこなうことができるのです。
以下では、損害賠償を請求できるケースを具体的にみていきましょう。
労働者が安全に業務をするための配慮を怠っていた
労働者が安全に業務をするための配慮を怠っていた場合は、債務不履行に基づく損害賠償請求ができます。
例えば、危険をともなう機器の使用にあたって、会社側から十分な操作説明がなされておらず、労働者がけがをしたときには治療費などの請求が可能です。
労働者の健康に対して適切な配慮がされていなかった
労働者の健康に対して適切な配慮がされていなかった場合も、安全配慮義務違反といえるため、会社に損害賠償請求することができます。
例えば、月に100時間を超える残業が常態化しているにも関わらず、負担軽減措置をとらないまま放置し、労働者が身体を壊してしまったケースなどが挙げられるでしょう。
ハラスメントに対して適切な対応をしていなかった
ハラスメントに対して適切な対応をしてもらえず、心身に不調をきたした場合なども、損害賠償請求が可能です。
実際、ハラスメントを訴えても、対応されずに終わってしまうケースは数多く見受けられます。
しかし、労働者をセクハラやパワハラなどから守ることは会社の義務といえるので、対策を講じてもらえなかった場合は、債務不履行に基づく損害賠償請求ができるのです。
使用者責任が認められる場合
会社に使用者責任が認められる場合も、損害賠償請求が可能です。
使用者責任とは、労働者が第三者に対して損害を与えた場合に、会社も連帯して責任を負うことを指します。
例えば、労働者Aの不法行為によって労働者Bがけがをした場合、労働者Bは労働者Aだけでなく、会社に対しても損害賠償を請求できるのです。
なお、使用者責任は不法行為を前提としており、実際の手続きも「不法行為に基づく損害賠償請求」として進めていくことになります。
安全配慮義務違反で会社に損害賠償・慰謝料を求めて訴える場合の流れ
安全配慮義務違反で会社に損害賠償・慰謝料を求めて訴える場合、以下の流れで手続きを進める必要があります。
- 安全配慮義務違反の証拠を集める
- 安全配慮義務違反の被害をまとめた書面を内容証明郵便で会社に送る
- 会社と直接交渉する
- 労働審判を起こす
- 訴訟を起こす
それぞれの手順について、詳しく見ていきましょう。
1.安全配慮義務違反の証拠を集める
会社に損害賠償や慰謝料を求めて訴える場合は、まず安全配慮義務違反の証拠を集める必要があります。
会社の義務違反を立証する責任を負うのは労働者なので、証拠がなければ請求を認めてもらえない可能性が高いからです。
例えば、長時間労働による健康被害を訴える場合は、タイムカード・業務日報・医師の診断書などが重要な証拠となります。
職場でのハラスメントに関しては、メールやチャットの履歴、目撃者の証言などが証拠として有効です。
ただし、不適切な方法で証拠を取得しようとすると、法律に抵触するおそれがあるので注意してください。
証拠の種類や収集方法がわからなければ、弁護士に相談しましょう。
2.安全配慮義務違反の被害をまとめた書面を内容証明郵便で会社に送る
安全配慮義務違反の証拠が揃ったら、被害内容をまとめた書面を内容証明郵便で会社に送付しましょう。
内容証明郵便自体に法的拘束力はありませんが、会社に通知した事実と文書内容が証拠として確実に残ります。
あとで裁判に発展した際には、いつどのような内容で会社に通知したのかが重要になるので、必ず内容証明郵便を使用してください。
また、内容証明郵便で通知することによって本気度が伝わるため、会社としても誠実に対応せざるを得なくなるはずです。
3.会社と直接交渉する
内容証明郵便が届いたことを確認したら、会社との直接交渉に着手しましょう。
損害賠償請求が裁判手続きにまで発展すると双方に大きな負担が生じるので、まずは当事者間での話し合いによる解決を目指すのが一般的です。
しかし、労働者が会社という組織と対等に交渉することは簡単ではありません。
場合によっては言いくるめられてしまったり、脅されたりすることも考えられます。
そのため、会社との直接交渉は弁護士に任せるのが賢明な判断といえるでしょう。
4.労働審判を起こす
会社との直接交渉で解決しない場合は、労働審判を起こすことも検討しましょう。
労働審判は、労働トラブルの解決に特化した裁判手続きです。
通常の裁判よりも費用負担が少なく、話し合いの期日が3回までと決められているため、迅速な問題解決が期待できます。
労働審判では、労働審判委員会の仲介のもと双方が意見を主張し合い、納得できる条件を模索していきます。
調停が成立しない場合は審判へと移行し、労働審判委員会による審判が言い渡されます。
調停成立もしくは審判には法的効力があり、会社が義務を履行しない場合は強制執行を申し立てることも可能です。
5.訴訟を起こす
安全配慮義務違反で会社に損害賠償や慰謝料を求める場合は、訴訟を起こすのもひとつの方法です。
会社と折り合いがつかない状態が続いていても、裁判では必ず結論が出されるので労働者にとって有効な解決手段となるでしょう。
ただし、裁判で争うとなると、証拠の準備や主張の整理などやるべきことがたくさんあります。
ただでさえ心身ともに疲弊している状況のなかで、難易度の高い手続きをこなしていくことは現実的ではありません。
そのため、訴訟に踏み切るのであれば弁護士のサポートが必要不可欠です。
会社の安全配慮義務違反はどこに相談すればいい?
ここでは、会社の安全配慮義務違反によって不利益を受けた場合の相談先として、以下4つを紹介します。
- ベンナビ労働相談
- 労働基準監督署
- 労働局
- 労働条件相談ほっとライン
それぞれ特徴や問い合わせ気を紹介するので、まずは一度相談してみることをおすすめします。
ベンナビ労働相談 | 会社に損害賠償・慰謝料を請求したい場合
会社に損害賠償・慰謝料を請求したい場合は、ベンナビ労働問題の利用をおすすめします。
ベンナビ労働問題は、労働問題を得意とする全国の弁護士が掲載されたポータルサイトです。
ベンナビ労働問題で弁護士を見つけて相談・依頼すれば、以下のようなサポートを受けられます。
- 安全配慮義務違反に該当する事案かどうかを判断してもらえる
- 証拠収集に関するアドバイスを受けられる
- 損害賠償金を適切に算定してもらえる
- 会社との交渉を一任できる
- 労働審判や裁判への対応も任せられる
ベンナビ労働問題には地域や相談内容を絞って検索できる機能があり、自分に合った弁護士を効率よくピックアップできます。
また、「初回の面談相談無料」「休日相談可能」などの条件で絞り込むこともできるので、有効に活用してみてください。
労働基準監督署 | 会社に安全配慮義務違反の是正を要求したい場合
会社に安全配慮義務違反の是正を要求したい場合は、全国各地の労働基準監督署に相談するのもよいでしょう。
労働基準監督署は、労働条件や安全衛生などに関する問題を扱う行政機関であり、会社に是正を促す権限を持っています。
相談する内容次第ですが、立ち入り検査や是正勧告を実行してもらえるかもしれません。
また、相談料は不要で、匿名でも相談することも可能です。
ただし、損害賠償請求をはじめとした民事上の争いには、原則として介入してもらえない点に注意してください。
労働局 | 労働問題について幅広く相談したい場合
労働問題について幅広く相談したい場合は、労働局への相談がおすすめです。
労働局が運営する総合労働相談コーナーでは、労働問題全般を扱っており、情報提供や問題解決に向けたあっせんに無料で対応しています。
どこに相談すればよいのか判断できないときには、まず労働局が運営している総合労働相談コーナーに足を運んでみてください。
予約不要・相談無料でプライバシーにも配慮してもらえるため、安心して相談できるはずです。
労働条件相談ほっとライン|安全配慮義務違反にあたるか電話で相談したい場合
安全配慮義務違反にあたるかどうかを電話で相談したい場合は、「労働条件相談ほっとライン」を利用しましょう。
労働条件相談ほっとラインは、労働基準に関する問題について無料で相談できるフリーダイヤルです。
専門のスタッフから助言を受けたり、適切な相談窓口を紹介してもらったりすることができます。
ただし、労働条件相談ほっとラインはあくまでも相談窓口であり、会社に対する指導などには対応していません。
会社に対する具体的な措置を求めるのであれば、弁護士や労働基準監督署などに相談することをおすすめします。
| 電話番号 | 0120-811-610 |
|---|---|
| 開設時間 | 平日17時00分~22時00分、土日祝日9時00分~21時00分(年末年始除く) |
会社を安全配慮義務違反で訴えた判例・事例
最後に、会社を安全配慮義務違反で訴えた判例・事例を4つ紹介します。
長時間労働についての安全配慮義務違反が認められた判例
本件は、月150時間前後の時間外労働などにより、労働者が心筋梗塞で死亡した事例です。
裁判では、長時間の時間外労働に加え、深夜労働・休日出勤も重なっていたことなどから、労働者に課せられた業務は過重なものだったと判断されました。
そのうえで、会社側が適切な労務管理を怠っていたことを理由に、安全配慮義務違反が認められたのです。
労災事故で後遺障害が残った賠償金として、9,000万円を獲得した事例
本件は、同僚の過失に起因する事故により、極度の疼痛などの後遺障害が残った労働者の事例です。
当該労働者には後遺障害等級6級が認められ、安全配慮義務違反を理由に裁判を起こした結果、9,000万円の賠償金を獲得しました。
なお、後遺障害を負った労働者は、賠償金のほか労災からの給付を受けることもできています。
会社内のセクハラについて、会社から慰謝料を勝ち取った事例
本件は、会社内でセクハラを受けていた20代女性が会社に対して損害賠償を求めた事例です。
セクハラに悩まされた女性はかねてから会社に相談していましたが、まともに取り合ってもらえませんでした。
そこで、弁護士のサポートを受け、環境整備を求める内容証明郵便を会社に送付したところ、セクハラはなくなり、120万円の慰謝料と200万円の和解金が支払われることになったのです。
パワハラが原因でうつ病となり、会社に損害賠償請求をした事例
本件は、上司から人格を否定する発言を受けてうつ病を発症し、会社への損害賠償請求に踏み切った労働者の事例です。
長期間の休職後に労災認定を受けた労働者は弁護士に相談し、労災による補償と各種損害との差額を請求しました。
その結果、会社との直接交渉を経て、1,400万円の和解金を獲得しています。
さいごに | 安全配慮義務違反で会社を訴えたい場合は弁護士に相談を!
長時間労働・過重労働を強いられていたり、ハラスメントを受けたりしている場合は、安全配慮義務違反として会社の責任を問える可能性があります。
また、労働環境によって実質的な損害が生じているのであれば、損害賠償を求めることも可能です。
しかし、安全配慮義務違反に該当するかどうかは、判断が難しいケースも少なくありません。
中途半端に会社と争う姿勢をみせてしまうと、余計なトラブルを招くおそれもあるので注意が必要です。
そのため、安全配慮義務違反で会社を訴えたい場合は、まず弁護士に相談してください。
労働問題を得意とする弁護士であれば、個々の状況を客観的に分析したうえで、今後の対応方針を的確に示してくれるはずです。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る
【不当解雇・残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
 この記事の監修
この記事の監修

ルーセント法律事務所

労務問題に関する新着コラム
-
長時間労働やハラスメントなどに苦しんでいる場合は、安全配慮義務違反として会社の責任を問うことも検討する必要があります。本記事では、安全配慮義務違反に該当するケー...
-
会社に有給休暇を申請したところ、「当日の休暇申請は欠勤だ」といわれてしまい、理不尽に感じている方もいるはずです。本記事では、有給休暇の取得条件や欠勤との違い、休...
-
取締役は原則いつでも辞任・退職できます。ただし、業務の途中や引継ぎなしで退職しようとすると、損害賠償を請求されることも少なくありません。本記事では、取締役の辞任...
-
実際に起こったコンプライアンス違反の事例をご紹介し、会社経営をする上で、どのような部分に気を付け、対処しておくべきかをご説明します。こちらの記事でご紹介した、コ...
-
内部告発は社内の不正を正すためにおこなうものです。しかし、内部告発をおこなったことによって不遇な扱いを受けてしまうケースも少なくありません。今回は内部告発のやり...
-
譴責は、懲戒処分の一つとして、会社の就業規則に定められるケースが多いでしょう。譴責処分を受けると、処分対象者の昇給・昇格に不利益な効果が生じることがあります。 ...
-
退職代行サービスを使われた企業はどう対処すればいいのか?弁護士運営ではない退職代行サービスは非弁行為?退職代行サービスを利用された後の流れや退職代行サービスを利...
-
就業規則とは、給与規定や退職規定などの労働条件が記載されている書類です。従業員を10人以上雇用している会社であれば、原則として作成した後に労働者に周知し、労働基...
-
団体交渉を申し込まれた場合に拒否をしてはならない理由や、拒否が認められる可能性がある正当な理由、また拒否する以外に団体交渉において会社が取ってはならない行為をご...
-
使用者が労働組合からの団体交渉の申入れを正当な理由なく拒否したり、組合活動を理由に労働者を解雇したりすると「不当労働行為」として違法となります。不当労働行為のパ...
労務問題に関する人気コラム
-
有給休暇とは、労働者が権利として取得できる休日のことです。有給休暇の取得は権利であり、これを会社が一方的に制限することは原則として違法です。この記事では、有給休...
-
残業代は原則、いかなる場合でも1分単位で支給する必要があります。しかし、会社によっては従業員へ正規の残業代を支払っていない違法なケースも存在します。この記事では...
-
在職証明書とは、職種や業務内容、給与など現在の職について証明する書類です。転職の際や保育園の入園申請時などに求められる場合がありますが、発行を求められる理由や記...
-
所定労働時間について知りたいという方は、同時に残業時間・残業代を正確に把握したいという思いがありますよね。本記事ではその基礎となる労働時間に関する内容をご紹介し...
-
就業規則とは、給与規定や退職規定などの労働条件が記載されている書類です。従業員を10人以上雇用している会社であれば、原則として作成した後に労働者に周知し、労働基...
-
同一労働同一賃金は2021年4月より全企業に適応された、正社員と非正規社員・派遣社員の間の待遇差を改善するためのルールです。本記事では、同一労働同一賃金の考え方...
-
管理監督者とは労働条件などが経営者と一体的な立場の者をいいます。この記事では管理監督者の定義や扱いについてわかりやすく解説!また、管理監督者に関する問題の対処法...
-
内部告発は社内の不正を正すためにおこなうものです。しかし、内部告発をおこなったことによって不遇な扱いを受けてしまうケースも少なくありません。今回は内部告発のやり...
-
ホワイトカラーエグゼンプションとは、『高度プロフェッショナル制度』ともいわれており、支払う労働賃金を労働時間ではなく、仕事の成果で評価する法案です。この記事では...
-
離職票とは退職した会社から受け取る書類のひとつで、失業給付の申請にあたり必要となるものです。どんな内容の書類なのか、いつ手元に届くのかなど、離職票を希望する際に...
労務問題の関連コラム
-
リファレンスチェックとは、中途採用において書類や面接だけでは分からない情報を求職者の前職に確認することを言います。実施の際に気を付けるべきポイントや質問項目、主...
-
退職代行サービスを使われた企業はどう対処すればいいのか?弁護士運営ではない退職代行サービスは非弁行為?退職代行サービスを利用された後の流れや退職代行サービスを利...
-
公益通報者保護法により設置が求められる内部通報制度の概要について説明。内部告発との違いは?労働者が内部通報を利用するメリットや実際に通報される内容、利用方法につ...
-
社内で犯罪行為などが発生することを防ぐためには、内部通報制度を設けることが有効です。その際、社内窓口を設置するだけでなく、弁護士に社外窓口を依頼すると、より効果...
-
在職証明書とは、職種や業務内容、給与など現在の職について証明する書類です。転職の際や保育園の入園申請時などに求められる場合がありますが、発行を求められる理由や記...
-
試用期間中でも解雇が認められるケースと不当解雇になり得るケース、試用期間中に対象社員にトラブルなく会社を辞めてもらう方法についてご説明します。正式雇用を決定する...
-
諭旨解雇(ゆしかいこ)とは、「懲戒解雇」の次に重い懲戒処分です。従業員を諭旨解雇する際、従業員とのトラブルを避けるために法律上の要件を踏まえて対応する必要があり...
-
取締役は原則いつでも辞任・退職できます。ただし、業務の途中や引継ぎなしで退職しようとすると、損害賠償を請求されることも少なくありません。本記事では、取締役の辞任...
-
転職活動において応募企業から内定をもらった後に届く「採用通知書」をテーマに、基本事項や法的性質について解説します。採用通知書が届いた際に確認するべきポイントや採...
-
企業が労務問題に直面した場合、対応を誤ると、思わぬ損害を被ってしまいます。企業が悩まされがちな労務問題のパターンや注意点、弁護士に労務問題の解決を依頼するメリッ...
-
問題社員をどうにか解雇できないかと悩んでいる会社は少なくないでしょう。この記事では、解雇の基礎的なルールをはじめ、問題社員を解雇する際のポイントや手順、有効性が...
-
労働者が有給休暇を取得しやすくするためには、労使協定によって時間単位の有給休暇を導入することも有効です。時間単位の有給休暇に関する法律上の要件や、導入のメリット...