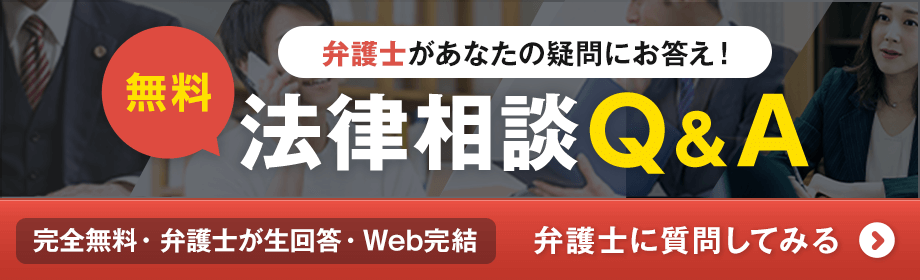団体交渉とは|交渉の流れや使用者側の注意点などを弁護士が解説

団体交渉とは、労働者側が団結して、多人数で使用者側と労働条件などについて話し合うことです。
日本国憲法では、労使間での対等な交渉を促して使用者による労働者の搾取を防ぐため、労働者に対して団体交渉権(団体行動権)を保障しています。
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
引用元:日本国憲法28条
労働者側から団体交渉の申入れを受けた場合、使用者側は正当な理由なく団体交渉を拒むことはできません。
そのため、使用者としては、労働組合法や労働基準法などの規制内容を踏まえて、真摯かつ毅然と対応する必要があります。
使用者が団体交渉に臨む際は、労働者側の数の圧力に屈しないように、十分な事前準備と法的な理論武装を整えていくことが大切です。必要に応じて弁護士などにも相談しながら、万全の態勢で団体交渉に臨みましょう。
この記事では、団体交渉の流れや、使用者側が団体交渉に臨む際の注意点などについて解説します。

団体交渉の協議事項は2種類に分類される
団体交渉では、労働組合があれば労働組合が、労働組合がなければ一定数以上の労働者が任意に組織した集団が交渉相手になります。
団体交渉の協議事項としては、義務的団体交渉事項と任意的団体交渉事項の2種類に分類され、以下ではそれぞれについて解説します。
義務的団体交渉事項|使用者側が団体交渉を拒否できない事項
義務的団体交渉事項とは、使用者側が団体交渉を拒否できない事項のことです。一例として、以下のような内容が該当します。
- 賃金・退職金
- 労働時間・休憩時間
- 休日・休暇
- 仕事場の安全衛生
- 労働災害の補償
- 配置転換・懲戒・解雇 など
任意的団体交渉事項|使用者側が団体交渉に応じるかどうか判断できる事項
任意的団体交渉事項とは、使用者側が団体交渉に応じるかどうか判断できる事項のことです。一例として、以下のような内容が該当します。
- 会社の経営戦略・生産方法などに関すること
- 他の労働者のプライバシーに関わること(他の労働者の賃金・退職金の開示要求など)
- 設備の更新について など
原則として使用者側は団体交渉を拒否できない
団体交渉の際、使用者には禁止事項などが定められています。
何も知らずに対応してしまうと不利益を被る恐れがありますので、以下で解説するポイントを押さえておきましょう。
正当な理由なく団体交渉を拒否すると「不当労働行為」にあたる
使用者は、正当な理由がなければ団体交渉を拒否することはできません(労働組合法7条2号)。
もし使用者が正当な理由なく団体交渉を拒んだ場合には、「不当労働行為」として、次の項目で解説する制裁の対象となります。
不当労働行為をした使用者にはペナルティが科される
使用者が不当労働行為をした場合、以下のようなペナルティが科されます。
労働委員会によって罰則付きの救済命令が発せられる
労働者は、労働委員会に対して、使用者の不当労働行為について審査開始の申立てをすることが認められています(労働組合法27条1項)。
労働者によって申立てがおこなわれると、労働委員会は実際に不当労働行為が存在するかどうかの審査をおこないます。
審査の結果、労働委員会が「不当労働行為が存在しており、労働者を救済する必要がある」と認めた場合には、労働委員会によって解雇撤回などの救済命令が発せられます(労働組合法27条の12第1項)。
もし救済命令の内容に不満がある場合、使用者は取消訴訟をおこなうことが可能ですが、裁判にて救済命令が確定すれば従うしかありません。
救済命令が確定したにもかかわらず、使用者が従わなかった場合には、以下のような刑罰の対象になります。
|
取消訴訟を経ずに救済命令が確定した場合 |
50万円以下の過料(労働組合法32条) |
|
取消訴訟を経て救済命令が確定した場合 |
1年以下の禁錮もしくは100万円以下の罰金 |
労働者側から損害賠償請求を受ける
団体交渉の問題となっている事項について、使用者側に具体的な法的責任が発生している場合には、労働者側から損害賠償請求などを受ける可能性があります。
例えば、職場での事故やハラスメントなどの場合、会社の安全配慮義務違反が問題になり得ます。また、不当解雇が問題となっている場合には、復職や解雇期間中の賃金を全額支払うことなどを求められる可能性があります。
労働者側との団体交渉は、「会社における責任問題について、法的手続きに発展する前に解決できる可能性がある場」と捉えることもできます。
使用者としては、労働者側の合理的な言い分に対しては耳を傾けて、円満な問題解決を目指す方が得策といえます。
例外的に使用者側が団体交渉を拒否できる場合もある
使用者側が労働者側からの団体交渉の申し入れを拒否するためには、正当な理由が必要です。
例えば、以下のようなケースであれば、団体交渉の拒否が認められる可能性があります。
団体交渉が難航して「法的手続きへの移行が適切」と認められる場合
団体交渉の目的は、「使用者と労働者の言い分を調整して、合理的な落としどころを見つけること」にあります。
すでに十分な団体交渉をおこなっており、合意に至るのが難しいという状況であれば、これ以上団体交渉を続けても解決は望めません。
このように、団体交渉が煮詰まり、労働審判や訴訟などの法的手続きへの移行が適切と認められる場合には、団体交渉を打ち切る正当な理由として認められる可能性があります。
法的手続きにて決着した問題について、労働者側から再度団体交渉の申し入れがあった場合
すでに法的手続きによって決着している問題について、再度団体交渉を申し入れることは、「労働者側による紛争の不当な蒸し返し」にあたります。
この場合、使用者には団体交渉を拒否する正当な理由があるとして認められる可能性があります。
使用者側が弁護士を同席させることについて、労働者側が拒否した場合
団体交渉の場において、使用者は弁護士を同席させるかどうかを自由に決定できます。
そうであるにもかかわらず、労働者側が弁護士の同席を拒否するようなことがあれば、労使間での健全な団体交渉は期待できません。
この場合、使用者には団体交渉を拒否する正当な理由があるとして認められる可能性があります。
労働者側の暴力行為などによって健全な話し合いが不可能な場合
どのような理由があっても、団体交渉の場で暴力行為などをおこなうことは許されません。
労働者側が暴力行為などをおこなっている状況では、労使間での健全な団体交渉は期待できません。
団体交渉にあたって労働者側による暴力行為があった場合、使用者側には団体交渉を拒否する正当な理由があるとして認められる可能性があります。
団体交渉を申し入れられた際の手順・流れについて
労働者側から団体交渉を申し入れられた場合、以下の流れに沿って和解の成立を目指すことになります。
労使間で打ち合わせをして、団体交渉の日時・場所・出席者などを決定する
まずは、予備折衝と呼ばれる事前の打ち合わせをおこない、団体交渉の進め方について双方の要望を調整して決定します。
団体交渉の日時・場所・出席者など、団体交渉の条件や環境を決定することは、交渉を進めるにあたって重要なポイントの一つです。
これらの条件を適切に設定しなければ、労働者側の交渉力が不当に強大化し、使用者側が交渉をコントロールできなくなる恐れもあります。
労使間で団体交渉をおこなう
交渉日当日は、労使間で主張を提示し合い、お互いに話し合って落としどころを探ります。労使間で事前に議題を共有しておけば、スムーズに交渉を進められます。
使用者側としては、労働者側の言い分が合理的であるか、法的な根拠はあるかなどを慎重に検討したうえで、要求に応じるかどうかを判断することになります。
なお、団体交渉は一回で終わることは少なく、何度か交渉を重ねて終結するのが一般的です。
和解が成立した場合は、合意書を作成する
団体交渉がうまく進んで合意が成立した場合には、和解合意書を作成して、労使の代表者が記名押印して締結します。
和解合意書とは、団体交渉によって決定した労使間の権利義務についてまとめた書面のことです。
和解合意書を作成する際は、本当にその内容で締結してよいかどうか、十分に精査したうえで作成しましょう。
和解が成立しなかった場合は、法的手続きを検討する
団体交渉がうまく進まずに決裂した場合には、労働審判や訴訟などの法的手続きを検討します。
すでに十分交渉を重ねており、このままでは解決が見込めない場合は、法的手続きに移行せざるを得ません。
ただし、法的手続きに移行するにはリスクもあります。本当に妥協できる部分はないか、一度確認しておくことをおすすめします。
団体交渉で失敗しないために使用者側が注意すべきことは?
労働者側から団体交渉の申し入れを受けた場合、使用者側が交渉を有利に進めるためには、以下の点に注意する必要があります。
できるだけ対等な条件で交渉できるように準備を整える
労働者側と事前の打ち合わせをおこなう際は、できるだけ不利にならないように準備を整えましょう。
特に、団体交渉の日時・場所・出席者などを取り決める際は注意が必要です。
①団体交渉の日時
団体交渉の日時は、労働者側の言いなりになるのではなく、使用者側の意思決定に関するキーパーソンが出席できる日時に設定しましょう。
キーパーソンが出席できなければ、使用者側の内部での意思疎通がうまくいかず、団体交渉が長引いてしまう恐れがあります。
②団体交渉の場所
労働者側のテリトリーで団体交渉をおこなうことは避けましょう。
会社のオフィスや労働組合事務所には多数の労働者がいるため、交渉日当日に予期せぬ乱入が起こるリスクがあります。
労働者側の人数による影響力に押されて負けないためにも、外部の会議室などを利用することをおすすめします。
③団体交渉の出席者
基本的に、使用者側は労働者側に比べて、人数の面では劣ります。
そのため、出席者の人数を無制限にしてしまうと、多勢に無勢の状況に陥ってしまう恐れがあります。
できるだけ対等な条件で団体交渉をおこなうためにも、出席者は労使同数にしましょう。
労働者側からの提案にはその場で応諾しない
たとえどんなに細かい事項であっても、団体交渉の場で労働者側の提案に応じることは避けましょう。
労働者側の勢いに押されてしまったりして、その場で応じてしまうと、あとになってから提案を拒否したいと主張しても「すでに話はついている」などと反論される恐れがあります。
口頭でのやり取りにも十分注意して、「労働者側の提案を応諾した」と受け取られかねない言動も慎むことです。
団体交渉の場において、労働者側から何らかの提案がされた場合には、必ず持ち帰って判断権者の指示を仰ぎましょう。
法的手続きに発展した場合のリスクなども考慮して、労働者側の主張を受け入れることも検討する
労働者側の主張が合理的な場合には、その主張を受け入れることも選択肢の一つとしてあります。
使用者側としては、労働者側を打ち負かすことを目的にするのではなく、「労使関係を良好に保つこと」「できるだけ少ないコストで紛争を解決すること」を目的にしましょう。
上記の観点を踏まえると、使用者としては労働者側の言い分を傾聴し、応諾と拒否のどちらが使用者側にとって得であるかを戦略的に判断する必要があります。
その際には、法的な観点から「労使どちらに分があるか」に加えて、法的手続きに発展した際のリスクやコスト、労働者側のモチベーション維持などの観点も考慮すべきといえます。
労働組合から団体交渉を申し入れられた際は弁護士に相談!
団体交渉の場では、労働者側はあらゆる手段を用いて、使用者側に対してさまざまな要求を提示してきます。
使用者側としては、労働法上の取り扱いを踏まえて、これらの要求に対応する必要があるほか、長期的な労使関係の在り方なども踏まえた総合的な判断が求められます。
団体交渉への対応方針について弁護士に相談すれば、労働者側の主張を受け入れるか否かについて、第三者的な視点から総合的なアドバイスを受けられます。
また、弁護士に団体交渉の場に同席してもらうことで、予定外の事態に対しても臨機応変に対応することが可能です。
団体交渉は、使用者側にとっては極めてセンシティブかつ負担の大きい問題であり、対応にあたっては慎重な事前準備が求められます。
万全の態勢で団体交渉に臨むためにも、労働組合から団体交渉の申し入れを受けた段階で、一度弁護士へご相談ください。

まとめ
団体交渉は労働者側に認められた憲法上の権利であり、使用者側が正当な理由なく団体交渉を拒否することはできません。
もし正当な理由なく団体交渉を拒否すると、不当労働行為として損害賠償請求や救済命令などの対象となる恐れがあります。
使用者が団体交渉の申し入れを受けた際には、団体交渉の日時・場所・出席者などに関する事前の交渉条件の整備から和解成立まで、一貫して慎重な姿勢で対応する必要があります。
安易に労働者側の要求を受け入れるような言動を発してしまうと、交渉時に不利になってしまう可能性があるので注意しなければいけません。
もし団体交渉の申し入れを受けた場合には、万全の態勢で団体交渉に臨むためにも、速やかに弁護士へご相談ください。弁護士は法律の専門家であり、総合的な視点から紛争解決を目指すことができます。
弁護士に相談すれば、法的な観点に加えて、「使用者にとって長期的にどのような解決が望ましいのか」を十分に検討したうえで、状況に合わせたアドバイスが望めます。

弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

【不当解雇・残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】
事務所詳細を見る
【労災/不当解雇の解決実績◎多数!】会社の非協力による労災申請の拒否や、納得できない理由での一方的な解雇・退職強要など、深刻な労働トラブルも当事務所にご相談ください!4人の特色ある弁護士が、実績に裏付けられた対応力でサポートします◆【平日夜間のご相談可○】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡


労務問題に関する新着コラム
-
長時間労働やハラスメントなどに苦しんでいる場合は、安全配慮義務違反として会社の責任を問うことも検討する必要があります。本記事では、安全配慮義務違反に該当するケー...
-
会社に有給休暇を申請したところ、「当日の休暇申請は欠勤だ」といわれてしまい、理不尽に感じている方もいるはずです。本記事では、有給休暇の取得条件や欠勤との違い、休...
-
取締役は原則いつでも辞任・退職できます。ただし、業務の途中や引継ぎなしで退職しようとすると、損害賠償を請求されることも少なくありません。本記事では、取締役の辞任...
-
実際に起こったコンプライアンス違反の事例をご紹介し、会社経営をする上で、どのような部分に気を付け、対処しておくべきかをご説明します。こちらの記事でご紹介した、コ...
-
内部告発は社内の不正を正すためにおこなうものです。しかし、内部告発をおこなったことによって不遇な扱いを受けてしまうケースも少なくありません。今回は内部告発のやり...
-
譴責は、懲戒処分の一つとして、会社の就業規則に定められるケースが多いでしょう。譴責処分を受けると、処分対象者の昇給・昇格に不利益な効果が生じることがあります。 ...
-
退職代行サービスを使われた企業はどう対処すればいいのか?弁護士運営ではない退職代行サービスは非弁行為?退職代行サービスを利用された後の流れや退職代行サービスを利...
-
就業規則とは、給与規定や退職規定などの労働条件が記載されている書類です。従業員を10人以上雇用している会社であれば、原則として作成した後に労働者に周知し、労働基...
-
団体交渉を申し込まれた場合に拒否をしてはならない理由や、拒否が認められる可能性がある正当な理由、また拒否する以外に団体交渉において会社が取ってはならない行為をご...
-
使用者が労働組合からの団体交渉の申入れを正当な理由なく拒否したり、組合活動を理由に労働者を解雇したりすると「不当労働行為」として違法となります。不当労働行為のパ...
労務問題に関する人気コラム
-
有給休暇とは、労働者が権利として取得できる休日のことです。有給休暇の取得は権利であり、これを会社が一方的に制限することは原則として違法です。この記事では、有給休...
-
残業代は原則、いかなる場合でも1分単位で支給する必要があります。しかし、会社によっては従業員へ正規の残業代を支払っていない違法なケースも存在します。この記事では...
-
在職証明書とは、職種や業務内容、給与など現在の職について証明する書類です。転職の際や保育園の入園申請時などに求められる場合がありますが、発行を求められる理由や記...
-
所定労働時間について知りたいという方は、同時に残業時間・残業代を正確に把握したいという思いがありますよね。本記事ではその基礎となる労働時間に関する内容をご紹介し...
-
就業規則とは、給与規定や退職規定などの労働条件が記載されている書類です。従業員を10人以上雇用している会社であれば、原則として作成した後に労働者に周知し、労働基...
-
同一労働同一賃金は2021年4月より全企業に適応された、正社員と非正規社員・派遣社員の間の待遇差を改善するためのルールです。本記事では、同一労働同一賃金の考え方...
-
管理監督者とは労働条件などが経営者と一体的な立場の者をいいます。この記事では管理監督者の定義や扱いについてわかりやすく解説!また、管理監督者に関する問題の対処法...
-
ホワイトカラーエグゼンプションとは、『高度プロフェッショナル制度』ともいわれており、支払う労働賃金を労働時間ではなく、仕事の成果で評価する法案です。この記事では...
-
内部告発は社内の不正を正すためにおこなうものです。しかし、内部告発をおこなったことによって不遇な扱いを受けてしまうケースも少なくありません。今回は内部告発のやり...
-
高度プロフェッショナル制度は、簡単に『量』ではなく『質』で給料を支払うという制度です。残業代ゼロ法案などと揶揄されていますが、働き方改革の関連法案でもある高度プ...
労務問題の関連コラム
-
実際に起こったコンプライアンス違反の事例をご紹介し、会社経営をする上で、どのような部分に気を付け、対処しておくべきかをご説明します。こちらの記事でご紹介した、コ...
-
問題社員の辞めさせ方が知りたい会社は案外多いのではないでしょうか。この記事では、問題社員を辞めさせる際に考慮すべきポイントや注意点、不当解雇とならずに解雇するた...
-
譴責は、懲戒処分の一つとして、会社の就業規則に定められるケースが多いでしょう。譴責処分を受けると、処分対象者の昇給・昇格に不利益な効果が生じることがあります。 ...
-
監査役を解任する方法や解任時の注意点について解説。監査役はたとえ任期途中であっても株主総会の特別決議によって解任することができます。実際に解任する際の流れや、解...
-
社内で犯罪行為などが発生することを防ぐためには、内部通報制度を設けることが有効です。その際、社内窓口を設置するだけでなく、弁護士に社外窓口を依頼すると、より効果...
-
会社に有給休暇を申請したところ、「当日の休暇申請は欠勤だ」といわれてしまい、理不尽に感じている方もいるはずです。本記事では、有給休暇の取得条件や欠勤との違い、休...
-
【弁護士監修】雇用保険とは何のために加入するのか、保険から出る給付金や保険料など、労務に役立つ計算式まで詳しく解説。雇用保険の加入義務や違法な場合など法的な視点...
-
内定通知書とは応募企業から求職者に送られる、内定を知らせるための書類です。内定通知書の記載内容やほかの書類との違い、法的効力や通知を受けた場合の行動など内定通知...
-
モンスター社員を辞めさせたくても、簡単に辞めさせることはできません。モンスター社員を辞めさせるにはどんなステップが必要なのか。また、弁護士に相談するべきメリット...
-
従業員の勤務態度を評価する際、どの様なポイントで判断して評価すべきか、『行動』『姿勢』をメインとした評価と、『実績』『能力』『勤務態度』の全てを評価するもの人事...
-
在職証明書とは、職種や業務内容、給与など現在の職について証明する書類です。転職の際や保育園の入園申請時などに求められる場合がありますが、発行を求められる理由や記...
-
従業員から未払い残業代を請求がされているのであれば、安易に自力で解決しようとせず、すぐに弁護士に相談し、迅速かつ適切な対応方法を選択すべきです。本記事では、残業...