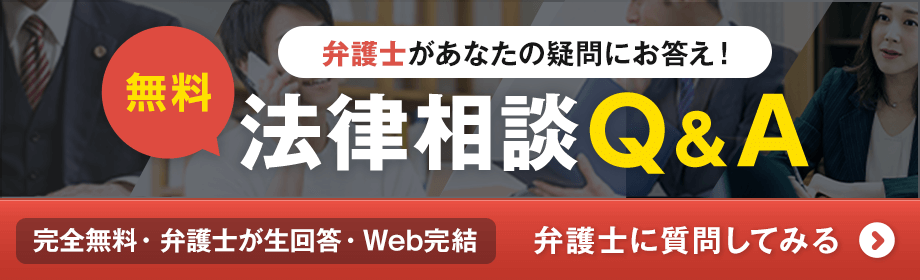OJT(On-the-Job Training)とは、主に企業で社員教育の手法として用いられる現場実習訓練のことです。簡単に言うと職場で実際に仕事をしながら業務を覚える研修です。
働き手不足の近年、企業の社員教育は本人の適性審査や企業の生産性向上のために取り入れられています。
社員研修でよくあるOJTとOFF-JTとは

OJTとOFF-JTは社員教育の手法として、よく耳にする言葉だと思います。現場実習を重ねながら業務を覚えるOJTに対し、OFF-JTは現場から離れて業務について学びます。
この項目では、社員研修などでよく用いられるOJTとOFF-JTについてわかりやすくご紹介します。
実際に職場で働くOJT
OJTとは『現場実習訓練』のことで、職場で実際に働きながら業務を覚えていきます。OJTは戦時中、アメリカで考案された実地訓練法です。
OJTでは以下の4つのポイントを重視します。これは4段階職業指導法とも呼ばれるもので、OJTを計画する上で、重要な考え方になります。
- 仕事を見せる
- 説明をする
- 実際に仕事をさせてみる
- 結果の確認をし、振り返りを行う
また、企業側は実施する際、①意図的、②計画的、③継続的という点を踏まえ計画する必要があります。
座学など職場外で業務を学ぶOFF-JT
OJTに対してOFF-JTとは、『職場外研修』のことをさします。
企業では、座学で会社の成り立ちや事業内容、業務に必要な最低限のスキルなどを学ぶことが多いです。
■企業がOJTを行う理由
厚生労働省によると、企業の7割以上が社員教育においてOJTを重視しています。
企業はなぜOJTを研修として重視し、取り入れるのでしょうか? この項目では、OJTの実施意図についてご紹介します。
実務を通した業務習得
OJTでは、社員に実務を通して業務を覚えてもらうことで、即戦力として早い段階から会社に貢献してもらいたいという意図があります。
実際に職場に配置して行うため、企業側からすると指導コストがあまりかからないという点もあります。
さまざまな配置を通した適性判断
現場での実施訓練は新入社員の適性判断にも有用です。
当初期待していた適性が認められなかった場合に、検討していた人事配置を変更することができます。
- 新入社員研修|社員研修のリスキル
OJTのメリット・デメリット

OJTは多くの企業で実施されている社員教育法ですが、デメリットもあります。
この項目では、OJTのメリット・デメリットについてご紹介します。
メリット|教育コストがかからない
OJTは職場内で実施できる研修なので、外部講師などを招くよりコストをかけずに社員教育を行うことができます。
また、この他にも以下のようなメリットがあります。
- 業務指導でのコストが少ない
- 新入社員の個々人のペースに合わせることができる
- 先輩社員とのコミュニケーションがとれる
継続的にOJTを行うことで、職場全体として新入社員を育てていこうという風土も生まれます。
新入社員が気をつけるポイント
OJTではいきなり職場に配属され、実際の業務に関わることになるので、新入社員からすると緊張の連続になると思います。
その際、重要なのは『報告・連絡・相談』です。
- 判断が必要なものは必ず上司の指示を仰ぐ
- 自己解決できるものは解決の方向性を上司に伝えて実行する
上記のことを心がけ、わからないことは早い段階で上司に聞くようにすることで、確認漏れや自己判断によるミスを減らすことができます。
【参考記事】OJTの8つのメリットとは?効果を最大化させる4つのポイントを詳しく解説|アーティエンス株式会社
デメリット|計画的に実施しないと負担増加
OJTは教育コストがかからない分、指導者に負担がかかる方法です。計画的に実施しないと現場にかかる負担が増加し、結果的に指導内容や新入社員の習熟度に差が出てしまいます。
- 現場指導者の負担が大きい
- 指導者によって習熟度に差が出る
- 教育指導が現場任せになる
上司が気をつけるポイント
OJTの基本は仕事を見せたり説明したりした上で『PDCA(※)』サイクルを回すこと。そのため、「まずやってみろ。」という指導は計画的なOJTとはいえません。
計画的なOJTを行う際には以下のことに配慮する必要があります。
- 目標を明確に設定し、説明する
- 目標達成のための具体的な指示を出す
- 振り返りの時間をとり個々の習熟度を確認する
- ルールや規範を逸脱する行為を早期から教えない
また、新入社員が目標を達成できなかったり、ミスをしたりした場合に感情的に怒ったり一方的な叱責を行うことは研修の意図にそぐわないため控えましょう。
|
※PDCAとはPlan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)を一連の流れとした業務を円滑に進め、改善する手法のことです。 |
企業が取り組むOJT研修事例
この項目では、実際に企業で取り組まれているOJTやユニークな研修についてご紹介します。
実践が伴ったユニークな入社式
入社式ですでにOJTの考え方を取り入れている企業もあります。
クレーンゲーム設置台数がギネス世界記録に認定されている世界一のゲームセンター「エブリデイ」や、県内売りたいショップNO.1獲得の埼玉県内13店舗のブランド品・貴金属等のリサイクル店「エブリデイゴールドラッシュ」を経営する株式 会社東洋(埼玉県北本市/代表取締役 中村秀夫)は、2018年4月2日(月)、業界初(※一般社団法人 日本クレーンゲーム協会調べ)となる『クレーンゲーム入社式』を開催致します。
引用元:ドリームニュース|【業界初※】 「世界一のクレーンゲーム専門店」×「新入社員」=?? 『クレーンゲーム入社式』2018年4月2日開催!! (※日本クレーンゲーム協会調べ)
この企業では、制服や証書などが入った筒をクレーンゲームで取るという入社式が行われました。
実際の業務で顧客にクレーンゲームのコツなどを聞かれたり教えたりすることがあることから、入社式でゲームをプレイしながら実際の業務をイメージしてもらうという意図があるそうです。
実際の業務にも活かせることから、この入社式もOJTといえそうです。
新入社員がOJTに臨む際に気をつけるポイント

OJTは実際に事業が行われている現場で、実際の業務を学びながら行う研修です。
新入社員の場合、会社のことや業務請負のことについて知識が浅いため、ミスが起きるのはあたりまえのことです。もしも、ミスをして叱責された場合も落ち込まず『なぜミスをしたのか』『次回からどのようなことに気をつければよいのか』など疑問に思ったことを先輩社員などに確認しましょう。
まとめ
OJTには働き手不足の現代では新入社員も『即戦力の働き手』として考え、早い段階で現場業務に慣れさせるという意図もあります。そのため、少子化の現代では、今後より多くの企業がOJTを取り入れると予測されます。
一方で、OJTは新入社員、指導社員ともに多少負担のかかる方法でもあります。そのため上層部でも、新人教育を現場任せにはせず、綿密に計画を練ることで効果的な研修ができるとよいですね。
この記事でOJTに関する疑問が解消されれば幸いです。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

【不当解雇・残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
 この記事の監修
この記事の監修

弁護士法人プラム綜合法律事務所

労務問題に関する新着コラム
-
長時間労働やハラスメントなどに苦しんでいる場合は、安全配慮義務違反として会社の責任を問うことも検討する必要があります。本記事では、安全配慮義務違反に該当するケー...
-
会社に有給休暇を申請したところ、「当日の休暇申請は欠勤だ」といわれてしまい、理不尽に感じている方もいるはずです。本記事では、有給休暇の取得条件や欠勤との違い、休...
-
取締役は原則いつでも辞任・退職できます。ただし、業務の途中や引継ぎなしで退職しようとすると、損害賠償を請求されることも少なくありません。本記事では、取締役の辞任...
-
実際に起こったコンプライアンス違反の事例をご紹介し、会社経営をする上で、どのような部分に気を付け、対処しておくべきかをご説明します。こちらの記事でご紹介した、コ...
-
内部告発は社内の不正を正すためにおこなうものです。しかし、内部告発をおこなったことによって不遇な扱いを受けてしまうケースも少なくありません。今回は内部告発のやり...
-
譴責は、懲戒処分の一つとして、会社の就業規則に定められるケースが多いでしょう。譴責処分を受けると、処分対象者の昇給・昇格に不利益な効果が生じることがあります。 ...
-
退職代行サービスを使われた企業はどう対処すればいいのか?弁護士運営ではない退職代行サービスは非弁行為?退職代行サービスを利用された後の流れや退職代行サービスを利...
-
就業規則とは、給与規定や退職規定などの労働条件が記載されている書類です。従業員を10人以上雇用している会社であれば、原則として作成した後に労働者に周知し、労働基...
-
団体交渉を申し込まれた場合に拒否をしてはならない理由や、拒否が認められる可能性がある正当な理由、また拒否する以外に団体交渉において会社が取ってはならない行為をご...
-
使用者が労働組合からの団体交渉の申入れを正当な理由なく拒否したり、組合活動を理由に労働者を解雇したりすると「不当労働行為」として違法となります。不当労働行為のパ...
労務問題に関する人気コラム
-
有給休暇とは、労働者が権利として取得できる休日のことです。有給休暇の取得は権利であり、これを会社が一方的に制限することは原則として違法です。この記事では、有給休...
-
残業代は原則、いかなる場合でも1分単位で支給する必要があります。しかし、会社によっては従業員へ正規の残業代を支払っていない違法なケースも存在します。この記事では...
-
在職証明書とは、職種や業務内容、給与など現在の職について証明する書類です。転職の際や保育園の入園申請時などに求められる場合がありますが、発行を求められる理由や記...
-
所定労働時間について知りたいという方は、同時に残業時間・残業代を正確に把握したいという思いがありますよね。本記事ではその基礎となる労働時間に関する内容をご紹介し...
-
就業規則とは、給与規定や退職規定などの労働条件が記載されている書類です。従業員を10人以上雇用している会社であれば、原則として作成した後に労働者に周知し、労働基...
-
同一労働同一賃金は2021年4月より全企業に適応された、正社員と非正規社員・派遣社員の間の待遇差を改善するためのルールです。本記事では、同一労働同一賃金の考え方...
-
管理監督者とは労働条件などが経営者と一体的な立場の者をいいます。この記事では管理監督者の定義や扱いについてわかりやすく解説!また、管理監督者に関する問題の対処法...
-
内部告発は社内の不正を正すためにおこなうものです。しかし、内部告発をおこなったことによって不遇な扱いを受けてしまうケースも少なくありません。今回は内部告発のやり...
-
ホワイトカラーエグゼンプションとは、『高度プロフェッショナル制度』ともいわれており、支払う労働賃金を労働時間ではなく、仕事の成果で評価する法案です。この記事では...
-
離職票とは退職した会社から受け取る書類のひとつで、失業給付の申請にあたり必要となるものです。どんな内容の書類なのか、いつ手元に届くのかなど、離職票を希望する際に...
労務問題の関連コラム
-
使用者が労働者側から団体交渉の申入れを受けた場合、労働組合法や労働基準法などの規制内容を踏まえて、真摯かつ毅然と対応する必要があります。団体交渉の流れや、団体交...
-
従業員から未払い残業代を請求がされているのであれば、安易に自力で解決しようとせず、すぐに弁護士に相談し、迅速かつ適切な対応方法を選択すべきです。本記事では、残業...
-
【弁護士監修】雇用保険とは何のために加入するのか、保険から出る給付金や保険料など、労務に役立つ計算式まで詳しく解説。雇用保険の加入義務や違法な場合など法的な視点...
-
高度プロフェッショナル制度は、簡単に『量』ではなく『質』で給料を支払うという制度です。残業代ゼロ法案などと揶揄されていますが、働き方改革の関連法案でもある高度プ...
-
企業が労務問題に直面した場合、対応を誤ると、思わぬ損害を被ってしまいます。企業が悩まされがちな労務問題のパターンや注意点、弁護士に労務問題の解決を依頼するメリッ...
-
問題社員の辞めさせ方が知りたい会社は案外多いのではないでしょうか。この記事では、問題社員を辞めさせる際に考慮すべきポイントや注意点、不当解雇とならずに解雇するた...
-
うつ病になった社員の復帰が難しい場合の対処法やトラブルを防ぐためにできる退職までの話の進め方、うつ病で解雇して裁判になった過去の例などをご説明します。うつ病の社...
-
在職証明書とは、職種や業務内容、給与など現在の職について証明する書類です。転職の際や保育園の入園申請時などに求められる場合がありますが、発行を求められる理由や記...
-
ホワイトカラーエグゼンプションとは、『高度プロフェッショナル制度』ともいわれており、支払う労働賃金を労働時間ではなく、仕事の成果で評価する法案です。この記事では...
-
就業規則とは、給与規定や退職規定などの労働条件が記載されている書類です。従業員を10人以上雇用している会社であれば、原則として作成した後に労働者に周知し、労働基...
-
実際に起こったコンプライアンス違反の事例をご紹介し、会社経営をする上で、どのような部分に気を付け、対処しておくべきかをご説明します。こちらの記事でご紹介した、コ...
-
公益通報者保護法により設置が求められる内部通報制度の概要について説明。内部告発との違いは?労働者が内部通報を利用するメリットや実際に通報される内容、利用方法につ...