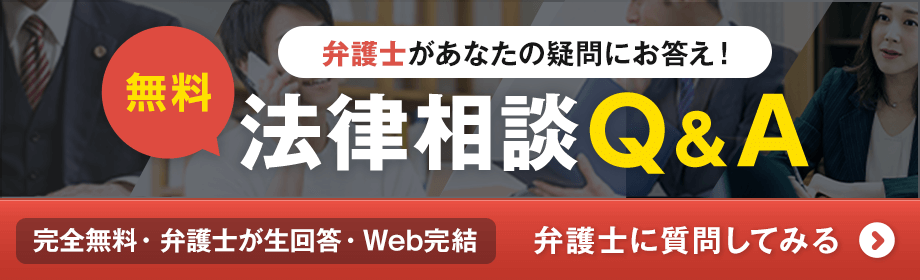ハラスメント・労務問題・会計の不正などを内部通報した場合に、通報者が守られる「公益通報者保護法」が2004年に公布、2006年に施行されました。
しかし、実際には内部通報による企業からの報復を恐れて、通報者が通報できないケースもありました。
2020年に「公益通報者保護法」が改正され、2022年6月1日以降は従業員301人以上の企業などに内部通報制度の整備が義務付けられることになりました。
事業者に対し、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口設定、調査、是正措置等)を義務付け。具体的内容は指針を策定【第11条】
※中小事業者(従業員数300人以下)は努力義務
内部通報制度では、内部通報窓口の設置が求められており、企業は社内通報窓口・外部通報窓口の設置をすることになります。
そのなかでも外部通報窓口はどんな役割を果たすのでしょうか?
設置の目的と内部通報との違いについて紹介します。
【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談OK
外部通報窓口の役割とは|設置する理由や通報できる内容
外部通報窓口とは、企業が通報に対する業務を依頼した法律事務所や、外部通報窓口の専門会社に社内の不正を通報する場所です。
平成28年の消費者庁の調査によると、外部通報窓口を設置する理由としては以下のものがありました。
- 社内の事情に左右されずに公正な判断ができる 68.7%
- 面識がないので従業員が通報しやすい 51.8%
- 通報者の匿名性を確保しやすい 48.3%
【参考】消費者庁|平成28年度民間事業者における内部通報制度の実態調査報告書
社内通報窓口への通報では躊躇してしまうケースの是正
社内通報窓口の場合、規模が小さな企業であれば通報窓口の担当者と顔見知りのケースもあるでしょう。
通報者の保護は公益通報者保護法で求められていますが、その通報内容を顔見知りの担当者に説明したくない場合は通報者が通報を躊躇してしまう可能性もあります。
匿名での通報も可能としている企業も多いですが、社内の担当者に電話で通報する場合には声で通報者が特定できてしまうこともあるかもしれません。
外部通報窓口の場合、社内の事情を知らない弁護士や専門会社が通報を受けてくれるので匿名性の確保や公正な判断に期待ができます。
内部通報窓口との違い
内部通報窓口は社内の総務部門・法務部門・人事部門などが窓口になるケースが多いです。
内部通報窓口の場合、勇気を出して通報したのに社内の事情によりうやむやにされてしまうケースもあります。
さらに、公益通報者保護法では通報者が不利益を被ることがないように求められていますが、企業の認識が薄い場合は通報者が不利益を被ったり、嫌な思いをしたりすることもあるかもしれません。
その結果、社内通報窓口自体はあったとしても実際に報復が怖くて利用できないというケースもあるでしょう。
通報者にとっては外部通報窓口に通報したほうが公正な判断がされやすい印象から通報がしやすくなります。
匿名性も内部通報窓口を利用するより確保しやすいといえるでしょう。
情報漏洩の可能性を抑える
また、外部通報窓口を設置する企業としては、通報に迅速に対応できなかったり、対応に慣れていないことにより情報漏洩したりする可能性を避けたいという思いがあります。
このようなことが起これば、通報者からの損害賠償請求を受ける可能性もあり、避けたいところです。
外部に依頼することによりコストはかかりますが、慣れない業務をするよりは専門家に任せてしまった方が良いという思いから外部相談窓口を設置する企業も多いのです。
どんな時に外部通報窓口は利用できる?
労務提供先への通報をする場合、公益通報者保護法に基づく保護を受けるための要件は以下の通りです。
1号通報(労務提供先への通報)の場合
通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思われることが要件となります。
このうち「まさに生じようとしている」とは、通報対象事実の発生が切迫しその蓋然性が高いことをいいますが、必ずしも発生する直前のみをいうわけではありません。誰が、いつ、どこでやるといったことが社内で確定しているような場合であれば、実行日まで間がある場合であっても「まさに生じようとしている」といえるでしょう。
引用元:消費者庁|通報者の方へ
通報対象事実は、特定の対象となる法律に違反する犯罪行為または最終的に刑罰につながる行為であることが求められます。
2022年5月時点では、刑法・食品衛生法・金融商品取引法・JAS法・個人情報保護法など計480の法律に規定する犯罪行為が対象です。
また、法律違反の行為が既に起きてしまった場合だけではなく、これから起こりそうな内容についても、法律に抵触する内容ならば相談できます。
「まさに生じようとしている」とは
これに関しても消費者庁から定義が定められているのでご紹介します。
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨」について
このうち「まさに生じようとしている」とは、通報対象事実の発生が切迫しその蓋然性が高いことをいいますが、必ずしも発生する直前のみをいうわけではありません。誰が、いつ、どこでやるといったことが社内で確定しているような場合であれば、実行日まで間がある場合であっても「まさに生じようとしている」といえるでしょう。
例えば、事業者が廃棄物の不法投棄をする方針を固めただけでは、「生ずるおそれ」はあっても「まさに生じようとしている」とはいえませんが、いつ、どこに、誰がやるといったことが確定したような段階であれば、「まさに生じようとしている」といえる場合が多いと考えます。引用元:消費者庁|行政機関の方へ
外部通報窓口における基本用語と適用法律

公益通報とは
「公益通報」とは、企業の違法行為や不正を労働者が内部通報することをいいます。
企業の不正があっても、公益通報できる内部通報制度が整っていない場合、不正の被害者や発見者が通報をすることを躊躇して、社内の不正はなくなりません。
不正を隠すための不正を行うなどしてさらに大きな不祥事になることも考えられます。
また、社内に相談や通報する仕組みがなければ、不正の被害者や発見者は不正の是正のために「内部告発」という手段を選ぶ可能性があります。
内部告発は社内の不正をマスコミや行政に告発することです。社内の不正がマスコミなどに取り上げられれば、企業のブランドイメージは大きく失墜します。
このような内部告発を避けるためにも通報者が公益通報をしやすい環境を整えて、問題が小さい内に解決していくことが大切なのです。
公益通報は通報者も企業も守られる方法といえます。
公益通報者保護法とは
通報者が公益通報できる内部通報制度が整ったとしても、通報したことにより解雇や配置転換、嫌がらせなどの不利益を被る可能性があれば内部通報がしにくくなります。
そのため、「公益通報者保護法」では、内部通報をした通報者が保護される仕組作りを求めており、次のような不利益からの保護を定めています。
- 解雇の無効(法第3条)
- 派遣契約の解除の無効(法第4条)
- 不利益な取扱いの禁止(法第5条)
具体的には降格、減給、退職金の減額・没収、給与上の差別、訓告、自宅待機命令、退職の強要、専ら雑務に従事させることなどです。
2018年にスルガ銀行による不正融資問題が起きましたが、多くの労働者は問題を認識していたそうです。しかし、内部通報を利用しようと思ったものの通報したことによる不利益を恐れて結局止めたという労働者が200人弱もいたとのことです。
当時、内部通報をする通報者の保護が約束されていればこのような大きな問題に発展しなかったかもしれません。このような問題を受けて、2020年の改正により、2022年6月1日以降は従業員301人以上の企業などに内部通報制度の整備が義務付けられました。
万が一、通報したことにより不利益な状況になった場合には、労働審判手続を申し立てたり、最終的に訴えを提起したりして、裁判所の手続による解決を図っていくことになるでしょう。
【参考】消費者庁|通報者の方へ
公益通報の窓口は3パターン
公益通報の窓口は社内通報窓口、外部通報窓口、併用というケースがあります。実際の運用では、以下のように社内通報窓口と外部通報窓口を併用しているケースが多いです。
- 社内通報窓口 32.1%
- 外部通報窓口 7.0%
- 併用 59.9%
【参考】消費者庁|平成28年度民間事業者における内部通報制度の実態調査報告書
通報者について
公益通報は企業で働く「労働者」が通報できます。具体的には以下の通りです。
- 正社員
- パート・アルバイト
- 派遣社員
- グループ会社社員
- 役員
- 退職後1年以内の退職者(派遣社員も含む)
たとえば、企業Aで務めるBが派遣社員Cにセクハラをした場合、派遣社員Cは企業Aから直接雇用を受けているわけではありませんが、企業Aの通報窓口を利用できます。
退職者と役員は通報できないことになっていましたが、2022年6月の法改正で保護される通報者の範囲が拡大され、役員と退職後1年以内の者も保護の対象となりました。
なお、通報時点で「労働者」であった退職者への不利益な取扱いとしては、公益通報をしたことに対する報復で退職金の没収や減額などがあります。
外部通報窓口に1年間で寄せられる件数
消費者庁のデータによると、外部通報窓口を設置している企業で1年間に通報が寄せられる件数は、
- 1〜5件が49.7%
- 0件が29.1%
- 6〜10件が6.7%
とのことです。 (n=626)
従業員数別にみると、3,000人超の企業では、通報件数が1件以上あった割合が8割以上あり(83.7%)、「6~10 件」(10.0%)、「11 件~30 件」(15.3%)、「31 件~50 件」(4.2%)を合わせた割合は3割(29.5%)と、通報件数が多くなります。
規模が大きい企業の方が不正は起こりやすかったり、通報しやすかったりすることが推測できます。
【参考】消費者庁|平成28年度民間事業者における内部通報制度の実態調査報告書
寄せられる通報の内容
外部通報窓口業務を請け負う株式会社エス・ピー・ネットワークは、実際の通報内容を公表しています。
- 上司への不満・パワハラ 37.0%
- 上司以外への不満・パワハラ 15.5%
- 改善提案・意見 8.6%
- 社内ルール 7.9%
- 残業問題 3.9%
- 不正(疑いも含む) 3.3%
- 給与 3.0%
- セクハラ 2.5%
- 有給休暇 2.2%
- 契約関係 2.2%
- 退職問題 2.1%
- 法律・法令違反(疑いも含む) 1.7%
- 人事異動 1.4%
- 評価制度 1.1%
- 人員不足 0.8%
- 情報漏洩(疑いも含む) 0.7%
- 禁煙・喫煙問題 0.7%
- 差別問題 0.1%
- その他 5.3%
この結果から、上司・上司以外のパワハラに対する通報が圧倒的に多いことがわかります。しかし、労務問題や給与についてなど幅広い内容の通報もあるようです。
【参考】株式会社エス・ピー・ネットワーク(対象期間:2003年7月1日~2022年4月30日)
外部通報窓口を利用するメリット
外部通報窓口を利用するメリットは、匿名性が確保されやすいことです。
社内通報窓口でも匿名通報を受け付けている場合もありますが、電話の声などで通報者がわかってしまうこともあります。
通報者の保護が求められていますが、残念ながら通報したことにより不利益を被った事例もあります。社内の人間になるべく通報した事実を知られたくない場合には外部通報窓口が有効です。
外部通報窓口を利用するデメリット
外部通報は匿名性の確保がしやすいなどのメリットもありますが、匿名で通報したら結局具体的な調査ができずに問題が解決しないということもあります。
たとえば、セクハラの被害にあった通報者が、社内で身バレやセクハラの具体的な内容を公表したくないために匿名で通報したとします。
企業としては具体的な調査がしにくいため、原因の追究をしたり再発防止策を講じたりすることがしにくくなります。
このような場合、セクハラの加害者が、問題発覚しないことを良いことに、セクハラが続くなどのケースもあるでしょう。
問題を本気で改善したい場合には、社内通報で匿名にしない方が良い場合もあります。
外部通報窓口の利用方法
外部通報窓口を利用する時には、まず電話・メール・手紙・faxなどで外部通報窓口に通報をします。
通報を受けた窓口は相談者から情報収集を行い、その内容を企業に伝えます。企業は事実確認をした後に企業の方針を決め、それについて窓口へ報告します。窓口から相談者に企業からの回答を伝えます。
外部通報に必要な情報
外部通報をする場合、一般的に必要となる情報は以下の通りです。
- 通報者の氏名(実名)
- 通報者の連絡先
- 法令違反をしている勤務先(会社等の名称、住所等)
- 法令に違反している行為(又は法令に違反しようとしている行為)、どの法令の違反が疑われるか
- 法令違反行為を客観的に証明できる資料
ただし、匿名での通報を受け付けている場合もあります。
外部通報窓口として利用できる先
外部通報窓口の担い手は以下のようになっています。
- 法律事務所(顧問弁護士) 49.2%
- 親会社・関連会社 22.7%
- 法律事務所(顧問弁護士ではない) 21.6%
- 通報受付の専門会社 14.9%
法律事務所が外部通報窓口になるケースが非常に多いことがわかります。
通報をただ受けるだけではなく、不正の内容を法律の専門家として企業の指導やアドバイスできることにも期待されているからといえるでしょう。
【参考】消費者庁|平成28年度民間事業者における内部通報制度の実態調査報告書
通報受付の専門会社
また、通報受付の専門会社も存在し、このような会社を窓口にするケースもあります。
従業員数3,000人超の企業では専門会社を窓口にしている企業が23.3%と、他の規模の企業と比べると多くなります。株式会社クオレ・シー・キューブでは外部相談窓口としてさまざまな相談に対応しています。
こちらの会社のカウンセラーは産業カウンセラーの資格も持っており、通報に直結する問題以外の相談も受け入れているそうです。利用者の声には以下のようなものがあります。
ハラスメントと言われることが怖くて部下をうまく指導できずに困っていました。カウンセラーとコミュニケーションの方法を見直したことで指導方法に少し自信が持てました。是非実践してみたいと思います。(40代男性・管理部門)
引用元:株式会社クオレ・シー・キューブ
社内に相談しづらかったので外部窓口を利用しました。
相談するうちに会社へ報告する気持ちが固まり、窓口を通して社内担当者に繋いで頂きました。自分では話しにくいことを、客観的に、整理して会社に報告してくれるので、気持ちがとても楽になりました。もっと早く相談すれば良かったです。(30代女性・顧客サービス部門)
引用元:株式会社クオレ・シー・キューブ
このように実際に通報するわけではなくても問題解決したり、相談しながら通報の意思が固まったりするケースもあります。
専門的な知識を持つ担当者が答えてくれるので、通報しようか迷っている場合は相談という形で連絡するのも良いでしょう。
通報者の注意点
通報者は不正の証拠となる写真・ボイスレコーダー・スマホの動画などを用意しましょう。
口頭の説明だけだと事実確認できない可能性もあるからです。もしこのような証拠がない場合には、不正内容についてなるべく詳しく書いたメモを残しておきましょう。時間や場所などなるべく詳細まで書き起こしてください。
詳細が分からない内容の場合、通報された人も「知らない。勘違いでは?」と言い逃れできてしまいますが、詳細な記載があれば、事実確認できる可能性も高くなるでしょう。
まとめ
内部通報制度では不正を通報するための通報窓口の整備を求めており、社内の総務部門や法務部門などが窓口となる内部通報窓口と、法律事務所などが窓口となる外部通報窓口があります。
企業により設置する窓口はさまざまですが、内部通報窓口と外部通報窓口を併用するケースも多いです。
外部通報窓口は匿名性の確保や専門家(弁護士)による公正な判断に期待ができます。法律で保護されているとはいえ、内部の人に不正の詳細を話したくない場合には外部通報窓口を選んだ方が良いといえます。
ただし、外部通報窓口に匿名で通報したところ、調査が進まず問題解決にならないというケースもあるので、その点には注意する必要があります。
外部通報窓口は、社外の人の意見も聞くことができるので、企業への通報に至らなくても悩みが解決することもありますし、通報の後押しをしてもらえることもあります。
一人で悩んでいても職場での環境が悪くなる一方かもしれないので、外部通報窓口があるならば是非相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

【不当解雇・残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】
事務所詳細を見る
【労災/不当解雇の解決実績◎多数!】会社の非協力による労災申請の拒否や、納得できない理由での一方的な解雇・退職強要など、深刻な労働トラブルも当事務所にご相談ください!4人の特色ある弁護士が、実績に裏付けられた対応力でサポートします◆【平日夜間のご相談可○】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡


その他に関する新着コラム
-
会社役員を辞めるのは原則自由です。ただし、タイミングによっては損害賠償を請求されることがあるため、しっかり見極めなければなりません。本記事では、会社役員の辞め方...
-
本記事では、法律トラブルを依頼中の弁護士に不信感を抱く6つのケースについて紹介します。それらの原因と対処法についても詳しく解説し、ほかの弁護士に変えたいと思った...
-
本記事では、会社との労働問題を通常訴訟で解決したいと考えている方に向けて、労働問題で会社を訴える際の手順、会社を訴えるメリット、会社との訴訟を弁護士に依頼すべき...
-
長時間労働やハラスメントなどの労働問題に直面しているにも関わらず、どこに相談すればいいか分からず悩んでいませんか。本記事では豊中市で労働相談が可能な4つの窓口と...
-
長時間労働やハラスメントなどの労働問題に直面しているにも関わらず、どこに相談すればいいか分からず悩んでいませんか。本記事では練馬区で労働相談が可能な5つの窓口と...
-
長時間労働やハラスメントなどの労働問題に直面しているにも関わらず、どこに相談すればいいか分からず悩んでいませんか。本記事では松戸市で労働相談が可能な4つの窓口と...
-
長時間労働やハラスメントなどの労働問題に直面しているにも関わらず、どこに相談すればいいか分からず悩んでいませんか。本記事では世田谷区で労働相談が可能な5つの窓口...
-
長時間労働やハラスメントなどの労働問題に直面しているにも関わらず、どこに相談すればいいか分からず悩んでいませんか。本記事では豊田市で労働相談が可能な4つの窓口と...
-
長時間労働やハラスメントなどの労働問題に直面しているにも関わらず、どこに相談すればいいか分からず悩んでいませんか。本記事では西宮市で労働相談が可能な4つの窓口と...
-
長時間労働やハラスメントなどの労働問題に直面しているにも関わらず、どこに相談すればいいか分からず悩んでいませんか。本記事では神戸市で労働相談が可能な4つの窓口と...
その他に関する人気コラム
-
この記事では、労働基準監督署でパワハラの相談をして解決できることや、パワハラ問題の解決フローについて紹介します。
-
うつ病と診断されたら無理をせず、休職するのも大切です。本記事では、うつ病で休職する際の手続き方法や相談先、休職期間の過ごし方や傷病手当金の申請方法などを紹介しま...
-
有給休暇の取得理由は、法律上必要ありません。有給の休暇取得は、労働者に与えられた権利ですし、休暇中の過ごし方は労働者の自由です。しかし、実際は会社で上司から取得...
-
企業が労働基準法に違反した行為をすると罰則が与えられます。以下で労働基準法違反となるのはどういったケースなのか、その場合の罰則はどのくらいになるのかご説明してい...
-
本記事では「源泉徴収票を紛失してしまった」「複数枚必要になった」など、さまざまな理由で再発行が必要な場合に知っておくべき知識と対処法を解説します。
-
うつ病にかかり退職を考えている方は、退職の流れや生活費などが気になると思います。この記事では、うつ病で退職する場合の流れや保険、支援制度についてご紹介します。
-
試用期間中に「この会社合わないかも…。」と思って退職を考える人もいるでしょう。試用期間中の退職は正社員同様、退職日の申し出や退職届などが決まっています。この記事...
-
マイナンバーカードは郵便またはインターネットから作ることができます。まだ作成していない場合はこれからの利用拡大に備えて作っておきましょう。この記事では、マイナン...
-
マイナンバー制度は利用する機会が少ないため、通知カード・マイナンバーカードを紛失した方もいるのではないでしょうか。通知カード・マイナンバーカードを紛失した場合、...
-
労働組合の作り方について、実は難しいことはありません。煩わしい手続きを取ることなく結成することができるのです。そんな労働組合の作り方について、記事にてご紹介して...
その他の関連コラム
-
基本給が低いことによって、労働者側にデメリットはあるのでしょうか。こちらの記事では基本給の概括や、基本給が低いことで受ける影響を、法律の専門家である弁護士監修の...
-
長時間労働やハラスメントなどの労働問題に直面しているにも関わらず、どこに相談すればいいか分からず悩んでいませんか。本記事では京都で労働相談が可能な4つの窓口と専...
-
法律トラブルの解決は、能力・経験・得意分野や人柄などの特徴を見極めた上で、信頼できるに弁護士に依頼しましょう。ポータルサイトを利用して、複数の弁護士を比較して選...
-
長時間労働やハラスメントなどの労働問題に直面しているにも関わらず、どこに相談すればいいか分からず悩んでいませんか。本記事では松戸市で労働相談が可能な4つの窓口と...
-
長時間労働やハラスメントなどの労働問題をどこに相談すればいいか分からず悩んでいませんか。本記事では大田区で労働相談が可能な5つの窓口と専門家を解説しています。本...
-
アルコールに関連して周囲に嫌な思いをさせることはアルコールハラスメント、いわゆる「アルハラ」に該当してしまう可能性があります。本記事では、アルコールによるハラス...
-
長時間労働やハラスメントなどの労働問題に直面しているにも関わらず、どこに相談すればいいか分からず悩んでいませんか。本記事では世田谷区で労働相談が可能な5つの窓口...
-
夏と冬のイベントの1つでもあるボーナス(賞与)。ボーナスの平均額を年代・男女・業種別に紹介。年収が多い企業ではいくらボーナスが支給されているのか。公務員のボーナ...
-
企業が労働基準法に違反した行為をすると罰則が与えられます。以下で労働基準法違反となるのはどういったケースなのか、その場合の罰則はどのくらいになるのかご説明してい...
-
職場や家庭で、差別や虐待、ハラスメントなど人権問題に苦しむ方に向けた相談窓口として、国が運営する「みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)」があります。...
-
解雇予告(かいこよこく)とは会社側が労働者を解雇しようとする場合に、少なくとも30日前に通知なければならない『解雇の予告』です。今回は、解雇予告とはどういったも...
-
長時間労働やハラスメントなどの労働問題に直面しているにも関わらず、どこに相談すればいいか分からず悩んでいませんか。本記事では名古屋市で労働相談が可能な5つの窓口...