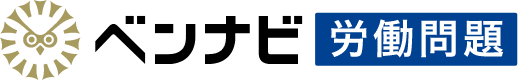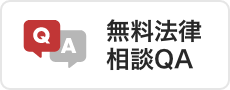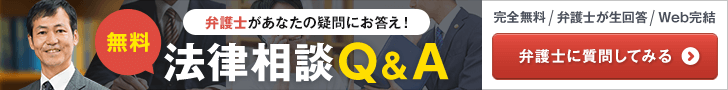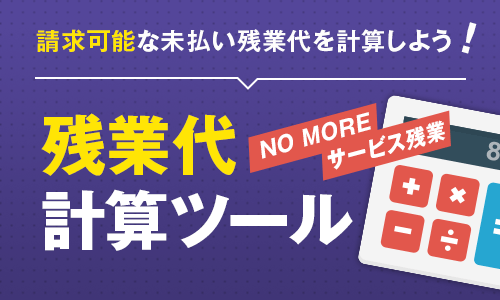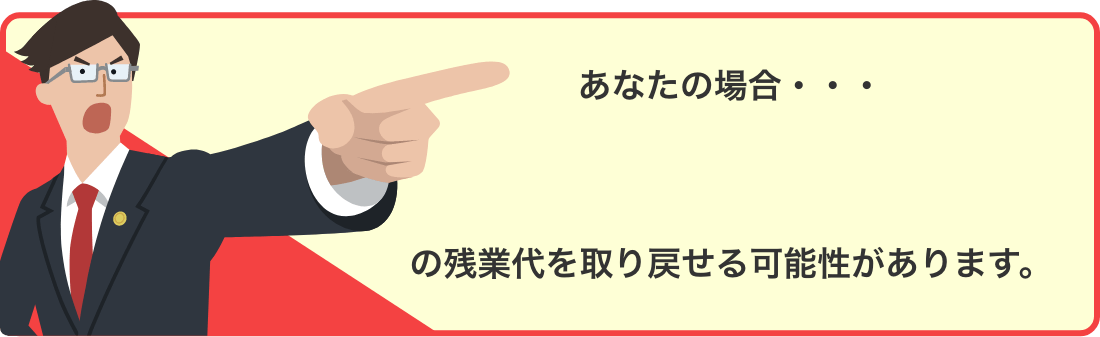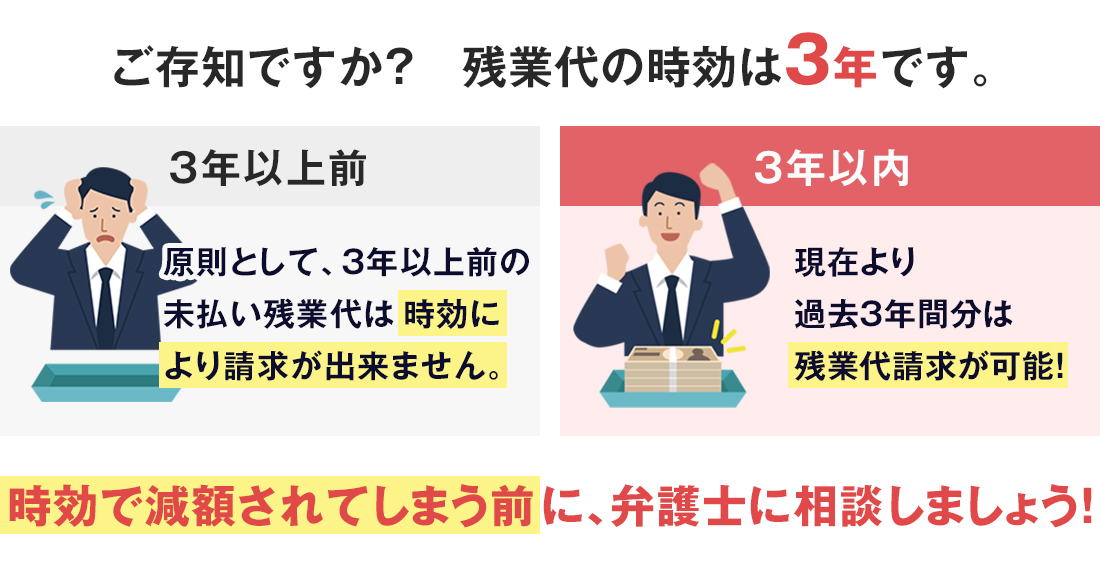社内の問題社員について、対応に苦慮している会社は少なくないでしょう。
自主的に退職してくれればありがたいですが、そう上手くことは運ばず、なんとか辞めさせる方法はないものかと、頭を悩ませているかもしれません。
ご存知の方も多いでしょうが、日本では解雇に対する規制が厳しく、問題社員であろうと、会社を辞めさせるのは難しいといえます。
ただ決して辞めさせられないわけではありません。適切な手順・手続きに則って対処すれば、不当解雇とならずに済みます。
この記事では、問題社員を辞めさせる際に考慮すべきポイントや注意点、具体的な手順などについて解説します。
問題社員を辞めさせたいあなたへ
問題社員を辞めさせたいけど、不当解雇に当たらないか不安で悩んでいませんか?
結論からいうと、適切な手順・手続きに則って対処すれば、従業員を辞めさせても不当解雇とならずに済みます。
もし、不当解雇にならないような形で問題社員を辞めさせたい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします。
弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。
- 解雇の前にできる措置を教えてもらえる
- 解雇理由に不当性がないか判断してもらえる
- 依頼すれば、解雇通知書の作成などを任せられる
- 依頼すれば、訴訟の際の複雑な手続きを任せられる
『企業法務弁護士ナビ』では、不当解雇を得意とする弁護士を多数掲載しています。
無料相談・電話相談など、さまざまな条件であなたのお近くの弁護士を探せるので、ぜひ利用してみてください。
社員を辞めさせるハードルは非常に高い
社員を簡単には辞めさせられないとはいうものの、実際に解雇のハードルの高さを理解している方は、それほど多くはないでしょう。
労働契約法では解雇が認められるのは、客観的にみて合理的な理由が存在し、社会通念上(社会一般の常識で考えた際に)相当な場合に限るとしています。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
引用元:労働契約法第16条
社会一般の常識からからみて合理的な理由があればよいなら、問題社員の解雇も十分可能だろうと思うかもしれません。
ですが、現在の解雇制度においてはこの点を非常に厳しく見ます。
例えば、ある会社の社員が通勤手当を不正受給していたことを理由に解雇を行ったケースでは、懲戒事由には該当しうるが、不正の動機や金額などを考慮すると解雇は重すぎるとして無効の判断がなされました。
参考:光輪モータース事件(東京地裁平成18年2月7日判決)
また、ある大学の教授がハラスメントを理由に解雇をされたケースにおいては、不適切ではあるものの、悪質性が高いとはいい難く、教授が過去に懲戒処分を受けていないことや、反省の意思が見られることなどを考慮すると、懲戒解雇処分は重過ぎるとして無効と判断されました。
参考:国立大学法人群馬大学事件(前橋地裁平成29年10月4日判決)
このように一般的にみて会社に非がないと思われる状況においても、不当解雇と判断される可能性はゼロではなく、むしろ解雇が正当とみなされることのほうが少ないといえるかもしれません。
問題社員を辞めさせる方法は主に二つ
問題社員を辞めさせる場合、おおむね以下のいずれかによって行われます。
この項目では、それぞれの方法の基礎的な知識を確認していきましょう。
退職勧奨
退職勧奨はその名前の通り、社員に自主的に辞めるよう促す方法です。
解雇とは異なり、本人の同意を得ての退職となるため、法律による規制は特になく、比較的自由に行うことが可能です。
例えば解雇の場合、就業規則の定めや解雇予告等が必要となりますが、退職勧奨の場合はこのような規制はありません。
しかし、退職勧奨がある程度自由に行うことができるといっても、度が過ぎれば、退職強要とみなされ違法となる点には注意が必要です。
解雇
解雇とは、使用者による労働契約の一方的な解除のことをいい、以下3つの種類があります。
うち問題社員を辞めさせる際に関係するのは、主に普通解雇と懲戒解雇の2つです。
普通解雇は、懲戒解雇や整理解雇には該当しない、やむを得ない事由があるときに行う解雇のことを言います。
懲戒解雇は、会社の秩序を著しく乱した労働者に対し、懲罰的意味合いで行われる解雇のことです。
どちらの方法をとるにせよ、解雇を行うのであれば相応の理由が必要となり、また就業規則の定めや解雇予告をすることなどが法律で定められています。
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
③ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
引用元:労働基準法第20条
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
引用元:労働基準法第89条
問題社員を辞めさせる際に考慮すべきポイント
前述したように、解雇には厳しい規制がなされており、適切な方法で行わなければ、不当解雇と評価されてしまうかもしれません。
この項目では、問題社員を辞めさせるにあたって、適切に対応するためのポイントを解説します。
就業規則の解雇事由に該当するか
裁判所は就業規則の解雇事由について、限定的に列挙したもの(限定列挙説)と考えています。
どういう意味かというと、就業規則記載の解雇事由以外では、基本的には解雇が認められないということです。
なので、問題社員を解雇する場合は、まず就業規則の解雇事由に該当するかを確認しなければなりません。
なお限定列挙説の捉え方は、普通解雇と懲戒解雇では多少異なります。
普通解雇に関しては、裁判所も特段の事情がある場合は列挙事由以外の解雇も認める余地を残しています。
他方、懲戒解雇については、懲戒処分の有効要件として、懲戒事由をあらかじめ定めておくよう法律の定めがあるため、就業規則に記載のない事由での解雇は認められません。
(懲戒)
第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
引用元:労働契約法15条
解雇制限期間に該当しないか
解雇にあった労働者は再就職ができなかった場合、経済的に困窮する恐れがあることから、以下の期間については、解雇が法律で制限されています。
- 労災休業期間とその後30日間
- 産前産後休業期間とその後30日間
ただし、解雇制限期間であったとしても、
- 打切補償を支払う
- 天災事変その他やむを得ない事由のために事業継続が不可能
のいずれかを満たす場合には解雇することが認められています。
なお、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業継続が不可能」なことを理由に解雇を行う場合は、所轄の労働基準監督署の認定を受けなければなりません。
(解雇制限)
第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
引用元:労働基準法第19条
いきなり解雇を行おうとしていないか
解雇は労働者が被る不利益が大きいことから、一部の例外を除き、段階的な手続きを踏んだうえで行うよう求められています。
段階的な手続きとは、注意や指導、解雇よりも軽微な懲戒処分などです。
要するに解雇は他に解決策がなくどうしようもない場合の最終手段であり、そうなるまでは他の手段で改善を図ってくださいということです
ただし、以下のいずれかに該当するような場合は、いきなりの解雇も認められてはいます。
- 労働基準法第21条に該当する短期雇用労働者
- 天災などのやむを得ない事由により事業継続が不可能となった場合
- 労働者の責に帰すべき事由がある場合
第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
引用元:労働基準法第21条
見てわかるとおり、一般的な解雇で当てはまるケースではありません。なので、不当解雇として訴えたくなければ、段階的に対処を行っていきましょう。
問題社員に会社を辞めてもらうための具体的な手順
問題社員に対してであろうと、辞めさせ方を一歩間違えれば、不当解雇となってしまい、会社がペナルティを負うことになります。
不当解雇として訴えられないためにも、適切な辞めさせ方の具体的な手順を確認していきましょう。
1.現状の把握を行う
問題社員を辞めさせるにあたり、まず行うべきは現状の把握です。
当該社員の問題点、会社がこれまでに行った対応などがわからないことには、今後の方針が決められません。
万が一、誤った情報をもとに対応をしてしまうと、不当解雇につながる恐れがあるので、しっかりと確認しておきましょう。
2.注意や指導を行う
前述したように、問題があるからといって、社員を即解雇することは原則として認められていません。
訴訟に発展した事例においても、注意や指導が不十分であったとして、解雇を無効と判断される企業がたびたび見受けられます。
裁判所からしてみれば、解雇は雇用の継続が困難で、他に対処のしようがない場合の最終手段という位置づけです。
したがって、不当解雇と判断されないためには、注意や指導を十分に行っておく必要があるのです。
3.就業規則を確認する
問題社員を解雇するにしても、軽度の懲戒処分を行うにしても、就業規則に該当事由があることが前提です。
問題社員の態様に一致する該当事由がないのにもかかわらず、正式な処分を下せば違法となってしまう可能性があるので、あらかじめ就業規則を確認しておく必要があります。
また、そもそも就業規則の内容が社員に対して周知されており、閲覧できる状態になっているかどうかも重要なポイントです。
就業規則がいつでも閲覧できる状態になっておらず、社員への周知が行われていない場合、就業規則そのものが無効となってしまい、それに基づく懲戒処分等も無効となる可能性があるので注意しましょう。
4.解雇よりも軽微な懲戒処分を行う
注意や指導等を繰り返しても、問題社員に改善が見られないようであれば、必要に応じて懲戒処分を行いましょう。
ただこの段階でも原則は軽い処分から。問題行為の程度にも寄りますが、懲戒処分の中では軽い部類に入る戒告から行うのが無難でしょう。
仮に問題行為に対して重すぎる懲戒処分を与えてしまうと、裁判で争った際に無効となる可能性があります。
5.退職勧奨を行う
解雇については厳しい規制がある一方で、退職勧奨は特に法律で制限は設けられていません。
というのも、退職勧奨はあくまでもお願いであって強制はできず、最終的な判断は社員自身に委ねられているためです。
したがって、退職勧奨で会社を辞めてもらえば、不当解雇の心配をする必要はありません。
ただ前述したように、あくまでも退職勧奨はお願いであるため強制はできず、無理やり同意させようとすれば退職強要で違法となります。
退職強要とならないためには、あまり早い段階では退職勧奨を行わず、解雇も視野に入るタイミングほどで、交渉を持ちかけてみるとよいでしょう。
6.解雇を行う
問題社員に対して改善を促そうと散々対処してきたが、どうにもならないような状況に至ってはじめて解雇が有効と認められる可能性が高くなります。とはいえ、まだ焦ってはいけません。
まずは幹部や問題社員の上司に解雇を行う旨を伝え、情報共有しておきましょう。情報共有ができていないと、引継ぎや連絡で不備が生じるかもしれません。
また、解雇通知書の作成も作成しておく必要があるでしょう。
解雇予告も忘れてはいけません。原則として解雇の際は少なくとも解雇日の30日以上前に通知しなくてはならないと定められています。
ただし解雇予告手当を支払う場合は別です。解雇日になるまでの間、問題社員の行動に不安があるなら解雇予告手当を支払うことを検討したほうがよいでしょう。
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
引用元:労働基準法第20条
なお懲戒解雇の際には法律の定めはありませんが、不当解雇のリスクを減らすため、弁明の機会を設けることを忘れないようにしてください。
問題社員を辞めさせる際の注意点
問題社員がいることで、他の社員も相応の苦労がかかっている点を踏まえると、適切な対処ができれば、社内環境の好転が期待できます。
他方で、理不尽な理由での強引な解雇を行えば、他の社員も明日はわが身かもしれないと、会社を辞める決断をするかもしれません。
違法だからというだけでなく、会社の今後を考えた上でも解雇は適切かつ透明性のある手続きで行うのが一番です。
したがって、社員の会社に対する信頼を手放さないためにも、適切な手順で解雇を進めていきましょう。
問題社員を辞めさせる場合は専門家(弁護士)の力を借りるべき理由
解雇手続きにおいて企業に求められる対応は必ずしも一定ではありません。
問題社員の態様や企業の置かれた状況など、さまざま事情を総合的に考慮して判断がなされるため、解雇案件の内容ごとに会社のとるべき対応方法も変わるといえます。
一律で対処するのが難しい事案を社員だけで対応をするのは至難であるため、弁護士の力を借りたほうがよいでしょう。
弁護士でもどの程度まで対処を尽くせば解雇が有効となるのかを判断するのは難しいですが、これは明らかにダメだという対応は容易に判別がつきます。
弁護士の指導やアドバイスのもと、リスクを最小限に抑えた対応をしていけば、不当解雇となる可能性はかなり抑えられるでしょう。
まとめ
解雇したい相手が問題社員であろうと、基本的に厳しい解雇規制を免れて対処する術はありません。会社は問題社員に解雇ありきで対処するのではなく、改善を促す対応をしていく必要があります。
不当解雇として訴えられたくないのであれば、適切な手順で解雇手続きを進めていきましょう。
- 現状の把握を行う
- 注意や指導を行う
- 就業規則を確認する
- 解雇よりも軽微な懲戒処分を行う
- 退職勧奨を行う
- 解雇を行う
ただ適切な手順で解雇を進めていたとしても、どこまで手を尽くせば有効となるかはケースごとに異なります。
より不当解雇のリスクを抑えたいのであれば、弁護士に依頼したほうが無難でしょう。
会社に顧問契約を結ぶ弁護士がいないのであれば、人事労務に精通した弁護士を探すことをおすすめします。
『企業法務弁護士ナビ』では問題社員の解雇など、人事労務に強い弁護士を掲載しています。
無料相談可能な弁護士も掲載しているのでまずはお気軽にご相談を。