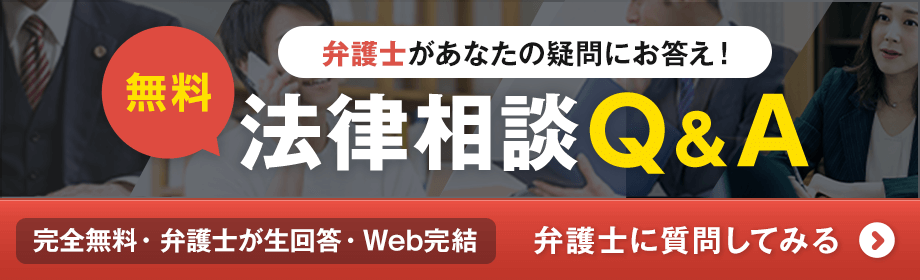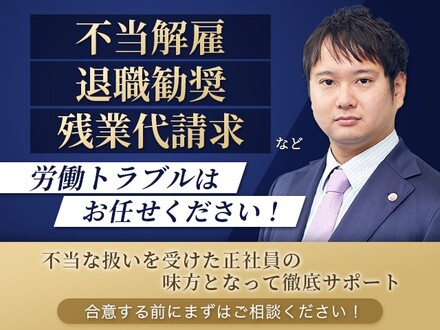正社員として働いている方のなかには、なんらかの理由でできるだけ早急に退職したいという方もいるでしょう。
結論からいうと、正社員の即日退職は、原則として認められません。
しかし、例外的に正社員の即日退職が認められることもあります。
本記事では、正社員が実質的に即日退職する方法やその流れを解説します。
弁護士への依頼以外にも、即日退職のサポートを受ける方法は存在します。
ぜひ本記事を参考にしてください。
正社員の即日退職は、原則として認められない
冒頭でも解説したように、正社員の即日退職は原則として認められません。
これは民法627条に基づき、雇用期間が定められていない場合でも、退職は解約申し入れから2週間後に有効となるからです。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
正社員はこのルールに該当するため、退職するためには最低でも2週間前に会社に申し入れる必要があります。
また、会社によっては「退職予定日の1ヵ月前までに申し出ること」といった規定がある場合もあるでしょう。
退職手続きをスムーズに進めるためにも、事前に就業規則を確認しておくことが重要です。
例外的に正社員の即日退職が認められることもある
正社員の即日退職が認められるかどうかは、「やむを得ない理由(事由)」であるかによって異なります。
ここでは、「やむを得ない理由」に該当する理由や注意点について説明します。
「やむを得ない理由(事由)」があれば即日退職が認められる
民法第628条によれば、やむを得ない理由がある場合には、契約社員やパートなどの期間の定めがある雇用契約でも直ちに解除できます。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
具体的な「やむを得ない理由」には、ストレスや過重労働による体調不良、職場でのハラスメント、賃金未払い、上司による強引な引き止めなどが含まれます。
「やむを得ない理由」に該当する理由
- 肉体的・精神的な病気のため、継続的に働くことが難しくなった
- 要介護の親や病気の子どものケアに専念する必要がある
- 職場の上司や同僚からセクハラやパワハラを受けて困っている
- 上司から法令に違反する業務を命じられた
- 未払いのままになっている賃金や残業代がある
これらの状況に該当する場合、2週間前の退職意思表示は不要です。
労働者には退職の権利があり、会社はこれを拒否できません。
もし退職が難しい場合や会社側が取り合ってくれない場合には、退職代行サービスの利用が勧められます。
また、家族の看病や介護が必要で通勤が困難になった場合も即日退職が可能です。
やむを得ない理由で即日退職する際の注意点
ここでは、やむを得ない理由で即日退職をする際の注意点について説明しています。
会社から損害賠償請求される可能性がある
民法628条では、「やむを得ない理由」で退職する場合について規定しています。
もし「やむを得ない理由」がない場合、相手方(会社)に対して損害賠償の責任を負うことがあります。
具体的には、即日退職によって業務に支障が生じ、損害が発生した場合などが該当します。
社員が突然の病気や家族の不幸など、やむを得ない理由で退職を希望する場合、その旨を会社に適切に報告して手続きを進めることが重要です。
会社への報告が不十分だったり、無断で会社を去ったりすると、その行為が会社に損害を与える可能性があります。
具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 重大なプロジェクトを担当していた場合
突然の退職によりプロジェクトが遅延し、取引先に損害を与えた場合、その損害に対する賠償責任が生じることがあります。 - 欠員による業務の停滞
退職者の業務を他の社員がカバーできず、業務全体が停滞することで会社の売上や信用に影響を与える場合も、損害賠償の請求がおこなわれることがあります。 - 特定のスキルや資格が必要な仕事
たとえば、特定の資格を持つ社員が急に退職し、その穴を埋めることが困難な場合、会社はその期間中に生じた損害について賠償を求めることがあります。
以上のような事態を防ぐためにも、退職の際には、可能な限り早く上司や人事部に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。
退職前にはできる限り担当業務の引き継ぎをおこない、会社に対して誠実に対応することが望まれます。
さらに、退職にともなうトラブルを避けるためには、労働契約書や就業規則をよく確認し、法的なアドバイスを求めることも検討するとよいでしょう。
診断書の提出書を求められる場合もある
病気やけがを理由に即日退職する場合、医師からの診断書が必要なことがあります。
診断書の発行には通常2週間ほどかかるため、退職希望日から逆算して早めに準備を進めることが重要です。
診断書を依頼する際には、その使い道を事前に医師に伝えておくとスムーズでしょう。
また、診断書の内容によっては会社の人事部や上司と早急に相談し、退職手続きを円滑に進めることが求められます。
可能であれば、医師との診察日時を早めに設定し、診断書をスムーズに取得できるように調整しましょう。
医師に直接事情を説明し、迅速な対応をお願いすることもひとつの手段です。
医師によっては、緊急性を理解して対応してくれる場合もあります。
さらに、会社側とのコミュニケーションも重要です。
診断書の提出が遅れる場合や何らかの理由で即日退職が難しい場合は、誠意を持って会社に説明することが求められます。
その際、どうしても即日退職が必要である理由や、今後の治療計画などを具体的に伝えると理解を得やすくなるでしょう。
無断欠勤を繰り返していると懲戒解雇になる場合もある
即日退職を希望する方の中には、職場のストレスが原因で精神的に追い込まれている場合が多いでしょう。
しかし、無断欠勤を繰り返すと懲戒解雇のリスクがあります。
懲戒解雇は最も重い処分で、その後の転職活動にも悪影響を及ぼす可能性も否定できません。
懲戒解雇を受けた事実は経歴として残り、一般的に転職時に不利になる傾向があります。
退職理由を偽ると経歴詐称に当たるため、正直に話す義務があります。
無断欠勤中の場合でも、まずは上司や同僚に連絡し謝罪することが重要です。
即日退職を希望する場合の具体的な手順と注意点は、以下のとおりです。
|
①事前準備 |
・退職理由を明確にする ご自身にとっての退職理由を再確認し、上司や人事担当者に説明できるように準備しましょう。 家庭の事情や健康問題など、正直かつ具体的な理由を述べることが大切です。 |
|
・書面での退職願の作成 退職願は正式な書類であり、口頭だけでなく書面で提出することが望ましいです。 書類には「即日退職希望」と明記し、理由とともに提出日を記載しましょう。 |
|
|
②上司への相談 |
・直接のコミュニケーション まずは直属の上司に対して、即日退職の希望を伝えます。 対面が難しい場合は電話やメールでも構いませんが、できるだけ誠意を持って伝えることが大切です。 |
|
・フィードバックの受け止め 上司からの質問やフィードバックを冷静に受け止め、可能な限り協力する姿勢を見せるとよいでしょう。 |
|
|
③人事部門との面談 |
・正式な手続き 上司の了承が得られたら、人事部門と面談を行い、正式な退職手続きを進めます。 必要書類の提出や最終給与の確認、引継ぎのスケジュール等について調整します。 |
|
・社内規定の確認 即日退職が可能かどうか、会社の規定や労働契約を確認しておくことも重要です。 場合によっては、退職日の調整が必要なこともあります。 |
|
|
④引継ぎと整理 |
・引き継ぎの準備 退職日に向けて自分の担当業務を整理し、後任者に適切に引き継ぐ準備をします。 これは後々のトラブルを避けるためにも重要です。 |
|
・社員証や備品の返却 退職時には社員証や会社から支給された備品を返却する必要があります。 |
|
|
⑤書面の確認 |
・離職票の取得 退職後の失業手当の受給に必要な離職票を人事部門から受け取ります。 これには少し時間がかかる場合もあるので、早めに確認しておくと安心です。 |
|
・残りの有給休暇の確認 未消化の有給休暇がある場合は、その扱いについても事前に確認しましょう。 有給休暇の消化が認められない場合もあります。 |
即日退職は心身の健康を優先する重要な決断ですが、可能な限り円滑に進めるためには、誠実な対応と適切な手続きが不可欠です。
上記のステップを踏んで、慎重に進めるようにしましょう。
正社員が実質的に即日退職する(退職日まで出勤しない)方法
法律上、基本的には即日退職は認められず、やむを得ない理由がある場合に限ります。
しかし、退職日の2週間前に通知するルールは会社の準備期間を確保するためのものであり、会社が同意すれば即日退職は可能です。
有休消化をして退職日まで出勤をしない
退職の際、雇用期間の定めがない場合は、退職希望日の2週間前までに退職意思を伝える必要があります。
その後、在籍し続ける必要がありますが、出勤は義務ではありません。
つまり、有給休暇を利用することで、実質即日退職が可能となるのです。
ただし、この方法を活用する場合は、事前に残りの有給休暇が2週間分以上あるかを確認しましょう。
この方法は無期雇用のパート・アルバイト、契約社員の方にも適用されます。
退職日まで欠勤扱いにしてもらう
残りの有給が2週間に満たない場合、退職日までの間を欠勤扱いにする方法があります。
欠勤も有給と同様に「会社を休んでいる」とみなされるため、法律で定められた2週間の在籍期間を満たします。
会社と相談して欠勤扱いが承諾されれば、この方法により実質的に即日退職が可能です。
会社の合意が得られるのであれば、有給消化などしなくても即日退職が可能
もし消化できる有給休暇がなくても、会社との合意があれば即日退職が可能です。
期間の定めがない雇用契約では、退職の意思を伝えたあとも2週間必要ですが、会社との間で合意が成立すれば即日退職できます。
この合意解約では、有給休暇や欠勤を使う必要がありません。
14日間の欠勤後に退職する場合と合意解約による即日退職では業務への影響に差がないため、会社が合意する可能性もあります。
合意解約のためには会社との交渉が必要なケースもあるため、その場合は弁護士のサポートが有効です。
正社員が実質的に即日退職する際の流れ
ここでは、正社員が実質的に即日退職する際の流れについて解説します。
1.まずは有給の残日数を確認する
やむを得ない理由がある場合は即日退職が可能であるものの、適切な手続きを踏まないとトラブルのリスクがあります。
可能であれば退職までの期間、有給休暇を使いながら手続きを進めるのが理想的です。
退職の2週間前に連絡する必要があり、有給休暇が残っていればその間出社せずに退職することができます。
残りの有給休暇日数は勤怠管理システムや給与明細で確認するか、総務課や人事労務課にたずねましょう。
2.上司に退職の意向を伝え、退職届を提出
上司に退職の意向と翌日から有給休暇を取得したいことを伝え、退職届を提出します。
退職届の書き方はインターネット上に公開されている作成例を参考にしたり、無料テンプレートを利用したりすることができます。
退職届はメールで受け付ける会社もありますが、基本的には上司に直接手渡しするのがマナーです。
退職届の提出後は、上司や人事部との面談がおこなわれることが多いです。
この面談では、退職の理由や今後の手続きについて話し合います。
退職理由については正直に伝えることが大切ですが、トラブルを避けるためにも誠実な対応を心がけましょう。
その後、自分の業務内容をリストアップし、誰に何を引き継ぐかを上司と相談します。
その際、ご自身が退職した後も業務が滞りなく進行するために、引き継ぎ資料やマニュアルの作成を求められるでしょう。
3.退職手続きをする
退職までに残っている有給休暇の日数を会社の人事担当者に確認し、その範囲内で休暇を取得します。
有給休暇の申請は、通常の手順に従っておこないますが、退職を前提とするため、必要に応じて上司や人事部に直接確認を取ることが望ましいでしょう。
有給休暇を取得している間も、会社からの連絡がある場合には、速やかに対応できるようにしておきます。
特に退職手続きに関連する書類や、退職後の福利厚生(例:健康保険の任意継続や年金手続きなど)に関する質問がある場合に備えて、連絡手段を確保しておくことが重要です。
もし有給休暇が不足し、全て消化できない場合は、その部分について欠勤扱いとなります。
この場合、欠勤扱いの期間については賃金が支給されませんので、事前に欠勤期間とその賃金への影響について確認しておきましょう。
また、退職にあたり会社に返却が必要な物品についても整理しておきます。
具体的には、以下のようなものがあります。
- 社員証
- 保険証
- 名刺
- 鍵
- 作業服
- 会社支給の携帯電話
- 業務資料やマニュアル
これらを退職日までにまとめて返却するようにします。
このとき、返却物のチェックリストを作成し、漏れがないようにすることも大切です。
最終的には、退職日に以下の書類を会社から受け取ります。
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 離職票
これらの書類は、退職後の手続きや転職活動の際に必要となるため、大切に保管してください。
また、離職票は退職後に届く場合もあるので、その点についても会社の人事部に確認し、手続きの進捗を把握しておきましょう。
正社員が即日退職するときの言い方・退職の伝え方
即日退職を希望する場合、やむを得ない理由があるなら正直に伝えましょう。
特別な理由がない場合は有給休暇を利用し、不足している場合は欠勤扱いにします。
このとき、退職の意思と理由を伝えることが重要です。
会社は即日退職を避けたがるため、時期の引き延ばしを提案される可能性が高いものの、一方的な即日退職はトラブルの原因となります。
多くの会社では就業規則に退職の予告期間が定められており、これに基づいて退職手続きを進めることが求められます。
これを無視して即日退職を申し出ると、会社との間にトラブルが発生する可能性があります。
そのため、正当な理由がある場合でも、できる限り会社の規定に従うよう努めることが重要です。
また、即日退職を申し出る際には、退職願にしっかりと理由を記載することも大切です。
たとえば、「◯月◯日より体調不良が続いており、これ以上業務を続けることが困難なため、誠に勝手ながら即日退職を希望いたします」などと、退職願はできる限り具体的かつ簡潔に、事実に基づいて書くようにしましょう。
たとえば、
以下は、即日退職をメールで伝える際の文例です。
|
件名: 退職のご連絡 ○○部長 おつかれさまです。○○部の△△です。 突然のご連絡となり大変恐縮ですが、私の体調不良により、業務を続けることが困難となりました。 医師の診断を受けた結果、即日での療養が必要と判断されました。 そのため、誠に勝手ながら本日をもって退職させていただきたく存じます。 多大なるご迷惑をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。 なお、残りの有給休暇を本日より消化させていただくようお願い申し上げます。 短い間でしたが、お世話になりましたことに感謝しております。 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 △△ |
最終的には、自己の健康や家庭の事情を最優先に考え、必要なサポートを受けながら退職手続きを進めることが大切です。
退職後の円満な関係を保つためにも、誠意を持って対応することが求められます。
ご自身で会社を説得するのが難しい場合は、法律事務所や労働組合が運営・提携する退職代行サービスに依頼しましょう。
正社員が実質的に即日退職する際の注意点
ここでは、正社員が実質的に即日退職をする際の注意点について説明しています。
退職の意向は退職日の2週間前までに伝える
労働者が退職を申し出てから2週間経過すれば、その時点で労働契約が終了します。
そのため、労働者がその後出勤しなくても損害賠償を請求することはできません。
労働者の一方的な行為でも退職は成立し、法律上使用者の同意は必要ありません。
民法では使用者による一方的な解雇は法的に規制されている一方、労働者が一方的に退職することを規制する法律はないため、労働者は退職の申し出から14日後に一方的に退職できます。
欠勤の場合、給与はもらえない
退職日までの期間を欠勤扱いにすると賃金は支払われません。
会社と従業員は労働提供と賃金支払いの契約を結んでいるため、欠勤は従業員の義務違反となり、賃金は発生しません。
しかし、従業員の健康やライフワークバランスを保つために、有給休暇が一定条件のもとで付与されます。
退職日まで欠勤の場合、その日数分の賃金が差し引かれるため、生活資金に困らないよう転職準備や資金計画をきちんと立てて退職意思を伝えることが重要です。
退職を考える際には、以下のポイントをしっかりと確認し、準備を進めることが大切です。
1. 退職意思の伝え方
退職意思を伝える際はまず、上司や人事部門に口頭で相談し、その後正式な退職願を提出するのが一般的です。
礼儀を重んじ、適切な方法で伝えることが重要です。
2. 退職時期の調整
退職のタイミングを見極めることも重要です。
会社の繁忙期やプロジェクトの進行状況を踏まえ、円満退職を目指しましょう。
可能であれば、後任者への引き継ぎ期間を確保することが望ましいです。
3. 有給休暇の消化
退職前に、有給休暇を全て消化することも考慮に入れるべきです。
有給休暇の消化に関しては、会社の規定に従い、早めに申請をおこなうことが求められます。
4. 賃金と退職金の確認
欠勤が賃金に影響するため、退職前の賃金計算や退職金の有無について確認しておくことが重要です。
また、退職後の生活資金を確保するためにも、賃金や退職金の支払いスケジュールを確認しましょう。
5. 社会保険や年金の手続き
退職後の健康保険や年金の手続きを忘れずにおこなう必要があります。
新しい職場での社会保険加入手続きや、国民健康保険への切り替え、国民年金への加入など、必要な手続きを把握しておきましょう。
6. 転職活動の準備
転職を考えている場合は、現職中に転職活動を進めることが望ましいです。
履歴書や職務経歴書の準備、転職先のリサーチ、面接対策など、転職活動を計画的におこないましょう。
7. 貯蓄計画の立て直し
退職後の収入源を確保できるまでの間の生活費を考慮し、貯蓄計画を見直すことも重要です。
必要な生活費や急な出費に備え、十分な貯蓄を確保することが望ましいです。
8. 家族との話し合い
退職は個人だけでなく家族にも影響を及ぼすため、家族と話し合いながら進めることが大切です。
家族の理解と協力を得ることで、スムーズに退職を迎えることができるでしょう。
正社員で即日退職したいなら退職代行の利用もおすすめ
即日退職は会社にとってリスクが高く、上司や同僚から引き止めにあう可能性があります。
また、上司から怒られることを不安に感じる人も多いでしょう。
そのような場合におすすめなのが、退職代行サービスです。
退職の連絡や有効消化・退職日の交渉を任せられる
退職代行サービスの一部は有給休暇や退職日に関する交渉も依頼でき、即日退職を希望する方にとって便利です。
ただし、会社と交渉できるのは法律事務所や労働組合が運営または提携している場合に限られます。
民間企業が交渉をおこなうのは違法ですが、弁護士や労働組合と提携していれば問題ありません。
民間企業が提供する退職代行サービスは比較的リーズナブルで、費用を抑えたい方におすすめです。
退職代行サービスを利用することによって、精神的な負担が軽減されるというメリットもあります。
退職を直接伝えることに抵抗を感じる方や、職場での人間関係に悩んでいる方にとっては、大きなサポートとなるでしょう。
思い立った当日に対応してもらえるところもある
退職代行サービスには24時間対応可能なものもあり、最短で当日の朝に相談・依頼し、当日中に退職できることもあります。
ただし、サービスの実行は料金の入金確認後となり、早朝はATMが稼働していないため銀行振込だと退職連絡が会社の始業時間に間に合わない可能性があるでしょう。
そのため、当日朝に即日退職を目指す場合はクレジットカード決済を選ぶことが推奨されます。
退職代行サービスの担当者は、利用者の勤務先に退職の意思を伝えるだけでなく、引継ぎの方法や最終出勤日の相談なども一手に引き受けます。
これにより、利用者は直接会社とやり取りをする必要がなくなり、精神的な負担が大幅に軽減されます。
正社員の即日退職におすすめの退職代行サービス3選
ここでは、正社員の即日退職におすすめの退職代行サービスについて説明しています。
1.退職代行Jobs|有休消化の交渉も任せられる!
退職代行サービスJobsは、即日退職や有給休暇消化の交渉を可能にし、全国規模での対応実績がある退職代行サービスです。
弁護士監修のため、安心して退職を進めたい方におすすめです。
さらに、有給休暇の無料申請や無料の求人サービスによる転職サポートも提供しています。
実際に利用した方からは、職場での人間関係に問題があり、退職の相談をするたびに引き止められていたが、Jobsの代行サービスを利用してスムーズに退職できたとの声があがっています。
また、過酷な労働環境で悩んでいた別の利用者からは、Jobsのスタッフが詳細にヒアリングし、退職日を慎重に決定してくれたことで、安心して退職できたとの声が寄せられています。
2.退職代行ガーディアン|スピーディーな対応で安心!
運営元が公的機関の認証をもつ労働組合の退職代行ガーディアンは、迅速な対応と高い交渉力で即日退職を実現する退職代行サービスです。
有給休暇の交渉も可能で、利用者からは、迅速な対応やスムーズなやり取りへの感謝の声が寄せられ、退職が難しい状況でも精神的に大きな助けとなったと評価されています。
3.退職代行OITOMA(オイトマ)|業界最安値なのに丁寧な対応が魅力
退職代行OITOMA(オイトマ)は業界最安値の2万4,000円で24時間対応、返金保証付きです。
労働組合が運営しているため、会社との交渉も可能です。
利用者は、相談回数無制限で電話での相談も可能で、迅速かつ適格なサポートに満足しています。
ほかの退職代行サービスと比べて低価格であり、全額返金保証もある点が好評です。
このサービスを利用した結果、終始安心して退職手続きを進めることができたと報告されています。
正社員の即日退職についてよくある質問
正社員の方が即日退職するにあたり、いくつか疑問が生じることもあるでしょう。
ここでは、正社員の方が即日退職するにあたってよくある質問を紹介します。
正社員の即日退職は違法ですか?
違法性について、正社員は退職の2週間前に申告が必要であり、理由なく突然仕事を辞めることは不利です。
正社員とは期限の定めがない社員を指し、退職には事前の退職届が法的にも重要です。
パワハラで悩む方が即日退職を希望する気持ちは理解できますが、原則として即日退職が認められるわけではありません。
パワハラの認定には時間がかかるため、一方的に即日退職をすることは避けるのが無難だと考えらえます。
即日退職をする旨は電話で伝えてもよいでしょうか?
即日退職の際には記録を残すことが重要です。
電話での退職申し出が認められる企業もありますが、のちに無断欠勤として扱われ損害賠償を請求されるリスクもあります。
「言った、言わない」のトラブルを避けるためにも、メールや正式な退職届で証拠を残しておくことが推奨されます。
これは、口頭で伝えた場合、特に訴訟に発展した際に証拠がないと個人が不利になる可能性が高いからです。
このとき、即日退職を希望する理由や背景を説明する文書もあわせて作成するとよいでしょう。
書面でのやり取りを通じて、双方にとって納得のいく形での退職が実現する可能性が高まると考えられます。
いわゆる「バックレ」にリスクはありますか?
退職は雇用契約の終了行為であり、一方のバックレは雇用契約が続いているにもかかわらず仕事に来ないことをいいます。
バックレによって生じた損害はその本人の責任となり、最悪の場合、損害賠償請求されるリスクもあります。
たとえ上司のハラスメントが理由であっても、バックレによる損害とは別問題です。
このことからも、バックレは絶対に避けるべきでしょう。
嘘をついて即日退職をしてもよいでしょうか?
退職する際にやむを得ない理由であっても、嘘をつくことは絶対に避けるべきです。
たとえば、親の介護を理由に退職した後にすぐ転職すると、信頼を損ねるだけでなく、場合によっては損害賠償を請求されるリスクもあります。
退職は雇用契約の破棄に当たるため、嘘をつくことはモラルの問題だけでなく、法的リスクもともないます。
そのため、退職の理由についてはできるだけ正直に、そして適切な方法で伝えることが重要です。
たとえば、「スキルアップのために新しい環境でチャレンジしたい」「家庭の事情で勤務時間の調整が難しくなった」など、自身の状況を率直に説明することが求められます。
これらのような理由であれば、会社からの理解を得やすく、円満な退職が実現しやすくなると考えられます。
また、退職の意向を伝える際には、できるだけ早めに上司や人事部に相談し、適切な手続きを踏むことが大切です。
これにより、会社側も後任の手配や業務の引き継ぎがスムーズに進行するため、周囲に対する影響を最小限に抑えることができます。
また、会社に対して誠実な態度を示すことで、自分自身の信用を保ち、将来的なキャリアにもプラスとなるでしょう。
さいごに|トラブルなく即日退職をしたいなら弁護士に相談
正社員の即日退職は、原則として認められませんが、例外的に正社員の即日退職が認められることもあります。
もし直接やり取りをすることに不安を感じる場合は、退職代行サービスの利用も有効です。
退職代行サービスには24時間対応可能なものもあり、最短で当日の朝に相談・依頼し、その日のうちに退職できることもあります。
ご自身に合った退職方法を探して、スムーズに退職できるよう心がけましょう。
なお、ベンナビ労働問題では、労働問題を得意とする弁護士も多数掲載しています。
相談分野や無料法律相談ができるかどうかでも弁護士を探せるので、ご自身に合った弁護士を見つけてみてください。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

【不当解雇・残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
 この記事の監修
この記事の監修

東日本総合法律会計事務所

パワハラに関する新着コラム
-
正社員の即日退職は、原則として認められません。しかし、例外的に正社員の即日退職が認められることもあります。退職代行サービスの利用も有効です。本記事では、正社員の...
-
退職代行ヤメドキの評判を知りたいと思っていませんか?本記事では退職代行ヤメドキの良い評判・悪い評判を紹介します。また、退職代行ヤメドキの特徴や注意点、利用に適し...
-
パワハラ被害を受けていて、在職時はその余裕がなかったものの、退職してから被害を訴えたいと考えることもあるでしょう。本記事では、退職後にパワハラ被害を訴えられるこ...
-
職場や家庭で、差別や虐待、ハラスメントなど人権問題に苦しむ方に向けた相談窓口として、国が運営する「みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)」があります。...
-
職場のハラスメントに悩んでいる場合、誰かに相談することで解決の糸口がつかめるうえに心も少しは晴れるでしょう。本記事ではハラスメント行為に悩んでいる場合の相談窓口...
-
労働者には退職の自由が認められており、「会社を辞めれない」「辞めさせてもらえない」ということはありません。しかし、状況によって取るべき対応は異なるため、対処法を...
-
仕事を辞めたいと思っていても、家族は上司に言えないで悩んでいませんか?怖い上司や支えてくれる親に辞めたいと言えずに悩んだときは、まず辞めたい原因を考え直して見ま...
-
自身の部下からパワーハラスメントを受ける「逆パワハラ」が起きてしまった場合について、適切な対処方法を解説していきます。また、どのような被害を受けていると逆パワハ...
-
本記事では、パワハラについて無料相談ができる窓口と、どの窓口に相談すべきかをわかりやすく解説します。「パワハラを本気でどうにかしたい」という方は、ぜひ参考にして...
-
パワハラを訴えたい場合に録音データ・写真・メール・SNS・メモ・同僚の証言など、どんな証拠が有効になるのかを紹介。パワハラの訴訟に至るまでの流れ、訴えることのメ...
パワハラに関する人気コラム
-
パワーハラスメントの定義とは何かを解説!パワハラには6つの種類があるとされますが、法律上定義や意味を解説する項目はありません。ただ、労働者への嫌がらせ行為は違法...
-
上司のパワハラは労働問題の中でも比較的多いトラブルのひとつです。長時間労働や嫌がらせは違法になる可能性が高い為、正しい知識を身につけた上で中止交渉をすれば解決す...
-
パワハラを受けた方にとっては理不尽で許し難いものであり、パワハラをした相手に何か報復したいと考える方もいるでしょう。そこで今回は、パワハラの訴え方と訴える前に考...
-
過労死ラインとは労災給付の基準であり、月に80〜100時間を超える労働は深刻な健康障害を引き起こす可能性が高いとして、抑制する取り組みが広まっています。この記事...
-
今回は、パワハラに悩まれている方の最終手段とも言えるパワハラでの訴訟の事態と、パワハラで訴訟を起こす際の手順、慰謝料請求をするための相場、請求方法を解説していき...
-
この記事では、労働基準監督署でパワハラの相談をして解決できることや、パワハラ問題の解決フローについて紹介します。
-
長時間労働による過労死は緊急を要する社会問題です。長時間労働を強いられているニュースをよく耳にしますが、他人事ではない働き方をしている方も多いでしょう。そこで、...
-
本記事では、パワハラで労災認定を受けるための条件や手順などを解説します。パワハラを受けていて悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
-
仕事を辞めたい、鬱(うつ)になりそうと悩んでいる方は少なくないでしょう。うつ病は単なる甘えだと言われてしまうこともありますが、自分を追い詰めてしまう前に、休職や...
-
退職までの手続きを徹底解説!大企業の終身雇用が崩れ始める中、退職と転職は身近なものになってきています。昨今の新型コロナウィルスの影響で突然解雇を言い渡される方も...
パワハラの関連コラム
-
中小企業も2022年4月から施行されるパワハラ防止法(労働施策総合推進法)とは何かをわかりやすく解説。規制している内容、パワハラの定義や境界線、事業主が講ずべき...
-
ハラスメントは特殊な事例ではなく誰もが被害を受ける・与える可能性がある問題です。この記事では、ハラスメントの定義や種類、関係する法律、被害に遭った際の対応方法相...
-
公益通報者保護法により設置が求められる内部通報制度の概要について説明。内部告発との違いは?労働者が内部通報を利用するメリットや実際に通報される内容、利用方法につ...
-
正社員の即日退職は、原則として認められません。しかし、例外的に正社員の即日退職が認められることもあります。退職代行サービスの利用も有効です。本記事では、正社員の...
-
この記事では、労働基準監督署でパワハラの相談をして解決できることや、パワハラ問題の解決フローについて紹介します。
-
本記事では、パワハラについて無料相談ができる窓口と、どの窓口に相談すべきかをわかりやすく解説します。「パワハラを本気でどうにかしたい」という方は、ぜひ参考にして...
-
退職までの手続きを徹底解説!大企業の終身雇用が崩れ始める中、退職と転職は身近なものになってきています。昨今の新型コロナウィルスの影響で突然解雇を言い渡される方も...
-
自爆営業は、労働法に違反している恐れがあり、民事上も損害賠償の対象になる可能性があります。この記事では、自爆営業の違法性や断り方、対処法などについてご紹介します...
-
外部相談窓口の役割や設置の目的について解説!労働者が内部通報窓口ではなく外部通報窓口を利用するメリットはどんなところにあるのか。実際に外部通報窓口を利用する要件...
-
賃金を支払わないで労働をさせるサービス残業は、労働基準法に違反する行為です。しかし、実態としては多くの方がサービス残業をしている状況です。今回はサービス残業を拒...
-
ハラスメントの被害にあった場合の通報窓口を設置すべき理由やメリットは?どんなハラスメントを受けた場合に利用できるのか。通報があった場合に企業がすべき対策も解説し...
-
今回は、パワハラに悩まれている方の最終手段とも言えるパワハラでの訴訟の事態と、パワハラで訴訟を起こす際の手順、慰謝料請求をするための相場、請求方法を解説していき...