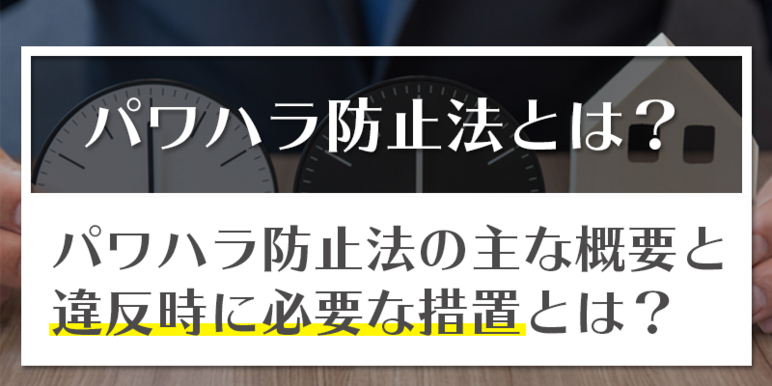
パワハラ防止法とは、正式名称を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(略称:労働施策総合推進法)といい、かつての雇用対策法ですが、2019年5月の改正でパワハラ防止のための雇用管理上の措置が義務づけられたことで、パワハラ防止法と呼ばれるようになりました。
法改正にともない、厚生労働省はいわゆる「パワハラ指針」として、事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して、雇用管理上講ずべき措置等についての指針も公表しています。パワハラ防止法により「パワハラはだめだよ」と法律が明確に述べたことになり、「パワハラの定義」も整理され、不明確な部分は減ったといえます。
経営者・労働者を問わずパワハラの知識を深めて防止に努めることが義務化されたため、これまで無意識にあるいは悪意的になされてきたパワハラが減ると期待されています。
一方で、パワハラは適切な教育・指導との線引きが難しい側面があります。何でもパワハラだと決めつけることで、必要な教育・指導がおこなわれない事態は避けなくてはなりません。
企業活動に関わるすべての人は、パワハラについての正しい知識を備え、パワハラのない職場環境をつくることを求められているといえるでしょう。
パワハラは、身近になってきている法律問題なのです。
本記事では、パワハラを防止するための措置を義務づける法律が、具体的にどんな措置が必要で、違反した場合にはどうなるのか、パワハラ防止法および指針の内容を整理して解説します。
パワハラ防止法の施行日|大企業2020年6月1日・中小企業2022年4月1日から
パワハラ防止法は、大企業2020年6月1日から、中小企業は2022年4月1日から施行されました。
パワーハラスメント(以下パワハラ)は、労働者の就業意欲の低下や精神的な障害、離職率の上昇などを引き起こす行為です。パワハラの行為者だけでなく、パワハラを放置した企業も社会的なイメージを失墜し、ひいては業績悪化につながる可能性もあります。実際、社会的ダメージを受けた企業のイメージ回復には、長時間かかり、回復しきれないケースも存在します。
パワハラ防止法(労働施策総合推進法)が成立した背景
パワハラ防止法が成立した背景のひとつとして、パワハラや関連する行為に対する相談件数が増加したことが挙げられます。
「平成28年度 職場のパワーハラスメントに関する実態調査」では、従業員の悩みや不満を相談する窓口において相談の多いテーマは、パワーハラスメントが32.4%ともっとも多いことがわかっています。
また、過去3年間のパワハラ相談件数について「増加している」「件数は変わらない」とした企業の合計は23.9%で、「パワハラの相談がある」と回答した企業の約半数にあたります。
2020年度の「個別労働紛争解決制度の施行状況」によれば、いじめ・嫌がらせに関する相談件数は7万9,190件です。
なお、前述したように、2020年6月に大企業におけるパワハラ防止法が施行されたため、上図の「いじめ・嫌がらせ」の件数には当該紛争に関する件数には含まれていません。大企業におけるパワハラ防止法の件数は、以下の通りです。
同法に関する相談件数:18,363件
同法に基づく紛争解決の援助申立件数:308件
同法に基づく調停申請受理件数:126件
引用元:「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します | 厚生労働省
これらのデータからは、対人関係に起因する職場環境の悪化が多発しており、環境改善が強く求められているという社会の現状が見てとれます。こうした現状を受け、国がハラスメントを防止するための取り組みとして法制化したものと考えられます。
また2016年12月に厚生労働省が公表した「過労死等ゼロ」緊急対策は、大手広告会社に勤める女性社員の過労自殺が、上司によるパワハラが一因となったとの指摘をきっかけに取りまとめられたという見方があります。
若く尊い命が失われたこともパワハラ防止法成立の背景にあるといえるでしょう。
パワハラ防止法で規制されるパワハラの定義
パワハラ指針ではパワハラの定義として3要件を示すとともに、典型的なパワハラと呼べる6つの類型を紹介しています。
3つの要件
職場におけるパワハラとは、以下の3つの要件をすべて満たすものと定義されています。
- 優先的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
- 労働者の就業環境が害されるもの
「優先的な関係を背景とした言動」とは
言動を受ける者が行為者に対し、抵抗・拒絶できない関係を背景にしておこなわれるものを指します。したがって上司から部下への言動だけとは限らず、同僚や部下による言動でもパワハラになり得ます。
たとえば次のようなケースでは職場内での優先的な関係が背景にあるといえるでしょう。
- 部下が業務上必要な知識や経験を有しており、部下の協力がなければ業務を円滑に進められない場合における部下から上司への言動
- 営業成績のよい社員から悪い社員への言動
- 経験年数が長いリーダー格の社員から新入社員への言動
「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」とは
業務上明らかに必要のない行為や目的を大きく逸脱した行為、業務遂行の手段として不適切な行為をいいます。
たとえば、重要な会議に遅刻した部下に対して上司が一度叱責するような行為は教育としての意味合いが強く、通常はパワハラには該当しません。他方で、「遅刻するような人間だからお前はだめなんだ」などと、人格を否定するような言動をともない、それが日常的に繰り返されればパワハラに該当し得るでしょう。
教育・指導の名目でも社会通念上許容される限度を超えていればパワハラとなる可能性があるということです。この、社会通念上許容される限度がどの程度のものかをめぐって争いになるのです。
「労働者の就業環境が害されるもの」とは
労働者が能力を発揮するのに重大な妨げとなるような看過できない程度の支障を指します。たとえば就業意欲が低下する、業務に専念できないなどの影響が生じている場合です。
6つの類型
典型的なパワハラの類型は以下の6つです。
- 身体的な攻撃
- 精神的な攻撃
- 人間関係からの切り離し
- 過大な要求
- 過小な要求
- 個の侵害
6つの類型は限定列挙ではありませんので、これに該当しない場合でもパワハラだと認められるケースがある点には注意が必要です。
パワハラにあたるか否かは平均的な労働者の感じ方を基準としつつ、労働者の属性や心身の状況、行為者との関係などさまざまな角度から総合的に判断されるべきものとされています。
(参考:あかるい職場応援団 事業主パンフレット|厚生労働省 )
パワハラの具体例
6つの類型をもとに、何をするとパワハラに該当するのか具体例をチェックしてみましょう。
- 身体的な攻撃……殴る蹴る、物で頭を叩く、物を投げつけるなど
- 精神的な攻撃……人格を否定する暴言を吐く、他の従業員の前で罵倒する、長時間にわたって執拗に非難するなど
- 人間関係からの切り離し……別室に隔離する、集団で無視する、他の従業員との接触や協力を禁止するなど
- 過大な要求……新卒者に対して教育のないまま過大なノルマを課す、私的な雑用を強要する、終業間際に大量の業務を押し付けるなど
- 過小な要求……役職名に見合わない程度の低い業務をさせる、嫌がらせで仕事を与えないなど
- 個への侵害……個人用の携帯電話をのぞき見る、センシティブな個人情報を他の労働者へ暴露する、家族や恋人のことを根掘り葉掘り聞くなど
厚生労働省が2020年に実施した調査によると、過去3年間に勤務先でパワハラを受けたことがあると回答した人約2,500人のうち、受けたパワハラの内容でもっとも多いのは「精神的な攻撃」で49.4%、次いで「過大な要求」が33.3%、「個の侵害」が24.0%でした。

引用元:令和2年度 職場のハラスメントに関する実態調査報告書 | 厚生労働省
自身が受けた言動がどの類型のパワハラにあたるのかは、厚生労働省のハラスメント対策サイト「あかるい職場の応援団」内で設問に答えてチェックしてみてもよいでしょう。
実際にあったパワハラ事例3選
ここからは実際の裁判例から、パワハラや損害賠償請求が認定された事例を紹介します。
社員個人のパワハラに対して、会社のパワハラ防止法義務違反が問われた事例
土木建築会社で養成員として働いていたAが、先輩社員であるBから日常的にパワハラを受けていて、Aの両親が会社に対して損害賠償を請求した裁判例です。AはBを含む先輩数名と居酒屋で飲酒後、先輩を自宅に送る道中で交通事故を起こし、Bらとともに亡くなっています。
Aは先輩Bから以下のようなパワハラを受けていました。
【精神的な攻撃】
・関係がない従業員のリストラをAのせいにする
・Aの父の会社が勤務先の二次下請であることについて嫌みを言う
【身体的な攻撃】
・物や危険な道具を投げつける
・机を蹴る
・ガムを吐きつける
【過大な要求】
・他の従業員がやるべき仕事を押しつけたり、無茶な仕事量を命じたりして、深夜まで残業させる
このようなBのAに対する言動について、上司かつ責任者である所長に「パワハラである」という認識はなく、とくに対処もしていませんでした。
裁判では、先輩社員BのAに対する嫌がらせがパワハラと認められるとともに、会社が然るべき措置を取らなかったことは、パワハラ防止義務違反・安全配慮義務違反にあたり、また不法行為についても責任を負うとされました。一方飲酒後の事故については、飲み会への参加と飲酒後の運転はAの自由意思のもとでおこなわれたものであり、会社に責任を問えるものではないと判断されました。
【参考】津地裁 平成21年2月19日判決 日本土建事件|あかるい職場応援団
上司の侮辱的メールがパワハラとされ、損害賠償が認められた事例
上司が部下に送信したメールの内容が、パワハラにあたるかどうかが争点となった裁判例です。
上司Cが部下Dに対して送ったメールの内容は、以下のとおりです。
【精神的な攻撃】
・意欲・やる気がないなら、会社を辞めるべき
・部署・会社ともにDによって損失を受けている
・他の人間ならD以上の成績をおさめられる
このような内容のメールを、職場の同僚を宛先に含めてDに送信しました。
部下Dはこのメールによって名誉が毀損された上に、Cの行為はパワハラにあたるとして、損害賠償を請求しました。
一審判決では、メールの内容はあくまでもDを叱咤するもので、Dの名誉を傷つけたとまではいえないと判断されました。
しかし二審では、Cのメールの目的が部下を叱咤激励することにあり、そこに精神的苦痛を与える意図がなかったとしても、本メールの内容は社会通念上許容される限度を大きく超えたものであるとして、パワハラに該当すると判断されました。加えて関係のない同僚にもメールを送信したことを考慮し、Dが受けた精神的苦痛に対して5万円の損害賠償が認められました。
【参考】東京高裁 平成17年4月20日判決 A保険会社上司(損害賠償)事件|あかるい職場応援団
同僚へのパワハラに対し、慰謝料200万円の請求が認められた事例
社員EのFに対する言動がパワハラであるとして、慰謝料を請求した裁判例です。EはFの上司ではありませんが、社内で優位的な立場にありました。
社員EがFに対しておこなった言動は、以下のようなものです。
【精神的な攻撃】
・深夜に業務外の長電話をする
・本来の業務以外の個人的な仕事をさせ、指示に従わないと怒鳴る
・他の従業員や役員の前で罵倒する
・Fを罵倒する内容のメールを同僚・上司を宛先に含めて送る
・侮辱的な言葉や退職勧告・女性差別とも受け取られる表現を使い、激しく罵る
こうした社員Eの行為がパワハラにあたるとして、同僚Fは慰謝料300万円を請求しました。
判決では、社員Eが立場上優位であることを利用しFに対してパワハラをおこなったと認められ、慰謝料200万円の支払いが命じられました。
【参考】東京地裁 平成25年1月30日判決 慰謝料請求事件|あかるい職場応援団
パワハラ防止法で事業主に義務づけられる措置
ここでは、パワハラ指針で定められている事業主が講ずべき措置について解説しています。
企業にも職場環境配慮義務があるため、パワハラを含む各種ハラスメントを防止するための環境を整え、ハラスメント事案が発生した際には速やかに対処する必要があります。
また法改正がおこなわれた事実によってパワハラに対する社会の目がいっそう厳しくなっています。パワハラの行為者およびそれを放置する企業のリスクは高まっていると認識するべきでしょう。
社内方針の明確化と周知・啓発
事業主はパワハラを防止するために自社でどのような方針をとるのかを明確にし、管理監督者を含める労働者に周知・啓発しなくてはなりません。
周知・啓発をするには次のような方法があります。
- 社内報、社内ホームページなどに「パワハラをおこなってはならない」と明記し、発生原因や背景、トラブル事例などもあわせて紹介する
- 社内方針やパワハラの発生原因・背景を理解させるための研修や講習、説明会などをおこなう
加えて、パワハラの加害者に対して厳しく対処する方針や、懲戒処分などの対処内容を就業規則や服務規定に定め、周知・啓発しなくてはなりません。
トップが明確に意思表示をし、企業としての方針を知らせることで、労働者は自らの問題として「パワハラはいけないことなのだ」と認識します。周知・啓発においては、パワハラが発生する原因や背景について労働者の理解を深め、原因があれば解消していくことでパワハラを防止する効果が高まるとされています。
相談に適切に対応するための体制づくり
労働者から相談があった際に適切に対処するために必要な体制の整備として、相談窓口を設けて事前に労働者へ周知することが必要です。
たとえば相談に対応する担当者を決める、相談への対応を弁護士などへ外部委託するなどの方法が挙げられます。企業規模が小さく窓口や担当を決める余裕がない中小企業などでは、とくに外部委託は有効な方法でしょう。
また相談窓口の担当者が適切に対応できるよう、担当者へ対する研修の実施や人事部との連携をあらかじめ整えておくことなども求められます。
パワハラが発生した場合の迅速・適切な対応
事業主はパワハラについて労働者から相談があった際には、次の措置を講じる必要があります。
- 事実関係を迅速かつ正確に把握する
- 事実関係が確認できた場合にはパワハラを受けた被害者に対する配慮措置をおこなう(例:休暇を与える、必要な補償をするなど)
- 事実関係が確認できた場合には加害者に対する必要な措置をおこなう(例:注意、配置転換、懲戒処分など)
- 再発防止に向けて、改めて事業主の方針を周知・啓発するなどの措置をおこなう
そのほか併せて講ずべき措置
ここまで説明したパワハラに対してのさまざまな措置をおこなう際には、あわせて次の措置も実施する必要があります。
- 相談者や相談を受けた者、行為者、目撃者などの第三者のプライバシーを保護するために必要な措置
- 労働者が相談したことや相談された者が調査したことなどを理由として、解雇・降格その他不利益な取り扱いをしないように定め、労働者に周知・啓発すること
パワハラ防止法の対象となる範囲
パワハラ防止法の適用を受ける職場や労働者の範囲を確認しておきましょう。
職場の範囲とは
職場とは「事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所」を指します。したがって会社の事務所など毎日出勤するような場所でなくても、たとえば出張先や社用車などで業務をおこなったのであれば、それらの場所は職場として認められます。
また時間の制限はないため、勤務時間外におこなわれたものであってもパワハラに該当します。
労働者の範囲
正社員に限らずパート・アルバイト、派遣社員、契約社員など雇用されるすべての労働者はすべてパワハラ防止法の適用を受けます。派遣社員の場合、労働者と雇用契約を結ぶ派遣会社はもちろん、実際に労働者が働く派遣先についても同様の配慮、措置が求められます。
業務委託契約の個人事業主やインターンシップの学生、求職者などは労働者の範囲に含まれません。
しかし、パワハラ防止法の趣旨に照らし合わせ、これらの人に対しても注意や配慮をすることが望ましいとされています。労働者と同様の方針を示し、実際にパワハラがあった場合には同じく必要な対応をするのがよいでしょう。
パワハラ防止法に違反した場合の罰則
パワハラそのものに罰則規定が設けられているわけではありません。
しかし、厚生労働大臣による助言・指導および勧告の対象となり、勧告にしたがわない場合には企業名の公表もあります。措置義務が定められている以上、従業員から「相談先がない」「相談しても何もしてくれなかった」などの通報があれば、助言・指導・勧告の対象となることは十分に考えられるでしょう。
加えて昨今はSNSで情報が一気に広まる時代です。被害者や被害者が加入する労働組合がパワハラ防止法違反を世間に大々的にアピールすることで、企業の信用失墜につながる可能性があります。
2019年の法改正でパワハラそのものへの罰則規定は見送られましたが、今後の改善状況などによっては罰則が設けられる可能性はあると思っておくべきでしょう。
なお、パワハラ行為が暴行罪や脅迫罪など刑法に規定された犯罪の成立要件を満たして有罪になった場合には、行為者には罰則が適用されます。
【関連記事】
パワハラが発生した際の企業側の対応とは
この章では、自身が人事やコンプライアンス部門などに所属し、パワハラ対策を講ずべき立場にある場合の、対応のポイントをまとめます。
防止策はここまでお伝えしたとおりですので、実際にパワハラ事案が発生した後の対応に絞って紹介します。
事実関係の調査
まずは相談を受けた後、事実関係を確認するために速やかに調査をおこないます。被害者とされる人の話だけでなく加害者とされる人の話も聞き、さらに関係者へも聴き取りをおこなうなどし、公平な調査となるよう気をつけることが大切です。
パワハラが事実だった場合、パワハラの内容に応じて加害者に対する処分を検討します。
加害者側の処分を検討
一律に同じ処分とするのではなく、パワハラの様態や回数、パワハラの経緯や目的、反省の有無などを総合的に判断しなくてはなりません。
懲戒処分は就業規則にもとづいておこなわれる必要があり、安易な懲戒処分はパワハラ加害者から訴えられかねませんので、慎重におこないましょう。
被害者へのフォローや謝罪、パワハラが発生してしまった原因の究明も重要です。社内規定の見直しや体制の強化、経営者からのメッセージ発信などを通じて再発防止に努めましょう。
誤解だった場合
調査の結果パワハラには該当しない、誤解だったといった場合でも、行為者に対して誤解を招く行為やその原因に関して注意や指導をおこないます。
また相談者に対してはパワハラに該当しない理由を理解してもらえるように丁寧に説明し、行為者へどのような指導をおこなったのかも伝えるなど、納得して業務に専念できるよう配慮するのが望ましいでしょう。
パワハラを受けた労働者ができること
パワハラ防止法の施行によって大企業・中小企業ともに、パワハラ相談窓口の設置が義務化されました。労働者がパワハラについて相談しやすい環境が整っているため、パワハラを受けた場合はすぐに相談しましょう。
相談窓口がない、相談しても軽くあしらわれたといった場合には、パワハラ防止法に違反していることになります。人事部などへ違反している旨を伝える、労働局へ通報するなどの対応が有効です。
ただし「経営者自身によるパワハラが横行して誰にも相談できない」、「企業規模が小さいため相談窓口の担当者とパワハラ加害者が同一である」など、どうにもできない状況もあるでしょう。
その場合は個別の相談を受けつけ、対策を考えてくれる弁護士への相談も検討してみてください。パワハラの証拠収集の方法や今後とり得る手段などを法律の観点からアドバイスしてくれるため、今何をするべきか見えてくるでしょう。
あなたの代理人となって企業へ防止を求めることや、労働審判・裁判の対応を任せることもできます。
まとめ
パワハラ防止法はパワハラのないよりよい職場環境をつくるための法律です。法の趣旨や指針が示す内容を理解して実行するとともに、職場ではお互いが思いやりの心をもってコミュニケーションをとることも重要です。
指導する側は相手の成長を促すよう努めること、指導される側は適正な指導かどうかをしっかり見極める冷静さが必要となるでしょう。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る
【不当解雇・残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る
【正社員の方限定】退職勧奨や残業代未払い、不当解雇、退職代行から労働組合関係まですべての正社員の方の権利をお守りいたします/当日相談・メール、LINEでの相談受付◎/分割払いや後払いにも対応可能
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡


パワハラに関する新着コラム
-
正社員の即日退職は、原則として認められません。しかし、例外的に正社員の即日退職が認められることもあります。退職代行サービスの利用も有効です。本記事では、正社員の...
-
パワハラ被害を受けていて、在職時はその余裕がなかったものの、退職してから被害を訴えたいと考えることもあるでしょう。本記事では、退職後にパワハラ被害を訴えられるこ...
-
職場や家庭で、差別や虐待、ハラスメントなど人権問題に苦しむ方に向けた相談窓口として、国が運営する「みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)」があります。...
-
職場のハラスメントに悩んでいる場合、誰かに相談することで解決の糸口がつかめるうえに心も少しは晴れるでしょう。本記事ではハラスメント行為に悩んでいる場合の相談窓口...
-
労働者には退職の自由が認められており、「会社を辞めれない」「辞めさせてもらえない」ということはありません。しかし、状況によって取るべき対応は異なるため、対処法を...
-
仕事を辞めたいと思っていても、家族は上司に言えないで悩んでいませんか?怖い上司や支えてくれる親に辞めたいと言えずに悩んだときは、まず辞めたい原因を考え直して見ま...
-
自身の部下からパワーハラスメントを受ける「逆パワハラ」が起きてしまった場合について、適切な対処方法を解説していきます。また、どのような被害を受けていると逆パワハ...
-
本記事では、パワハラについて無料相談ができる窓口と、どの窓口に相談すべきかをわかりやすく解説します。「パワハラを本気でどうにかしたい」という方は、ぜひ参考にして...
-
パワハラを訴えたい場合に録音データ・写真・メール・SNS・メモ・同僚の証言など、どんな証拠が有効になるのかを紹介。パワハラの訴訟に至るまでの流れ、訴えることのメ...
-
ハラスメントは特殊な事例ではなく誰もが被害を受ける・与える可能性がある問題です。この記事では、ハラスメントの定義や種類、関係する法律、被害に遭った際の対応方法相...
パワハラに関する人気コラム
-
パワーハラスメントの定義とは何かを解説!パワハラには6つの種類があるとされますが、法律上定義や意味を解説する項目はありません。ただ、労働者への嫌がらせ行為は違法...
-
上司のパワハラは労働問題の中でも比較的多いトラブルのひとつです。長時間労働や嫌がらせは違法になる可能性が高い為、正しい知識を身につけた上で中止交渉をすれば解決す...
-
パワハラを受けた方にとっては理不尽で許し難いものであり、パワハラをした相手に何か報復したいと考える方もいるでしょう。そこで今回は、パワハラの訴え方と訴える前に考...
-
過労死ラインとは労災給付の基準であり、月に80〜100時間を超える労働は深刻な健康障害を引き起こす可能性が高いとして、抑制する取り組みが広まっています。この記事...
-
今回は、パワハラに悩まれている方の最終手段とも言えるパワハラでの訴訟の事態と、パワハラで訴訟を起こす際の手順、慰謝料請求をするための相場、請求方法を解説していき...
-
長時間労働による過労死は緊急を要する社会問題です。長時間労働を強いられているニュースをよく耳にしますが、他人事ではない働き方をしている方も多いでしょう。そこで、...
-
この記事では、労働基準監督署でパワハラの相談をして解決できることや、パワハラ問題の解決フローについて紹介します。
-
本記事では、パワハラで労災認定を受けるための条件や手順などを解説します。パワハラを受けていて悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
-
仕事を辞めたい、鬱(うつ)になりそうと悩んでいる方は少なくないでしょう。うつ病は単なる甘えだと言われてしまうこともありますが、自分を追い詰めてしまう前に、休職や...
-
退職までの手続きを徹底解説!大企業の終身雇用が崩れ始める中、退職と転職は身近なものになってきています。昨今の新型コロナウィルスの影響で突然解雇を言い渡される方も...
パワハラの関連コラム
-
パワハラ被害を受けていて、在職時はその余裕がなかったものの、退職してから被害を訴えたいと考えることもあるでしょう。本記事では、退職後にパワハラ被害を訴えられるこ...
-
うつ病にかかり退職を考えている方は、退職の流れや生活費などが気になると思います。この記事では、うつ病で退職する場合の流れや保険、支援制度についてご紹介します。
-
マタニティハラスメント(マタハラ)とは、妊娠、出産、子育てなどをきっかけとして嫌がらせや不利益な扱いを受けることです。マタハラは法律で禁止されており、会社側に防...
-
現在、ハラスメント被害に遭われていて、社外の相談窓口を探している方は少なくないかもしれません。この記事では、ハラスメントに関する社外相談窓口7つの紹介と、相談前...
-
仕事を辞めたい、鬱(うつ)になりそうと悩んでいる方は少なくないでしょう。うつ病は単なる甘えだと言われてしまうこともありますが、自分を追い詰めてしまう前に、休職や...
-
パワハラを訴えたい場合に録音データ・写真・メール・SNS・メモ・同僚の証言など、どんな証拠が有効になるのかを紹介。パワハラの訴訟に至るまでの流れ、訴えることのメ...
-
日本看護協会も『ハラスメント対策』を講じるなど、ハラスメントについて一定の対応をしています。そこで、パワハラ被害に遭っている看護師の為の対処法や相談窓口などをご...
-
上司のパワハラは労働問題の中でも比較的多いトラブルのひとつです。長時間労働や嫌がらせは違法になる可能性が高い為、正しい知識を身につけた上で中止交渉をすれば解決す...
-
ハラスメントの被害にあった場合の通報窓口を設置すべき理由やメリットは?どんなハラスメントを受けた場合に利用できるのか。通報があった場合に企業がすべき対策も解説し...
-
自爆営業は、労働法に違反している恐れがあり、民事上も損害賠償の対象になる可能性があります。この記事では、自爆営業の違法性や断り方、対処法などについてご紹介します...
-
マタハラとは、働く女性が、出産・妊娠をきっかけに職場から、精神的・肉体的な嫌がらせを受けることで、マタニティ・ハラスメントの略です。
-
職場のハラスメントに悩んでいる場合、誰かに相談することで解決の糸口がつかめるうえに心も少しは晴れるでしょう。本記事ではハラスメント行為に悩んでいる場合の相談窓口...

































































