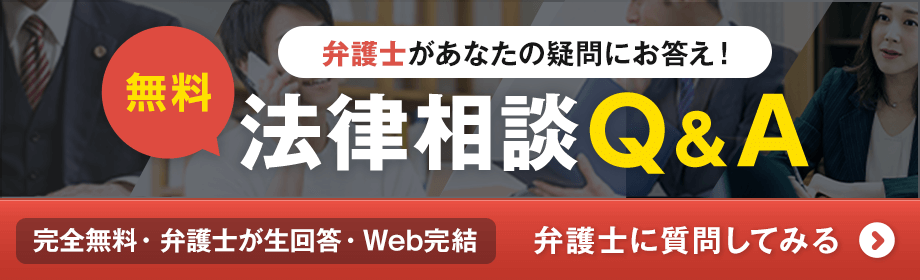近年、「コンプライアンスに厳しい世の中になってきた」というようなことを耳にする機会が増えています。
しかし、「コンプライアンス」という言葉の意味には多義的・曖昧なところがあり、とらえどころの難しい概念であることも事実です。
コンプライアンスをどのように遵守していくかは、企業が社会の中で経済活動を続けていくうえで、無視できない重要な問題で、企業活動においてコンプライアンスを軽視することは、社会的信用を失う可能性もある重要な話題なのです。
スマートフォン向けニュースアプリ大手「Gunosy(グノシー)」(東京都港区)の完全子会社「digwell(ディグウェル)」が虚偽広告を制作、配信していた問題で、東京都薬務課は医薬品医療機器法(薬機法)違反があったとしてグノシーに再発防止を求める行政指導を行った。グノシーは都に「管理や審査体制が不十分で一部の社員がやった」などと説明し、組織としての関与を否定したという。
そこで本記事では、コンプライアンスの意義・違反リスク・企業が取るべき対策などについて、労働者も知っておくべき内容として詳しく解説します。
コンプライアンスの本来の意味とは|法令遵守だけではない重要性
まずは、「会社にとってのコンプライアンスとは何か」、また「なぜコンプライアンスは重要か」ということについて解説します。
何を「遵守」すれば良い?法令遵守だけではない
コンプライアンス(compliance)という英語を日本語に訳すと、「遵守する」となります。つまり何かのルールなどを「守る」ということになりますが、会社が守らなければならないルールとは何なのでしょうか?
真っ先に思いつくのは、法律や条例などの法令でしょう。法律や条例など法令を守ることは、「法令遵守」という言葉が一般的になっていることからもわかるように、会社にとって重要かつ当然の義務です。
しかし、会社にとってのコンプライアンスとは、必ずしも法令遵守のみを指す言葉ではありません。会社として、法令遵守は最低限の義務であり、そのほかにも守らなければならないルール(規範)があります。
たとえば社内規程は、会社が自らを律するための仕組みとして定めたルールですので、(法令ではありませんが)遵守する必要があります。また、会社が社会からの支持・評判によって成り立っている部分が大きいことも考慮すると、社会の倫理を遵守することも非常に重要です。
法令・社内規程・社会倫理のいずれも、「社会が会社に対して守ることを期待しているルール(規範)」であるといえます。コンプライアンスの本質は、こうした社会からの目線を踏まえつつ、会社として期待される「あるべき姿」を逸脱しないことにあるのです。
コンプライアンスはなぜ重要か?
コンプライアンスは、会社にとってなぜ重要といえるのでしょうか。たしかに、コンプライアンスを遵守することは、会社の売り上げに対して直接貢献するわけではありません。
しかし、コンプライアンス違反が発覚した場合、会社は後から法的・社会的制裁を受けてしまいます。
この場合、会社の営業活動・生産活動に多大な悪影響が及んでしまうことになります。こうした事態を防ぐために、コンプライアンスは会社にとってのブレーキの役割を果たすものとして、決して軽んじられてはならないものといえます。さらに、「コンプライアンスがしっかりした会社である」と社会から認識されれば、会社としての信用を高めることにも繋がります。その結果として会社のブランドイメージが向上し、間接的に自社商品の売り上げアップに繋がる可能性も出てくるでしょう。
会社は社会的存在であるということを意識しつつ、社会からの信頼を裏切らないようにコンプライアンス遵守にまい進するのが、会社としてのあるべき姿といえます。
近年コンプライアンスの重要性が増している主な理由3つとその背景
会社にとってのコンプライアンスの重要性は、近年よりいっそう増す傾向にあります。以下では、コンプライアンスの重要性が増してきている理由について解説します。
SNSの発達により、情報伝達が加速化した
コンプライアンスの重要性に寄与している大きな要因の1つが、SNSの発達です。現在では、ひとたび企業が不祥事などを起こすと、その事実がSNSなどで即座に拡散されてしまいます。
SNS上の情報は、信ぴょう性が十分確認されないままに、尾ひれがついて広まってしまうことが非常に多いのが特徴です。そのため、たとえ些細な不祥事であったとしても大々的に拡散され、企業のレピュテーションに対して深刻なダメージが与えられてしまう可能性があります。
SNSの脅威から会社を守るためには、たとえ些細であってもコンプライアンス違反の種を見逃さず、透明性の高い経営を常日頃から目指していくほかありません。
事例|有名ホテルの食品偽装表示|不当景品類及び不当表示防止法違反
各地の有名ホテルでメニューの偽装表示が相次いで発覚し大きな社会問題に発展。食品の偽装表示は不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)違反になり得ます。
景品表示法は消費者に優良な商品やサービスであると誤認させる「優良誤認表示」を禁止している法律ですが、その適用基準はあいまいであったため、一連の偽装事件を受けて消費者庁はガイドライン案を公表。何が「優良誤認」に当たる表記なのかという定義や具体例を示すことに。
このガイドライン案について広く一般に意見を募集し、2014年3月 には正式なガイドライン「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方」 としてまとめています。
世間全体が他者に対して不寛容になった
最近では、特に日本国民全体の傾向として、他人の失敗を批判する・成功している他人を蹴落とそうとするなどの傾向が増しているように思われます。
この傾向にはさまざまな理由が考えられますが、
- SNSの発達により意見を発信しやすい環境が整ったこと
- 日本社会全体が収縮していく中で国民の経済状況・幸福度が悪化したこと
などが主な原因と思われます。
社会全体が他者に対してどんどん不寛容になっていく世の中では、企業の不祥事は批判の格好の的となってしまいます。できる限りそのような隙を与えないように、日頃からコンプライアンスの重要性を意識した取り組みを行うことが重要です。
メディアの報道傾向が極端になった
近年のメディアは、世間の耳目を引きやすいと見るや、過度にセンセーショナルな形で報道する傾向にあります。
特に名の通った大企業の場合は、少しの不祥事が大々的に報道されてしまい、想定外に大きな社会的ダメージを負ってしまう可能性が否定できません。
こうしたメディアの偏った報道傾向は、企業に対して保守的なコンプライアンス対策を強いている要因の一つといえるでしょう。
コンプライアンス違反の事例と違反リスク
会社にとって、コンプライアンス違反の危険性はいたるところに潜んでいます。
以下では、コンプライアンス違反の事例を取り上げつつ、違反した場合にどのような事態が発生してしまうのかについて解説します。
労務管理は、会社の日常のオペレーションの中でも、もっとも基本的な部類に入るものといえます。会社がずさんな労務管理を行っていると、コンプライアンス違反の温床になってしまうので十分注意が必要です。
労務関連のコンプライアンス違反で代表的なものは、
- 残業代の未払い
- 劣悪な労働環境の放置
- ハラスメント
などが挙げられます。
【関連記事】パワハラの定義とは|6つの種類と具体例・裁判例の判断基準付き
残業代の未払い
残業代(時間外労働手当)の支払いは、労働基準法37条1項において会社に義務付けられています。したがって残業代の未払いは、れっきとした労働基準法違反として、コンプライアンス違反に該当します。
もし残業代の未払いが発生した場合、
- ・従業員からの巨額の未払残業代請求
- ・従業員の離職
- ・新規採用への悪影響
などが生じる可能性があるので、きちんと支払いを行う必要があります。
劣悪な労働環境の放置
会社は、従業員が生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるように配慮する義務(安全配慮義務)を負担しています。
もし会社が劣悪な労働環境を放置すると、従業員の健康などに悪影響が生じ、会社の安全配慮義務違反としてコンプライアンス違反に該当する可能性があります。
また、仮に法令違反に至らないとしても、従業員の離職や新規採用への悪影響に繋がることは避けられないでしょう。経営層としては、現場の声をタイムリーに吸い上げることにより、劣悪な労働環境が放置されていないかを随時確認することが大切です。
ハラスメント
近年ハラスメントへの意識は、厚生労働省でも『事業主が雇用管理上講ずべき措置』という指針を発表するなど、社会全体で強まってきている傾向にあります。
職場におけるセクシュアルハラスメントや妊娠 ・ 出産・育児休業等に関するハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置
職場におけるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置が、厚生労働大臣の指針に定められています。事業主は、これらを必ず実施しなければなりません(実施が「望ましい」とされているものを除く)。企業の規模や職場の状況に応じて適切な実施方法を選択できるよう、具体例を示しますので、これを参考に措置を講じてください。
なお、派遣労働者に対しては、派遣元のみならず、派遣先事業主も措置を講じなければならないこ
とにご注意ください。
また、職場におけるハラスメントの防止の効果を高めるためには、発生の原因や背景について労働
者の理解を深めることが重要です。
引用元:労働基準法|事業主が講ずべき措置
そのため、コンプライアンスの一環としてのハラスメント対策が、会社にとってより重要な意味を持つようになってきました。
特にセクハラ・パワハラを放置すると、従業員によるSNSへのリークなどをきっかけとして世間にその事実が広まり、会社の社会的評判に大きな悪影響が生じる可能性もあります。もちろん、従業員からの損害賠償請求がなされることも考えられます。
そのため会社としては、ハラスメント行為に対して見て見ぬふりをせず、ハラスメント撲滅に向けた取り組みを積極的に行うことが期待されます。
【関連記事】パワハラ上司の訴え方|パワハラで訴える時に考える5つの事
品質管理関連|食品偽装・衛生管理の不備など
特に食品加工や飲食店を営む会社の場合、提供する食品の品質管理は、ビジネスの根幹をなす重要な事項といえます。
品質管理に関してコンプライアンス違反を犯している会社は、社会からの信頼を得ることを全く望めないでしょう。
食品の品質管理に関連するコンプライアンス違反の例としては、
- 食品の産地偽装
- 衛生管理の不備
などが挙げられます。
食品の産地偽装
食品の産地を偽装する行為は、食品衛生法という法律に違反します。食品の産地は、消費者にとってはきわめて関心の高い事項であり、これを偽装することは消費者に対する裏切りと言わざるを得ません。
そのため、たとえ軽い気持ちだとしても、食品の産地偽装は重大なコンプライアンス違反であると認識する必要があります。
もし食品の産地偽装が発覚した場合、企業イメージの失墜は避けられないほか、食品回収や損害賠償などで多額の出費を要することになります。そのため、自社で産地表示についての明確なルールとチェック体制を設けて、食品の産地偽装が発生しないようなシステムを構築することが肝要です。
衛生管理の不備
食品などを生産する現場の衛生管理の不備は、食品の腐敗や汚染などを招き、消費者の健康被害などの原因になり得ます。食は消費者の生命や健康にかかわるため、食品の衛生管理の不備は、極めて悪質性の高いコンプライアンス違反であるといえます。
もし違反が発覚した場合、食品偽装と同様に、企業イメージの失墜や多額の出費が発生することは避けられません。
粉飾決算
会計関連のコンプライアンス違反行為の例としては、粉飾決算や横領などが挙げられます。
会社の経営層は、会社の業績を良く見せるために、計算書類の内容をごまかしたりする誘惑に駆られるケースもあるかもしれません。しかし、粉飾決算は犯罪であり、重大なコンプライアンス違反に該当することに注意が必要です。
上場会社の場合、粉飾決算を行った個人は金融商品取引法違反として、「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれを併科」の刑事罰が科されます(金融商品取引法197条1項1号)。
さらに、両罰規定によって法人に対しても7億円以下の罰金刑が科されることになります(同法207条1項1号)。
非上場会社であっても、粉飾決算を行った個人は「特別背任罪」(会社法960条1項)として、「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれを併科」の刑事罰が科されます。
(取締役等の特別背任罪)
第九百六十条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。引用元:会社法960条
上記の刑事罰に加えて、株主から代表訴訟を提起され、会社と個人が連帯して巨額の損害賠償責任を負担するケースもあります。軽い気持ちで粉飾決算に手を出すと、後でとんでもない事態を招いてしまうおそれがあることを十分に認識しておきましょう。
横領
役員・従業員による会社資産の横領は、刑法上の業務上横領罪(刑法253条)に該当し、「10年以下の懲役」の刑事罰が科されます。悪質なケースでは、会社から預かった金を勝手に使ったり、不当な経費を申請して精算金を着服したりする例があります。
こうした行為については、刑事告発・懲戒処分などを含めて厳正に対処することが必要です。一方、会社の備品を勝手に持ち帰るなどの軽微なケースも存在しますが、こうしたケースであっても見逃してよいわけではありません。
横領などが発生にくい企業文化を育てるためにも、些細な横領行為であっても見逃さずに対応する必要があります。
【関連サイト】企業法務弁護士ナビ|企業法務における課題を解決する企業法務ポータルサイト
コンプライアンス遵守のために企業が取るべき対策は?
社内でコンプライアンス違反が発生することを防ぐために、企業はどのような対策を取ればよいのでしょうか。
以下では、企業の取ることのできるコンプライアンス対策の内容について解説します。
社内に二重・三重のチェック体制を設ける
社内でコンプライアンス違反についてのダブルチェック・トリプルチェックができる体制を整えておけば、コンプライアンス違反を未然に防ぐことに繋がります。たとえば、コンプライアンス遵守が通常の企業よりも強く求められる金融機関には、「3つの防衛線(Three Line of Defense)」という考え方が存在します。
「3つの防衛線」とは、
- 顧客と接するフロントオフィス(営業など)
- 会社のリスク管理を担当するバックオフィス(法務、コンプライアンス、税務など)
- 内部監査の専門部署
の3つの段階で、それぞれが独立してコンプライアンス違反の有無をチェックするという考え方をいいます。
このトリプルチェック体制を確立することにより、金融機関はコンプライアンス違反を徹底して排除するよう努めています。このような充実したチェック体制を構築できるかどうかは、コンプライアンスに精通した内部人材を確保できるかどうかにかなりの部分依存することになります。社内弁護士・社内会計士などを確保できる場合は良いですが、難しければ外部委託を検討すべきでしょう。
コンプライアンスに関する社内研修を定期的に行う
社内研修によって、コンプライアンスの重要性を社内に啓蒙することも重要です。コンプライアンスに力を入れている企業では、3か月ごと・6ヶ月ごとなどのスパンで、定期的にコンプライアンス研修を行っているところもあるようです。
特に法改正などのホットなテーマがある場合には、臨時の社内研修を実施して、最新の知識をフォローするのも有効でしょう。法的な論点に関するコンプライアンス研修については、弁護士などの外部講師を呼んで講義をしてもらうやり方も考えられます。
外部監査を行う
社内のコンプライアンス体制を強化することは大切ですが、それと同時に必要に応じて外部監査を行うことも、コンプライアンスの観点からは重要です。
会社法上外部監査が義務付けられるケースに加えて、会社内部で重大なコンプライアンス違反が発生した場合には、万全を期すために監査法人による外部監査を活用すると良いでしょう。
【関連記事】内部通報窓口とは|相談出来ることや利用メリット・相談時の注意点も解説
コンプライアンス対策は弁護士に相談を
自社のコンプライアンス体制を強化したいと考えている企業は、弁護士に相談しつつ対策を進めることをおすすめいたします。
コンプライアンス対策を弁護士に依頼する場合には、以下のようなメリットがあります。
法律家の観点から万全なコンプライアンスチェックが可能
弁護士は法律の専門家として、法令遵守の観点から、会社内部でコンプライアンス違反行為がないかを詳細にチェックします。
さらに弁護士は、法令遵守の観点以外にも、会社にとってレピュテーションに影響が出そうなポイントとして気になるところを指摘してくれます。このように弁護士は、コンプライアンス対応に関する専門的な知見を活かして、依頼者である企業が万全のコンプライアンスチェックを実施できるようにサポートすることが可能です。
社内でのコンプライアンス研修も任せられる
また弁護士に対しては、社内向けのコンプライアンス研修の講師を依頼することもできます。
コンプライアンスに関する経験が豊富な弁護士は、他社のコンプライアンス違反事例などの集積も豊富なケースが多いです。弁護士はこれまで経験した案件などを踏まえて、具体的なコンプライアンス違反の事例などを交えつつ、社員がイメージしやすい形でわかりやすく抗議をしてくれることでしょう。
万が一違反が発覚した場合の危機対応も依頼可能
万が一会社の内部でコンプライアンス違反が発生してしまった場合には、迅速な火消しの対応(危機管理対応)が必要です。しかし、自社の一大事に突然遭遇してしまったら、経営陣としても冷静な判断を適確に下すことは難しいでしょう。
また、危機管理対応の経験が少なければ、良かれと思って取った行動が裏目に出てしまうこともしばしばあります。そこで危機管理対応については、弁護士に相談してみましょう。
弁護士は、法的観点および会社のレピュテーションの観点などを踏まえて、会社にとってやるべきことの優先順位は何かを整理してくれます。
危機管理対応はその性質上、スピード勝負になる傾向にあります。弁護士に依頼をすれば、弁護士の適確な指示の下で、コンプライアンス違反に対する迅速な意思決定を行うことが可能となるでしょう。
まとめ
コンプライアンスは「法令遵守」という意味で語られることも多いですが、それだけでなく、会社の社内規程や社会倫理を遵守することも重要な側面といえます。
コンプライアンスを守ることは、直接会社の売り上げに貢献するわけではありません。しかし、世間から批判の対象となる後ろ暗い部分をできるだけ生じさせないようにすることで、会社の信用やブランドイメージを失墜させないことに繋がります。
近年では、SNSの発達などにより、企業がコンプライアンスを遵守することの重要性が日に日に高まっています。
弁護士は、会社のコンプライアンスチェックを専門的な観点から行うほか、従業員に分かりやすい形でのコンプライアンス研修を提供することも可能です。
もしこれから、自社にコンプライアンス対策を導入することを検討中の企業の方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る
【不当解雇・残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
 この記事の監修
この記事の監修

弁護士法人アクロピース

労務問題に関する新着コラム
-
長時間労働やハラスメントなどに苦しんでいる場合は、安全配慮義務違反として会社の責任を問うことも検討する必要があります。本記事では、安全配慮義務違反に該当するケー...
-
会社に有給休暇を申請したところ、「当日の休暇申請は欠勤だ」といわれてしまい、理不尽に感じている方もいるはずです。本記事では、有給休暇の取得条件や欠勤との違い、休...
-
取締役は原則いつでも辞任・退職できます。ただし、業務の途中や引継ぎなしで退職しようとすると、損害賠償を請求されることも少なくありません。本記事では、取締役の辞任...
-
実際に起こったコンプライアンス違反の事例をご紹介し、会社経営をする上で、どのような部分に気を付け、対処しておくべきかをご説明します。こちらの記事でご紹介した、コ...
-
内部告発は社内の不正を正すためにおこなうものです。しかし、内部告発をおこなったことによって不遇な扱いを受けてしまうケースも少なくありません。今回は内部告発のやり...
-
譴責は、懲戒処分の一つとして、会社の就業規則に定められるケースが多いでしょう。譴責処分を受けると、処分対象者の昇給・昇格に不利益な効果が生じることがあります。 ...
-
退職代行サービスを使われた企業はどう対処すればいいのか?弁護士運営ではない退職代行サービスは非弁行為?退職代行サービスを利用された後の流れや退職代行サービスを利...
-
就業規則とは、給与規定や退職規定などの労働条件が記載されている書類です。従業員を10人以上雇用している会社であれば、原則として作成した後に労働者に周知し、労働基...
-
団体交渉を申し込まれた場合に拒否をしてはならない理由や、拒否が認められる可能性がある正当な理由、また拒否する以外に団体交渉において会社が取ってはならない行為をご...
-
使用者が労働組合からの団体交渉の申入れを正当な理由なく拒否したり、組合活動を理由に労働者を解雇したりすると「不当労働行為」として違法となります。不当労働行為のパ...
労務問題に関する人気コラム
-
有給休暇とは、労働者が権利として取得できる休日のことです。有給休暇の取得は権利であり、これを会社が一方的に制限することは原則として違法です。この記事では、有給休...
-
残業代は原則、いかなる場合でも1分単位で支給する必要があります。しかし、会社によっては従業員へ正規の残業代を支払っていない違法なケースも存在します。この記事では...
-
在職証明書とは、職種や業務内容、給与など現在の職について証明する書類です。転職の際や保育園の入園申請時などに求められる場合がありますが、発行を求められる理由や記...
-
所定労働時間について知りたいという方は、同時に残業時間・残業代を正確に把握したいという思いがありますよね。本記事ではその基礎となる労働時間に関する内容をご紹介し...
-
就業規則とは、給与規定や退職規定などの労働条件が記載されている書類です。従業員を10人以上雇用している会社であれば、原則として作成した後に労働者に周知し、労働基...
-
同一労働同一賃金は2021年4月より全企業に適応された、正社員と非正規社員・派遣社員の間の待遇差を改善するためのルールです。本記事では、同一労働同一賃金の考え方...
-
管理監督者とは労働条件などが経営者と一体的な立場の者をいいます。この記事では管理監督者の定義や扱いについてわかりやすく解説!また、管理監督者に関する問題の対処法...
-
内部告発は社内の不正を正すためにおこなうものです。しかし、内部告発をおこなったことによって不遇な扱いを受けてしまうケースも少なくありません。今回は内部告発のやり...
-
ホワイトカラーエグゼンプションとは、『高度プロフェッショナル制度』ともいわれており、支払う労働賃金を労働時間ではなく、仕事の成果で評価する法案です。この記事では...
-
離職票とは退職した会社から受け取る書類のひとつで、失業給付の申請にあたり必要となるものです。どんな内容の書類なのか、いつ手元に届くのかなど、離職票を希望する際に...
労務問題の関連コラム
-
労働者が有給休暇を取得しやすくするためには、労使協定によって時間単位の有給休暇を導入することも有効です。時間単位の有給休暇に関する法律上の要件や、導入のメリット...
-
勤務態度が悪い社員を抱えてしまっていてお困りの会社経営者の方は、ぜひ参考にしていただき、勤務態度を改善してもらう手立てや正しい解雇の方法などできることから行って...
-
同一労働同一賃金は2021年4月より全企業に適応された、正社員と非正規社員・派遣社員の間の待遇差を改善するためのルールです。本記事では、同一労働同一賃金の考え方...
-
従業員から未払い残業代を請求がされているのであれば、安易に自力で解決しようとせず、すぐに弁護士に相談し、迅速かつ適切な対応方法を選択すべきです。本記事では、残業...
-
長時間労働やハラスメントなどに苦しんでいる場合は、安全配慮義務違反として会社の責任を問うことも検討する必要があります。本記事では、安全配慮義務違反に該当するケー...
-
転職活動において応募企業から内定をもらった後に届く「採用通知書」をテーマに、基本事項や法的性質について解説します。採用通知書が届いた際に確認するべきポイントや採...
-
残業代は原則、いかなる場合でも1分単位で支給する必要があります。しかし、会社によっては従業員へ正規の残業代を支払っていない違法なケースも存在します。この記事では...
-
有給休暇とは、労働者が権利として取得できる休日のことです。有給休暇の取得は権利であり、これを会社が一方的に制限することは原則として違法です。この記事では、有給休...
-
諭旨解雇(ゆしかいこ)とは、「懲戒解雇」の次に重い懲戒処分です。従業員を諭旨解雇する際、従業員とのトラブルを避けるために法律上の要件を踏まえて対応する必要があり...
-
うつ病になった社員の復帰が難しい場合の対処法やトラブルを防ぐためにできる退職までの話の進め方、うつ病で解雇して裁判になった過去の例などをご説明します。うつ病の社...
-
退職代行サービスを使われた企業はどう対処すればいいのか?弁護士運営ではない退職代行サービスは非弁行為?退職代行サービスを利用された後の流れや退職代行サービスを利...
-
公益通報者保護法により設置が求められる内部通報制度の概要について説明。内部告発との違いは?労働者が内部通報を利用するメリットや実際に通報される内容、利用方法につ...