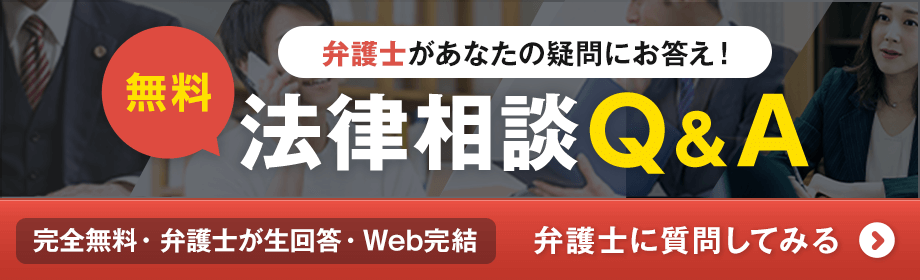交通事故で労災保険の休業補償を請求できる?支給条件や申請方法などの基礎知識を解説


業務中や通勤中の事故で働けなくなった場合、労災から休業補償を受けられる可能性があります。
休業補償を受けられれば、働いていない間も給料の何割かを受け取れるうえ、有給も減りません。
しかし、労災の休業補償を受け取るためには、一定の条件を満たさなければなりません。
たとえば業務中・通勤中の交通事故でも、働ける程度のけがなら休業補償の対象外となるため、あらかじめ条件を確認しておくことが重要です。
そこで本記事では、業務中・通勤中の交通事故で労災の休業補償を受ける条件や請求方法のほか、業務中・通勤中の交通事故にあった際の適切な対処法などを解説していきます。
会社によっては労災を使いたくないと考えることがあるため、従業員自らがルールを把握して適切に対処することが重要です。
本記事で、交通事故で労災の休業補償を申請する際に役立つ情報を確認していきましょう。
業務中・通勤中の交通事故では労災保険の休業補償を請求できる
業務中・通勤中の交通事故によって働けなくなった場合、労災の休業補償を請求できます。
休業補償とは、労働者が労働災害によって休業した際、労働基準監督署への請求によって労災保険として受け取れる給付金です。
労働災害とは、業務や通勤が原因で病気になったりけがをしたりすることです。
労働災害を原因とする損害を補償するための保険を労災保険といいます。
「労働災害」とは、労働者が業務遂行中に業務に起因して受けた業務上の災害のことで、業務上の負傷、業務上の疾病及び死亡をいう。ただし、業務上の疾病であっても、遅発性のもの(疾病の発生が、事故、災害などの突発的なものによるものでなく、緩慢に進行して発生した疾病をいう。たとえば、じん肺、鉛中毒症、振動障害などがある。)、食中毒及び伝染病は除く。なお、通勤災害による負傷、疾病及び死亡は除く。
引用元:用語の説明|厚生労働省
交通事故が労災保険の休業補償の対象であった場合の基礎知識
交通事故が労災保険の休業補償の対象になる場合、支給額や支給期間、支給開始時期などを把握しておきましょう。
支給額|給付基礎日額の80%×休業日数
労働災害によって給付される休業補償は給付基礎日額の80%で、内訳は以下のとおりです。
- 休業補償:休業1日につき給付基礎日額の60%
- 特別支給金:休業1日につき給付基礎日額の20%
労働災害によって休業損害が生じた場合、労災保険から「休業補償として給付基礎日額の60%」と「特別支援金として給付基礎日額の20%」が支給され、合計で給付基礎日額の80%が受け取れます。
なお、給付基礎日額とは、労働基準法における平均賃金を指し、原則として労働災害発生日以前の3ヵ月間に支払われた賃金総額を、その期間の総日数で除して算出します。
たとえば、直近3ヵ月間の賃金総額が63万円で3ヵ月間の日数が91日の場合、63万円÷91日=7,000円となり、労災保険から受け取れる休業補償は次のようになります。
- 休業補償:給付基礎日額7,000円×60%=4,200円
- 特別支援金:給付基礎日額7,000円×20%=1,400円
- 合計:休業補償4,200円+特別支援金1,400円=5,600円
なお、労災保険から休業補償が支払われるのは、4日目の休業からであるため、休業開始から3日間の休業補償は労災保険からの支払いはありません。
休業開始から3日間は、原則として会社が1日について平均賃金の60%の休業補償をすることになります。
対象期間|完治または症状固定まで
労災保険の休業補償を受け取れる期間は原則として、「けがが完治するまで」もしくは「症状固定するまで」です。
症状固定とは、症状は残っているが、一般的な治療を続けても効果が期待できなくなった状態を指します。
また、治療開始から1年6ヵ月が経過した場合、所定の手続きをすると、傷病等級の審査がされ、傷病等級1~3級に該当するかどうかが判断されます。
- 傷病等級1~3級に該当する場合:休業補償が傷病年金へ切り替わる
- 症状固定に至らず傷病等級1~3級に該当しない場合:休業補償が継続する
なお、症状固定になった際、交通事故の加害者側の保険会社にて、後遺障害等級認定の申請が認められれば、後遺障害部分の損害賠償金を請求できます。
支給開始時期|通常は約1ヵ月程度
休業補償が振り込まれるタイミングは、一般的に申請から1ヵ月程度です。
申請が認められ休業補償の支給が決定すると、労災から「支給開始決定通知」が郵送され、支給額・入金日を確認できます。
業務中・通勤中の交通事故で労災の休業補償を請求するための5つの条件
業務中・通勤中の交通事故で労災の休業補償を請求するためには、以下の5つの条件を満たす必要があります。
- 労災保険の対象者である
- 業務中または通勤中の交通事故が原因であること
- 交通事故のけがにより労働できる状態にないこと
- 会社から賃金などを受け取っていないこと
- 時効により請求権が消滅していないこと
次の項目から、上記5つの条件について解説していきます。
1.労災保険の対象者であること
休業補償を受けるには労災保険の対象者でなければなりません。
具体的には、労災保険は、常用・日雇・パート・アルバイトなどの雇用名称・雇用形態にかかわらず、労働の対価として賃金を受ける全ての労働者が対象となります。
なお、「法人の役員」や「事業主と同居している親族」は原則対象となりませんが、以下のような方は労災保険の対象になります。
- 取締役のうち業務執行取締役の指揮監督を受けて労働に従事し、労働の対価として賃金を一般の労働者と同一条件で支払を受ける者
- 代表取締役以外の取締役で、定款、社員総会、或いは取締役の過半数をもって、業務執行を除外された者であって、業務執行取締役の指揮監督を受けて労働に従事し、労働の対価として賃金を一般の労働者と同一の条件で支払を受ける者
- 同居の親族以外の労働者を常時使用する事業における、一般事務又は現場作業等に従事し、かつ一定の要件を満たす事業主と同居している親族
一般的な労働者であれば基本的には誰もが労災保険の対象者であり、労働災害があった場合には労災保険から補償を受けられると理解しておきましょう。
2.業務中または通勤中の交通事故が原因であること
労災保険の休業補償を受けるには、業務中または通勤中の事故などが原因である必要があります。
業務中の事故や業務上の疾病の場合は休業補償給付、通勤中であれば休業給付が給付されます。
休業補償給付と休業給付には、次の違いがあります。
| 給付名称 | 療養給付の一部負担金 | 待機期間(休業開始から3日間)の使用者の賃金支払い義務 |
|---|---|---|
| 休業補償給付(業務中) | なし | あり(賃金の6割) |
| 休業給付(通勤中) | あり(200円) | なし |
補償内容に大きな違いはありませんが、「療養給付の一部負担金」「休業開始から3日間の待機期間中の支払義務」などは、いつ発生した事故なのかによって違いがあります。
3.交通事故のけがにより労働できる状態にないこと
休業補償を受けるためには、単に業務上などに事故・疾病が生じただけでなく、働けない状態であることも求められます。
「働けない」と認められるためには、医師からの就労制限を受けるなどの証明をする必要があります。
なお、働ける場合、休業補償は受け取れず、治療費などが支給されます。
4.会社から賃金などを受け取っていないこと
休業補償を受けるためには、「対象期間中に会社から賃金を受け取っていない」という条件も満たす必要があります。
休業補償の趣旨は、労働災害で収入を得られなくなった場合に、賃金の一部を補償することであるため、労働災害によって働けなくなったとしても、会社から賃金を受け取って休業している場合は、休業補償の対象外です。
たとえば、有給休暇で休業している場合や、勤務日数に関わらず報酬を受け取れる歩合性の場合は、労災保険から休業補償を受けられません。
5.時効により請求権が消滅していないこと
時効を過ぎると休業補償を請求できません。
休業補償の請求権は、療養のため働けず、賃金を得られない日ごとに発生し、その日の翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅します。
たとえば2024年7月1日が「療養のため働けず、賃金を得られない日」の場合、その翌日から2年経過した2026年7月2日になると、2024年7月1日の休業補償は受け取れません。
休業補償には時効があることに注意したうえで、早めに請求することをおすすめします。
業務中・通勤中の交通事故で労災保険の休業補償を請求する際の流れ
業務中や通勤中の事故で労災保険の休業申請を請求する流れは、次のとおりです。
- 労働基準監督署に休業補償給付支給請求書を提出する
- 労働基準監督署が調査をし、支給・不支給を決定する
- 支給決定の場合は指定口座に給付金が振り込まれる
申請から受給までの流れについて、次の項目から解説していきます。
1.労働基準監督署に休業補償給付支給請求書を提出する
業務時間や通勤中の事故によって働けなくなった場合は、労働者から労災に休業補償を申請します。
業務災害の場合には「休業補償給付支給請求書(第8号)」と、通勤災害の場合には「休業給付支給請求書(第16号の6)」を提出します。
各請求書の必要事項を記入し、以下の書類を添付して、労災に休業補償の申請をしましょう。
- 賃金台帳
- 出勤簿の写し
- 休業補償と同じ理由で障害年金を受給している場合はその支給額の証明書
なお、休業補償の申請者は、原則として労働者本人です。
ただし、労働者による申請が困難な場合、会社は労働者の労災申請を助けよう義務付けられています。
これを助力義務と言います。
(事業主の助力等)
第二十三条 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。
休業補償の申請には賃金台帳など、会社に発行依頼する書類が必要です。
これらの必要書類を従業員から求められた場合、会社には、すみやかに発行する義務があります。
- 業務災害の場合は「休業補償給付支給請求書(第8号)」
- 通勤災害の場合は「休業給付支給請求書(第16号の6)」
第三者行為災害に関する書類も忘れずに提出する
労働災害では、通勤途中の交通事故の被害者になったり、仕事で道路を通行中に建設現場から落下した物に当たったりするなどして負傷する場合もあります。
このような第三者の行為によって被害に遭うことを「第三者行為災害」といい、労災保険法には以下のように記載されています。
第十二条の四 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
引用元:労災保険法|e-Gov法令検索
第三者行為災害によって労災を申請する場合、「第三者行為災害届」に加えて次のような書類の添付が必要です。
- 「交通事故証明書」(原本)または「交通事故発生届」
- 示談書
- 自賠責保険等の損害賠償金等支払証明書または保険金支払通知書死体検案書または死亡診断書
- 戸籍謄本
第三者行為災害被害者の損失補填分について、国は加害者に請求できるため、労災申請の際には、第三者の行為を証明する書類の添付が必要と考えられます。
2.労働基準監督署が調査をし、支給・不支給を決定する
労災の申請をすると労働基準監督署が申請内容を調査します。
調査方法は書類や勤務先への聞き取りで、基本的に以下の流れで進められます。
- 会社に資料提出要請の文書が届く
- 関係資料を集める
- 使用者報告書を記載する
- 使用者報告書提出から2~3か月後に労働基準監督署からの聴き取り調査がおこなわれる
- 調査結果復命書が作成される
- 調査結果が従業員へ通知される
労基署の調査結果は従業員本人にのみ通知され、会社には通知されません。
3.支給決定の場合は指定口座に給付金が振り込まれる
調査が終わり、支給が決定した場合、従業員が申請書に記載した口座番号へ振り込まれます。
保険金の振込までには1ヵ月程度かかりますが、事故の状況などによってはさらに時間を要する場合もあります。
不支給決定となった場合は審査請求などをおこなう
休業補償が不支給となった場合や、審査結果に不満がある場合は、審査請求ができます。
審査請求の方法は、不支給決定をした労働基準監督署の所在地を管轄する労働局に置かれている、労働者災害補償保険審査官に不服の申し立てをすることです。
不服申し立ては不支給決定の事実を知った日から3ヵ月以内である点にも注意しましょう。
業務中・通勤中に交通事故の被害に遭った方が知っておくべきポイント
業務中・通勤中に交通事故の被害に遭ったら、以下の3点を把握して適切に行動することが重要です。
- 労災保険では療養補償給付なども請求できる
- 会社によっては受任者払い制度を利用できる場合がある
- 加害者や任意保険会社に対して慰謝料などを請求できる
休業補償だけでなく他の手当が受け取れる場合もあるため、どのような手当がどのようなタイミングで受け取れるのかしっかりと把握しておきましょう。
1.労災保険では療養補償給付なども請求できる
労災保険を請求する場合、療養補償給付なども一緒に請求できます。
療養補償給付とは、労働災害によって労災病院や労災指定病院などを受診した場合、原則として傷病が治ゆするまで、無料で療養を受けられる制度です。
一般的に交通事故の治療費は過失割合に応じて支払われるため、過失割合がはっきりしない場合、保険会社は治療費を容易に支払わないことがあります。
しかし労災保険から療養補償給付を受ける場合、過失割合などとは無関係に全額労災保険から支払われます。
また損害保険会社の場合、保険会社が「治療が完了した」と判断し、治療費の支給を打ち切ることがあります。
その際は労災保険へ切り替えると、治療費を受け取れる可能性があります。
2.会社によっては受任者払い制度を利用できる場合がある
受任者払い制度とは、休業補償が労災から支払われる前に、会社が休業補償を立て替える制度です。
労働者の中には労働災害によって給料が入らなくなってから、休業補償が支給されるまでの間にお金がなくなり生活ができなくなってしまう場合があります。
このような際に、受任者払い制度を利用すれば、従業員は休業補償相当額を受け取れます。
なお、会社が受任者払い制度を利用することは法的な義務ではないため、必ず利用できるわけではありません。
3.加害者や任意保険会社に対して慰謝料などを請求できる
労災保険には、交通事故で負った肉体的苦痛・精神的苦痛に対する慰謝料は含まれていません。
そこで、加害者や加害者側の任意保険会社に対して直接慰謝料を請求する必要があります。
交通事故の慰謝料には、以下の3つがあります。
- 入通院慰謝料:交通事故によるけがで入通院した場合に受け取れる慰謝料
- 後遺障害慰謝料:交通事故により後遺障害になった場合に受け取れる慰謝料
- 死亡慰謝料:交通事故によって被害者が亡くなった場合に受け取れる慰謝料
慰謝料は今後の生活の質に影響するため、忘れずに加害者や保険会社に請求しましょう。
なお、交通事故の慰謝料請求については、以下のページで詳しく解説しています。
交通事故による労災の休業補償についてよくある質問
交通事故による労災の休業補償に関するよくある質問は、以下のとおりです。
- 労災保険の休業補償と任意保険の休業補償はどちらを先に請求すべきですか?
- 休業補償の受給中に退職しました。もう支給されないでしょうか?
次の項目から、上記2点をわかりやすく解説していきます。
Q.労災保険の休業補償と任意保険の休業補償はどちらを先に請求すべきですか?
労災保険の休業補償と任意保険の休業補償は、どちらから請求すべきというルールがないため、以下を参考に決めましょう。
| 労災保険の休業補償を優先させた方がよいケース | ・被害者の過失割合が大きい ・加害者が任意保険に加入していない場合 ・治療が長引きそうな場合 ・治療費を窓口で負担したくない場合 |
|---|---|
| 任意保険の休業補償を優先させた方がよいケース | 任意保険会社から早く後遺障害慰謝料を受け取りたい場合 |
被害者の過失割合が大きい場合や、加害者が任意保険に加入していない場合は、受け取れる保険金が少なくなることがあります。
加害者が任意保険に加入していない場合や、できる限り早く後遺障害慰謝料を受け取りたい場合には、労災保険の休業補償を優先しましょう。
なお、厚生労働省は「原則として自賠責保険を先行させるよう取り扱うこと(自賠先行)」という通達を出していますが、強制力はないため、状況をふまえて適切と考えられる保険を使用しましょう。
Q.休業補償の受給中に退職しました。もう支給されないでしょうか?
休業補償受給中に退職しても、条件を満たしている限り、休業補償は受け取れます。
第十二条の五 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない
また休業補償の申請に関しても、条件を満たしていれば退職後でも可能です。
さいごに|労災保険の休業補償についてわからないことは弁護士に相談を!
休業補償を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 労災保険の対象者である
- 業務中または通勤中の交通事故が原因であること
- 交通事故のけがにより労働できる状態にないこと
- 会社から賃金などを受け取っていないこと
- 時効により請求権が消滅していないこと
上記の条件を満たせば休業補償を受け取れますが、休業補償などで労災の申請をすると、会社に調査が入るなどの点から、会社が労災の使用を認めない可能性があります。
この場合、会社から申請に必要な書類を受け取れないため労災申請ができずに諦める労働者もいるでしょう。
また、すでに退職した会社の休業補償を申請する場合も、会社が協力してくれない可能性があります。
「会社が労災の使用を認めない」「すでに退職した会社での労災を申請したい」「労災申請について不明点がある」などの場合、弁護士に相談してみましょう。
弁護士が交渉すれば会社が真摯に対応してくれる可能性があり、また適切に手続きを進めてもらえます。
労災申請の相談をしたい場合、ベンナビ労働問題を活用して、労働問題に強い弁護士を探しましょう。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

【不当解雇・残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る
【労災/不当解雇の解決実績◎多数!】会社の非協力による労災申請の拒否や、納得できない理由での一方的な解雇・退職強要など、深刻な労働トラブルも当事務所にご相談ください!4人の特色ある弁護士が、実績に裏付けられた対応力でサポートします◆【平日夜間のご相談可○】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
 この記事の監修
この記事の監修

弁護士法人若井綜合法律事務所

労働災害に関する新着コラム
-
業務中や通勤中の事故で働けなくなった場合、労災から休業補償を受けられる可能性があります。しかし、休業補償を受け取るためには、一定の条件を満たさなければなりません...
-
労働問題について悩んでいませんか?本記事では労基署の相談方法や電話で相談するときのポイントを解説します。労基署に電話で相談できれば、労働問題に関する悩みを気軽に...
-
うつ病と診断されたら無理をせず、休職するのも大切です。本記事では、うつ病で休職する際の手続き方法や相談先、休職期間の過ごし方や傷病手当金の申請方法などを紹介しま...
-
仕事が原因でうつ病を発症した場合は、労災保険給付を受給できますが、慰謝料などは労災保険給付の対象外です。本記事では仕事でうつ病になった際に、会社へ損害賠償請求を...
-
労働災害で死亡事故が発生したのに会社の対応に納得できない方が多くいらっしゃいます。本記事では、労働災害による死亡事故数などのデータ、死亡事故の実例、ご遺族が受け...
-
会社の同僚との飲み会で労災認定される可能性は低いですが、会社の支配下にある飲み会(強制参加など)であれば労災認定される可能性が高まります。本記事では、労災認定さ...
-
労災の休業補償の審査には、通常1ヵ月程度かかります。しかし、業務との関連性が不明瞭なケースではより長い時間がかかるでしょう。また、申請をしても必ず労災認定を受け...
-
本記事では、パワハラについて無料相談ができる窓口と、どの窓口に相談すべきかをわかりやすく解説します。「パワハラを本気でどうにかしたい」という方は、ぜひ参考にして...
-
労災申請の認定が下りないケースと、実際に認定が下りなかった場合の医療費負担について解説。また、労災の審査請求や雇用元への損害賠償請求といった、医療費の自己負担を...
-
仕事とプライベートの時間のバランスを保つためにも、労働時間と共に重要になることが、年間休日の数です。
労働災害に関する人気コラム
-
仕事とプライベートの時間のバランスを保つためにも、労働時間と共に重要になることが、年間休日の数です。
-
裁量労働制は、あらかじめ定められた労働時間に基づき報酬を支払う制度です。本記事では、裁量労働制のメリット・デメリットや仕組み、2024年の法改正における裁量労働...
-
「36協定について知りたい」、「残業が多いので会社に違法性がないか確認したい」などのお悩みを抱えている方に向けて、この記事では36協定の締結方法、時間外労働の上...
-
過労死ラインとは労災給付の基準であり、月に80〜100時間を超える労働は深刻な健康障害を引き起こす可能性が高いとして、抑制する取り組みが広まっています。この記事...
-
長時間労働による過労死は緊急を要する社会問題です。長時間労働を強いられているニュースをよく耳にしますが、他人事ではない働き方をしている方も多いでしょう。そこで、...
-
うつ病と診断されたら無理をせず、休職するのも大切です。本記事では、うつ病で休職する際の手続き方法や相談先、休職期間の過ごし方や傷病手当金の申請方法などを紹介しま...
-
本記事では、パワハラで労災認定を受けるための条件や手順などを解説します。パワハラを受けていて悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
-
雇用保険と社会保険はセットで考えられることが多いですが、保障内容や加入条件が正社員・アルバイトでも違います。また、会社は通常雇用保険と社会保険に加入させる義務が...
-
労働基準監督署は域内の事業所が労働基準法を守って運用しているか監督しています。勤務先の会社が労働基準法を守っていない場合、労基署に相談すると指導勧告をしてくれて...
-
仕事を辞めたい、鬱(うつ)になりそうと悩んでいる方は少なくないでしょう。うつ病は単なる甘えだと言われてしまうこともありますが、自分を追い詰めてしまう前に、休職や...
労働災害の関連コラム
-
仕事とプライベートの時間のバランスを保つためにも、労働時間と共に重要になることが、年間休日の数です。
-
雇用保険と社会保険はセットで考えられることが多いですが、保障内容や加入条件が正社員・アルバイトでも違います。また、会社は通常雇用保険と社会保険に加入させる義務が...
-
証拠保全(しょうこほぜん)とは、裁判で使う時の証拠をあらかじめ確保しておくことを言います。あらかじめ証拠を調べて集めておき、その証拠を使わなければ裁判が困難にな...
-
仕事が原因でうつ病を発症した場合は、労災保険給付を受給できますが、慰謝料などは労災保険給付の対象外です。本記事では仕事でうつ病になった際に、会社へ損害賠償請求を...
-
新型コロナウイルス感染症による労災は、どのような場合に認められるのでしょうか。新型コロナを起因とする労災認定の条件や具体的な認定事例、その際の主な労災補償の内容...
-
本記事では、パワハラで労災認定を受けるための条件や手順などを解説します。パワハラを受けていて悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
-
労災申請には「健康保険証は使わない」「未加入の場合も給付を受けることは可能」など意外と知られていない制度があります。労災は業務中の怪我・病気の治療費、生活費など...
-
労働者にとってセーフティネットとして利用できる雇用保険、条件を満たしていれば誰でも加入できますが、もし未加入だったときどうすればいいのでしょう。
-
労災の休業補償の審査には、通常1ヵ月程度かかります。しかし、業務との関連性が不明瞭なケースではより長い時間がかかるでしょう。また、申請をしても必ず労災認定を受け...
-
労働問題について悩んでいませんか?本記事では労基署の相談方法や電話で相談するときのポイントを解説します。労基署に電話で相談できれば、労働問題に関する悩みを気軽に...
-
通勤災害とは通勤中に被った傷病や死亡のことを指します。当記事では、通勤災害における補償内容や、労災保険として認定された通勤災害の事例、書類の記入例などをわかりや...
-
過労死の種類、厚生労働省が定める過労死の認定基準、労災保険制度の概要、申請時の注意点についてご説明します。
労災申請が棄却された場合、労働局に対して『審査請求』『再審査請求』ができますが、労災認定の詳細は、調査復命書を入手して分析する必要があります。裁決の検討も必要です。もし、『会社が労災を認めない』『労働基準監督署からの認定がおりなかった』という場合は、弁護士への相談も検討しましょう。
労災の申請方法と拒否・棄却された時の対処法労災における休業補償の時効は5年ですので、うつ病発症時期が問題となります。安全配慮義務違反にもとづく損害賠償請求は可能ですが、職務内容、会社の対応等を子細に検討する必要があります。持ち帰り残業となっていた場合は、時間外労働と認められない可能性の方が高いです。また、何度も会社に改善を訴えていている、労災が発生した事実を労基署に新国際ないのは『労災隠し』になりますので、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
労災隠しの実態と違法性とは|労災隠しされた場合の対処法3つ精神疾患の程度、ハラスメント行為との関係、会社対応などを精査しないと、正確な法的な助言は難しいです。法的分析をきちんとされたい場合には、労働法にかなり詳しく、労災法理、安全配慮義務法理、退職問題にも通じた弁護士に、今後の対応を相談してみましょう。
労災(労働災害)とは?適用条件・補償内容・申請方法の解説
正確なことがわからないので正確な助言は難しいですが、面接で伝えただけでは、合意内容になっているとは限りません。労働基準法違反かどうかは、労働基準法及び同規則所定の事項について記載があるかどうかですので、現物を拝見する必要があります。交渉の経緯、面接の内容も子細に検討する必要がございます。
法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しい弁護士に相談に行き、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。
まずはご冥福をお祈り致します。結論からいうと、過労死が認められる可能性は十分あると思います。心疾患の疑いだけであっても労災申請して認められているケースはありますので、チャレンジするのがいいと思います。ただ、過労死事件は特に初期のアプローチ(初動)が極めて大切なので、会社にどの段階でアプローチするのか、しないのか、どのようにして証拠を確保するのかなど、過労死問題をよく担当している弁護士と相談して対応すべきと考えます。
過労死で労災認定を受ける基準と給付を受けるために知っておくべきこと