会社が労働員を解雇する場合には、適切な解雇理由が必要です。
しかし、労働者の無知を利用して、理不尽な理由で解雇をしてくる会社も存在します。
自身の解雇に納得がいかない方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すれば、以下のようなメリットを得られます。
- 自身の解雇理由が適切かどうかわかる
- 損害賠償を請求できるかわかる
- 不当に解雇されずに済む可能性が高まる
- 自分で会社と交渉せずに済む
自身の解雇に納得がいかない方は、まずは弁護士の無料相談をご利用ください。

不当解雇(ふとうかいこ)とは、解雇条件を満たしていないか、解雇の手続きが正確ではなく、労働契約や就業規則の規程に沿わずに使用者が労働者を一方的に解雇することです。
独自の社内規則がある中小企業に不当解雇が多く、会社に言いくるめられる労働者もいます。
しかし、本来会社が労働者を解雇するには厳格な決まりがあり、それらの条件をクリアしていなければ、解雇として認められません。
今回は、不当解雇を受けた、または受けそうな方に対して、会社が解雇をできる条件と、不当解雇を受けてしまった後の対処法をご説明します。
会社が労働員を解雇する場合には、適切な解雇理由が必要です。
しかし、労働者の無知を利用して、理不尽な理由で解雇をしてくる会社も存在します。
自身の解雇に納得がいかない方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すれば、以下のようなメリットを得られます。
自身の解雇に納得がいかない方は、まずは弁護士の無料相談をご利用ください。
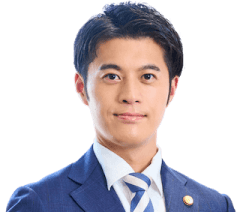

経済がなかなか良くならない現在の日本では、会社の都合で解雇をされてしまうことも少なくありません。解雇は、会社を存続させるために止むを得ないことでもあります。
しかし、会社は「ミスが多いから」「給料分の働きをしてないから」「反論してきたから」「怪我をして働けないから」などと簡単に労働者を切り捨てることはできません。
会社が労働者を解雇するにあたって、厳格な条件をクリアしていないと、それは「不当解雇」となります。それでは、以下で会社が労働者を解雇できる条件をご説明します。
まず、会社が労働者を解雇するには解雇せざるを得ない「客観的・合理的」な理由と「社会通念上の相当性」が必要です(労働契約法16条)。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。引用元:労働契約法16条
良くある解雇の理由から、どのような場合に解雇に客観的・合理的な理由があるのか解説します。
一般的に整理解雇(リストラ)と言われるものです。
ということですが、簡単にできるものではありません。
整理解雇の場合も解雇権濫用法理(労働契約法16条)の適用があり、整理解雇の4つの要件又は4つの要素が当てはまっている必要性があります。
本当に人員削減を行うほどの、重大な経営危機に陥っているか、客観的に存在するかが判断のポイントです。
ただ、数か月続けて赤字を出しただけや少し経費を抑えればなんとかなるような状態では、人員削減の必要性のある解雇とは認められないでしょう。
人員削減は止むを得ない事態であるが、それ以前にできる限りの処置をとっていたかも判断ポイントになります。
人員削減以外の具体的な処置は、「経営陣の賃金カット・求人のストップ・時間外労働の中止・希望退職者の募集」などがあります。
解雇される人員が不公平であってはいけません。客観的で合理的な基準に基づいて公平に選定されていることが必要です。
例えば「労働組合に入っていた・女性・担当部署」など会社の独断で選別してはいけません。
突然何の知らせもなく、解雇通告だけを送ることは、解雇として認められない可能性があります。
事前に会社の経済状況、整理解雇の必要性やその時期等を、労働組合や労働者に誠実に説明したうえで、『解雇通告』を送らないといけません。
労働基準法19条には業務上の傷病で「療養のために休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない」とあります。
また、妊娠をした女性に関しては、産前6週間と産後8週間は労働させることはできず、その後30日過ぎるまでに解雇することはできません。
つまり、業務で怪我をして休業になったからという理由で簡単に解雇をすることはできず、会社はその間も雇用し続けなくてはなりません。
もっとも、復職のめどが立たないほどの長期の休業は、解雇または休職期間満了による退職とされることもあります。
(解雇制限)
第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。引用元:労働基準法19条
「遅刻が多いから」「言うことを聞かないから」と確かに従業員に非があっても簡単に解雇することはできません。
解雇が有効になるには、解雇に「客観的に合理的な理由」があることと、解雇が「社会通念上相当」の処分と認められる必要があります。
以下の項目を基準に解雇に相当するかが判断されます。
労働者の単なる成績不良や能力不足を理由に解雇することは原則認められていません。
重大な経歴詐称をしていた場合は、解雇をされる可能性もあります。しかし、以下の項目に当てはまっている必要があります。
労働者が重大な問題を起こした場合は、懲戒解雇を受けることがあります。
通常の解雇と違い、解雇予告も解雇予告手当もなく即刻解雇されてしまい、退職金も支払われないことが多くあります。
ただし、即日解雇は労働基準監督署長の解雇予告の除外認定が必要になるなど会社側のリスクも大きいため、滅多に起こることはありません。
懲戒解雇に値しうる問題は以下の様な内容があります。
上記のように、解雇が有効になるには、解雇に「客観的にかつ合理的な理由」があることと、解雇が「社会通念上相当」の処分と認められる必要があります。

会社が労働者を解雇することはそう簡単にできるものではありません。
ここでは不当解雇になるであろう解雇の理由について解説していきます。
もし、あなたが解雇された理由が以下のようなものであれば、不当解雇の恐れがあります。
一度、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
上記でも説明しましたが、会社の経営不振による人員整理の解雇を整理解雇(リストラ)といいます。
しかし、リストラができる要件を満たしていない以下のような解雇は不当解雇の可能性があります。
懲戒解雇は、重大な企業秩序違反に対して行われる制裁としての解雇ですが、社会通念的に考えて懲戒解雇は厳しすぎると思える場合は不当解雇の可能性が出てきます。
また、解雇理由の内容が事実無根だと証明されれば不当解雇であるとして解雇の撤回を求めることも可能です。
以上のような内容は、不当解雇の可能性が十分にあります。
詳しい状況をまとめて弁護士へと相談されて下さい。
「ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)」では、労働問題を得意とする弁護士を掲載しておりますので、不当解雇問題に適した弁護士を素早く見つけることが可能です。

一方、こちらでは不当解雇ではなく正当な解雇であるだろうと考えられる内容を解説します。
細かい状況も加味したうえでの正当な解雇と認められるので一概には言えませんが、解雇としては認められるのではないかと思われる類型です。
『整理解雇』は上記の4つの要件又は4つの要素を満たしていないといけませんが、小さな会社や会社で危機的な問題が発生した場合は、会社の経営を存続させ再起するためには止むを得ないとして一部考慮されることもあります。
不治の病や業務外の事故で再起不能となったり、長期入院をせざるを得なくなり、職務が長期にわたって困難、不可能となった場合、普通解雇が正当とされることがあります。
「横領等の刑事事件を起こして裁判になり判決が確定したので解雇された」
「諸手当の不正受給を繰り返して会社に大きな損害を与えたので解雇された」
「会社の売上に直結する顧客の依頼を理由もなく故意に断っていたので解雇された」 など
以上の内容を元に正当な解雇か不当解雇かを判断されてみてください。
「怪しいのだけどどうだろう・・・」と確信を持てない方は、どのような状況かを細かくまとめ(不当解雇かどうかは明確な基準がないため少しの状況の違いで変わってきます)弁護士に相談されてもいいでしょう。
こちらでは、不当解雇を受けていたと判明した際に取れる行動をお伝えします。
不当解雇の対処法は大きく分けて以下の3つになります。自身が望む結果に一番近い方法を検討されてみたはいかがでしょうか。
不当解雇だった場合、解雇自体が無効となるため解雇を撤回してもらうよう交渉することができます。
解雇された会社でまた働きたいという方は多くはありませんが「この会社でもう一度働きたい」という気持ちが強い方は、解雇撤回を要求するとの方法を検討してみてください。
不当に懲戒解雇を受けた方は、撤回してもらうように会社と交渉することが賢明です。
懲戒解雇になってしまうと、退職金が支給されないことがあります。また、退職理由が懲戒解雇であると次に就職する際に不利になる可能性があります。
会社と不当解雇問題で問題になった場合多い対処法が、賃金の請求です。不当解雇だった場合、解雇されていないとみなされその間に発生した給料を請求することが可能です。
「不当解雇後に生じた賃金を請求する方法」を参考にして下さい。
解雇に納得いっていないとはいえ、会社と争うことは労力を使います。裁判が長引いたり、勝てるかどうかも微妙な場合は解雇に関する保障等を利用しつつ、早急に次の仕事先を見つけることも一つの手です。
こちらでは、受けてしまった不当解雇を撤回する方法をご説明します。
何度もお伝えしておりますが、「会社は簡単に従業員を解雇することはできません。」立場の弱い労働者を保護するために、労働契約法は正当な理由のない解雇を禁止しています。
従業員を解雇するためには、解雇が客観的に合理的であり、社会通念上相当であることを、会社が立証しなければなりません。
この立証ハードルは決して低いものでは有りません。
解雇を撤回するには、期間が空いてしまうと状況が不利になりますので、まずは早急に弁護士に相談をすることです。
会社による解雇の有効・無効は、純粋に民事的な問題であるため相談先は弁護士です。
弁護士であれば、事案を踏まえて解雇の有効性について見通しその他的確なアドバイスが期待できます。
また、弁護士は裁判外での交渉にも慣れていますし、万が一裁判に発展した際にも頼りになります。
弁護士にもそれぞれ得意分野がありますから、プロフィールに「労働トラブルを中心に依頼を受けています」「労働事件の実績豊富」などと記載されている人を選びましょう。

「不当解雇」された方の場合、当面の生活費への不安から弁護士費用をすぐに用意することが難しいケースも多いかもしれません。
最近では、初期費用をなるべく抑えた報酬システムを採用している弁護士も増えています。無料法律相談も利用しながら、自分に合った弁護士を探しましょう。
納得できない解雇の予告を受けた場合、すぐに会社に対して「解雇理由証明書」を請求しましょう。
解雇予告を受けた従業員が、退職までの間に当該書類を請求した場合、会社は、法律上、これを拒否することができません。
なお、解雇理由証明書を求めたのに、これが明確にされなかったという事実は、解雇の効力を争う際に、労働者側に有利な事情となり得ます。
そのため、解雇理由証明書の交付請求は、口頭ではなくて、Emailなど形の残るように行うべきでしょう。
解雇理由と就業規則・法律を見合わせて、不当解雇かどうかを確認しましょう。
解雇の有効性が争われる場合、これが有効であること(解雇が客観的に合理的で、社会通念上相当であること)は会社側が立証する責任があります。
が、労働者側も反証として積極的に証拠を提出することが望ましいです。
労働者側で提出する証拠としては以下のようなものが考えられます。
一番の方法は、内容証明郵便で「働き続ける意思がある」ということを通知して下さい。
気をつけていただきたいことは、復職を望んでいるのであれば退職を認めるような行動は取らないようにして下さい。
「復職を求めているのになぜ?」とつじつまが合わなくなります。例えば「退職金の請求、有給買い取りの申請、解雇予告手当の請求」などです。
「保険証の返還、退職金の受け取り、離職票の受け取り」などを会社から要求された場合、そちらに応じても構いません。
しかし、復職を望むのであればここで支払われた金銭には必ず手を付けずにいましょう。
解雇の撤回が確実に受け入れられるとは限りません。そのまま解雇されてしまうことを考えて、同時進行で行いましょう。
「雇用保険の受領(解雇が撤回されれば返還します)、就職活動、健康保険の手続き」などがあります。
弁護士のアドバイス・解雇理由の不当性・内容証明郵便を元に会社と「不当解雇に当たるので解雇の撤回を求める」と交渉の場を設けて下さい。
両者での折り合いが付けば、労力をかけずにこちらで解決します。
解雇の効力を争う場合、いきなり会社に労働審判や訴訟提起を行う方法もありますが、もし話合いで解決する可能性があるのであれば、訴外で会社と交渉することも検討に値します。
このような交渉や法的手続は、通常は、弁護士に依頼するべきでしょう。解雇の有効・無効についての判断は素人には極めて難しいからです。
その場合は、法的処置を取り、強制的に話し合いの場を設けることが可能です。
不当解雇の撤回を望んでいる場合は比較的簡単に行える「労働審判」がおすすめです。
個人で最後まで交渉することも可能ですが、弁護士に依頼をすることがより確実です。
不当解雇の事案では解雇の有効性を争うのと同時に、不就労期間中の賃金を請求するのが通常です。
会社が解雇した場合、労働者は就労の機会を奪われることになり、不就労期間中は賃金を支払ってもらえません。
しかし、解雇が無効となった場合、当該不就労は会社の責任によるものであるということになり、労働者は不就労期間中の賃金請求が可能となります。
したがって、解雇の有効性を争う場合は、当該解雇に伴い就労できなかった期間中の賃金を請求するのがセオリーです。
不当解雇後に生じた賃金を請求する際も方法と変わりません。
ただ、目的が解雇撤回ではなくて賃金の請求になります。前提として「働き続けたかったのだけど、不当解雇をされた。その間に発生した賃金を請求します。」というスタンスを取ります。
なので、こちらでも退職を認めるような「退職金の請求や有給買い取りの申請、解雇予告手当の請求」を同時に行わないように気をつけて下さい。
なお、解雇手続があまりに杜撰であったり、違法性の程度が強いような場合、上記賃金請求とは別に、解雇行為それ自体により被った精神的苦痛について、損害賠償を求めることができる場合もあります。
しかし、通常はこのような精神的苦痛は賃金が支払われることにより、慰謝されるものと考えられていますので、このような慰謝料請求ができるケースはよほど悪質な場合に限定されています。
こちらでは、不当解雇を解雇と認め、その他の賃金を請求する方法を解説します。
ただ、懲戒解雇を受けた方は、退職金等の金銭的な支払を受けられないこともありますので、懲戒解雇に不服の方は上記の不当解雇を訴えた2つの方法を取りましょう。
解雇は30日以上前に告知されていないといけません。それ以前に突然解雇をされてしまったのであれば「解雇予告手当」を請求することができます。
転職のために自ら退職することを「自己都合退職」、解雇されることを「会社都合退職」と言います。
就業規則等に退職金の支給基準がない場合は、使用者に退職金の支払義務はありません。
退職金の支給基準が定められている場合も会社の基準によって支給額が異なってきます。自分の場合に、退職金が支払われるかどうかを退職金規程等で確認しましょう。
整理解雇のようなケースでは退職金の積み上げを要求するなどの「交渉」がされることがあります。
原則として有給の買い取りは禁止されていますが、退職者に関してはこれ以上有給を消化することができない場合もあるので、会社は例外的に有給休暇の買い取りをするとができます。
ただし、買い取りの方法や金額に関して就業規則等で定められていない場合は、会社が有給を買い取るかどうかとその金額を交渉によって決めることになります。たとえ極端に金額が安くても違法とはいえません。
有給に関しては「交渉次第」になります。
失業手当とは、雇用保険の被保険者の方が離職し、新たな就職先を探すための支援等のために支払われる給付金です。
失業保険により失業手当を受けるにはいくつかの条件があります。
不当解雇をする会社は、どこかしらの不具合があることも考えられます。
率直に言えば「解雇されてしまった会社の労働環境はもうどうでもいいけど、支払われていなかった賃金はちゃんと支払ってもらいたい。」と思うものですよね。
代表的なものに「未払い残業代」があります。
こちらも、会社と事実関係だけではなく法的にも争うことになりますので、手続きが複雑になることが十分考えられます。
しかし、残業が多いような方は、請求額が何百万になることもあります。
以上のように会社が労働者を解雇することは、条件も厳しくそれに付随してのリスクも発生してくるので会社はあらゆる手を使って労働者を自主退社に追い込もうとしてくることがあります。
以下の内容が当てはまる方は気をつけて下さい。自ら退職してしまったら、会社の思いのままで損をしてしまいます。
労働者を自主退社に追い込もうと使ってくる手の中で、代表的なものが「パワハラ」です。
退職届を出す前に弁護士などの専門家に相談することもひとつの手段です。
口頭で上司に「お前なんかクビだ!」なんて言われてしまったら、頭に来て「分かった!こんな会社辞めてやる!」と思うこともあります。
しかし、ここで退職届を上司に突き付けて会社を辞めたらスッキリするかもしれませんが、自主的に退職したとして「自己都合退社」として処理されてしまします。
口頭で「クビだ」と言われても、決して認めず冷静になって「退職の理由」をしっかりと聞きましょう。
一方的に労働者を辞めさせるという解雇ではなく、使用者が労働者に対して辞職や退職に誘導することを「退職勧奨」といいます。
簡単に言うと、「君にこの仕事は向いていない」などといろいろと理由をつけて「退職届を出したらどうか」「辞めたらどうだ」と勧めてくることです。
もちろん、退職勧奨には応じる義務はありません。辞めたくないのであればしっかりと断りましょう。
断り続けても執拗に退職勧奨してきたり、断ったからと不当に部署異動させられたりするとなると、新たな問題に発展します。
しっかりと、状況を証明できる証拠を押さえ、弁護士に相談しましょう。
繰り返しになりますが、解雇は簡単に行えません。
もしも、不当解雇の疑いのある辞めさせられ方をしたのであれば、「明確な状況内容」と「解雇に対してどうしたいのか」をまとめて、早急に弁護士に相談してみてください。
会社が労働員を解雇する場合には、適切な解雇理由が必要です。
しかし、労働者の無知を利用して、理不尽な理由で解雇をしてくる会社も存在します。
自身の解雇に納得がいかない方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すれば、以下のようなメリットを得られます。
自身の解雇に納得がいかない方は、まずは弁護士の無料相談をご利用ください。
不当解雇に該当する場合は、解雇予告手当などの賃金が請求できます
不当解雇は労働問題の中でも今後の生活に多大な影響を与える重大な問題です。
「客観的かつ合理的なな理由』が会社から示されていない場合、解雇自体の撤回を求めることもできますし、もし退職をする場合でも、30日以上前に行われるべき『解雇予告』がなされていないのであれば、『解雇予告手当』として、【1日分の平均賃金 × (30日-足りない日数分)】の金銭が請求できます。
【例:10日前に予告した場合】
30日 - 10日 = 20日分の平均賃金支払いの義務
もし解雇を撤回するには、期間が空いてしまうと状況が不利になりますので、まずは早急に弁護士に相談をすることをおすすめします。
不当解雇を弁護士に依頼することで
・不当解雇の撤回
・不当解雇後の賃金請求
などの結果が望めます。不当解雇でお困りの方は早急に弁護士への相談をしましょう。

【不当解雇・残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る

会社から突然解雇を告げられると、大きなショックを受ける方がほとんどでしょう。本記事では、即日解雇が認められる3つの条件と、即日解雇の条件を満たしているかどうか確...
会社から突然解雇を告げられた方の中には「おかしい」と思いながらも、そのまま泣き寝入りになっている方も少なくないかもしれません。本記事では、突然解雇された場合の対...
本記事では、不当解雇をされた場合の相談先を紹介するとともに、ハローワークではどのような相談ができるのか、詳しく解説していきます。
会社都合退職とは、解雇や退職勧奨などの会社側の都合により労働者との雇用契約を終了することです。会社都合退職として認められるケースや、会社都合退職のメリット・デメ...
能力不足を理由したクビは違法な場合があります。本記事では能力不足で会社をクビになった場合の違法性や対処法を紹介します。
本記事では、会社から不本意に退職届を書かされた場合の対処法などについて解説します。
懲戒解雇とは、労働者へのペナルティとしておこなわれる解雇のことです。懲戒処分のなかでも最も重い処分であり、適正な手続きのもとでおこなう必要があります。本記事では...
近頃、新型コロナを理由に解雇や内定取り消しにあったという事例が増えつつありますが、実は違法かもしれません。この記事では、コロナ禍で解雇が認められる要件や解雇を言...
新型コロナによりリストラや倒産が増加傾向にあります。リストラには4種類あり、会社の方法によっては不当解雇の可能性もあります。この記事ではリストラの種類と不当解雇...
妊娠中の女性を悩ませている解雇問題ですが、妊娠を理由にした解雇は違法性が非常に高いと言えます。妊娠した女性が解雇されたらどのような対処法が取れるのか?ということ...
懲戒解雇とは、労働者へのペナルティとしておこなわれる解雇のことです。懲戒処分のなかでも最も重い処分であり、適正な手続きのもとでおこなう必要があります。本記事では...
会社が従業員を辞めさせるためによくやる退職勧奨の手口やその対処法を解説します。
雇い止めは契約更新をせずに契約期間満了を理由に契約を終了させることですが、何が悪いのか?という疑問を雇用側は思っています。現在は新型コロナによる深刻な労働問題と...
雇用保険と社会保険はセットで考えられることが多いですが、保障内容や加入条件が正社員・アルバイトでも違います。また、会社は通常雇用保険と社会保険に加入させる義務が...
労働基準監督署は域内の事業所が労働基準法を守って運用しているか監督しています。勤務先の会社が労働基準法を守っていない場合、労基署に相談すると指導勧告をしてくれて...
休日出勤とは、その名の通り休日に出勤することです。会社によっては休日出勤が当たり前のようになっている所もあるでしょうし、本来払われるべき休日手当が支給されない企...
会社が従業員を解雇する場合、解雇理由は正当なものでなければいけません。解雇理由が不当な場合、不当解雇として解雇の撤回や未払い賃金の獲得などが望めます。本記事では...
退職までの手続きを徹底解説!大企業の終身雇用が崩れ始める中、退職と転職は身近なものになってきています。昨今の新型コロナウィルスの影響で突然解雇を言い渡される方も...
不当解雇(ふとうかいこ)とは、解雇条件を満たしていないか、解雇の手続きが正確ではなく、労働契約や就業規則の規程に沿わずに使用者が労働者を一方的に解雇する行為です...
会社都合退職とは、解雇や退職勧奨などの会社側の都合により労働者との雇用契約を終了することです。会社都合退職として認められるケースや、会社都合退職のメリット・デメ...
弁護士依頼前の様々な疑問・不満を抱えている方も多いでしょう。今回は、それら労働問題の弁護士選び方に関する内容をお伝えしていきます。
不当解雇とは、労働基準法や就業規則の規定を守らずに、事業主の都合で一方的に労働者を解雇することをいいます。本記事では、不当解雇と通常解雇との違いや、解雇された際...
労働する際に、会社から誓約書にサインを求められることがあります。中には誓約書に理不尽なことが書かれていて会社とトラブルになってしまった方もいるのではないでしょう...
試用期間中に解雇されるのは違法なのでしょうか。もし試用期間が終わる前に「期待ほどの能力がなかった」「明日から来なくていい」と告げられるのは不当解雇の可能性があり...
不当解雇をされてしまった労働者が訴訟を検討している場合、裁判はどのように進み、費用はいくらかかるのか、不当解雇裁判に関わる手続きやかかる期間などについて解説して...
諭旨解雇(ゆしかいこ)とは、「懲戒解雇」の次に重い懲戒処分です。従業員を諭旨解雇する際、従業員とのトラブルを避けるために法律上の要件を踏まえて対応する必要があり...
取締役の解任については労働者の解雇とは法律上の取扱いが異なり、会社側で履践するべき手続や責任の内容は全く違います。今回は取締役の解任をテーマに、基本的なルールや...
護士に「内定取消し」トラブルを依頼した場合の費用について解説!金銭的に余裕がない就活中の学生でも、支払える金額なのでしょうか?弁護士費用の相場と内訳をご紹介する...
労働基準監督署は域内の事業所が労働基準法を守って運用しているか監督しています。勤務先の会社が労働基準法を守っていない場合、労基署に相談すると指導勧告をしてくれて...
本記事では、不当解雇をされた場合の相談先を紹介するとともに、ハローワークではどのような相談ができるのか、詳しく解説していきます。
本記事では、不当解雇を解決するために弁護士へ依頼するメリットや弁護士費用などを解説します。
試用期間中に「この会社合わないかも…。」と思って退職を考える人もいるでしょう。試用期間中の退職は正社員同様、退職日の申し出や退職届などが決まっています。この記事...
不法な解雇により労働者に不利益が生じた場合、労働者は企業相手に慰謝料請求を行うことが出来ます。
その際請求が出来るのは、解雇されたことにより受け取れなかった期待賃金になります。
ただし、解雇の不当性は弁護士を通じて正しく立証する必要があります。
不当解雇を防ぐために自己都合退職を迫る、「退職勧奨」の手口です。
会社から退職を勧められたとしても、それに従う必要はありません。今の会社に残りたいと考えるならば、拒み続けても問題ありませんので、安易に退職届にサインをするのは控えましょう。
それでもパワハラなどを絡めて退職を強要してきた場合には、損害賠償を請求できる可能性が生じますので弁護士に相談するのも一つの手です。
リストラ(整理解雇)を行うためには、選定の合理的理由や、解雇回避努力の履行など、企業側が満たすべき要件が複数あります。
上層部の私情によるものや、勤務態度や成績に依存しないリストラは認められないと定められています。
就業規則に明記されていない限り、会社が何らかの事由によって懲戒解雇処分を通知することは出来ません。まずは会社の就業規則を確認しましょう。
また、重大な犯罪行為や重大な経歴詐称など、著しく重要な問題に抵触しない限り懲戒解雇を受けることはありません。
会社の裁量基準に納得がいかず、撤回を求めたい方は早急に弁護士に相談しましょう。
前提として、企業は求職者を採用する際に長期契約を念頭において雇用契約を結ぶため、試用期間を設けられたとしても「向いてなさそうだから…」や「なんか気にくわない…」という理由で一方的に解雇することは出来ません。
もし解雇に妥当性がないと言い張る場合は、解雇の撤回を要求するか、解雇されなかった場合に受け取れるであろう期待未払い賃金の請求が可能です。


